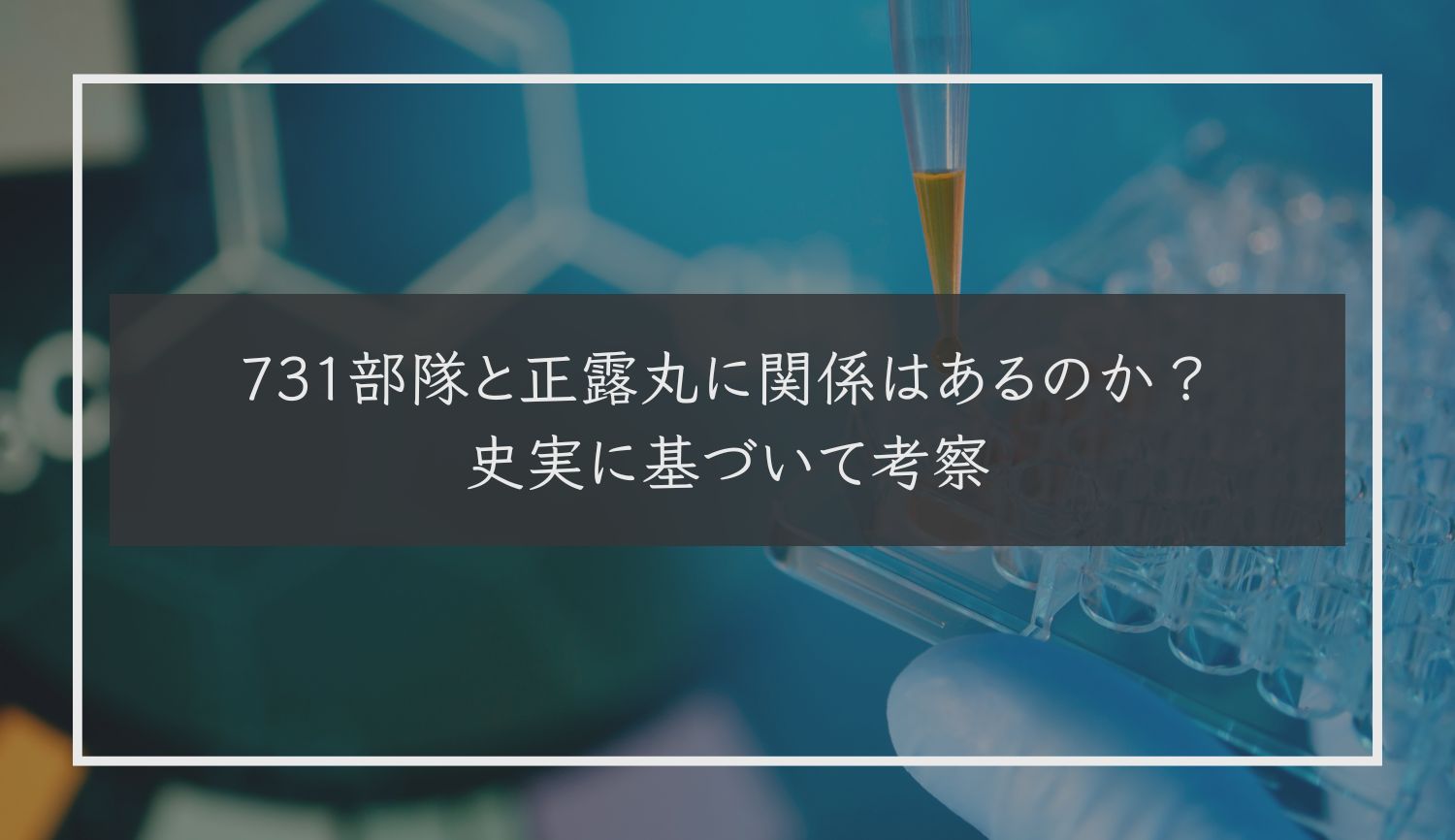日本の戦時医療史において、「731部隊」と「正露丸」はともに知られた存在ですが、両者の関係については誤解や混同が見られることがあります。
本記事では、731部隊と正露丸の歴史的背景を整理し、両者の関係性について史実に基づいた考察を行います。軍事医療という共通点を持ちながらも、その目的や性質は根本的に異なる両者の真実に迫ります。
731部隊とは?
731部隊は、第二次世界大戦期の大日本帝国陸軍に存在した研究機関です。正式名称は「関東軍防疫給水部」で、731部隊という名称はその秘匿名称(通称号)「満洲第七三一部隊」の略称です。1941年3月に通称号が導入されるまでは、指揮官であった石井四郎の苗字を取って「石井部隊」とも呼ばれていました。
表向きには兵士の感染症予防や衛生的な給水体制の研究を主任務としていましたが、実際には細菌戦に使用する生物兵器の研究・開発機関でもありました。石井四郎は1925年にジュネーブ議定書で化学兵器と細菌兵器の使用が禁止されたことを受け、「禁止しなければならないほど細菌兵器が脅威であり、有効であるなら、これを開発しない手はない」と考えたとされています。
1932年に陸軍軍医学校防疫部の下に石井らによる防疫研究室(別名「三研」)が開設され、翌1933年には満州の背陰河で研究が始まりました。1936年には関東軍参謀長の板垣征四郎によって「関東軍防疫部」の新設が提案され、同年8月に正式発足しました。1940年には現在の中国黒竜江省ハルビン郊外の平房に新施設が完成し、「関東軍防疫給水部(通称号:満洲第659部隊)」に改編されました。
731部隊の活動内容は極めて非人道的なものでした。NHKが発掘した旧ソ連・ハバロフスク裁判の音声記録によれば、部隊幹部らが日本に反発した中国や旧ソ連の人々を「死刑囚」として実験材料にしていた実態が明らかになっています。川島清軍医少将(731部隊第4部長)の証言によれば、実験の犠牲者は3,000人以上とされています。
731部隊と正露丸に関係はあるのか?
結論から言えば、731部隊と正露丸の間に直接的な関係はありません。両者は日本の軍事医療史において全く異なる文脈で登場する存在です。
正露丸は1902年(明治35年)、日露戦争開戦2年前に大阪市天王寺区の中島佐一氏によって「忠勇征露丸」として製造販売が開始されました。
当時、日本の軍隊にとって衛生状態の悪い外地において兵士の死亡原因が、戦闘での戦死より病死の方が多いことは大きな問題でした。クレオソートを主成分とする正露丸は、その後1904年の日露戦争で「征露丸」と名付けられ、兵士全員に服用を命じられていました。
一方、731部隊が正式に発足したのは1936年(昭和11年)であり、日露戦争(1904-1905年)から約30年後のことです。時代背景も活動内容も全く異なります。正露丸は消化器系疾患の治療薬として実用的に使用されていましたが、731部隊は細菌兵器の研究・開発を秘密裏に行っていた組織でした。
なぜ両者が混同されることがあるのかについては、以下の理由が考えられます:
- どちらも日本の軍事医療に関連している
- 731部隊の隊長だった石井四郎が「石井式濾水機」を開発したことと、正露丸も軍隊で使用された薬であったことから、両者を結びつける誤解が生じやすい
- 戦時中の軍事医学に関する情報の断片化
しかし、史実に基づけば、731部隊と正露丸の間に開発・製造・使用における直接的な関係性は見出せません。
正露丸は軍事利用されていたのか?
正露丸は確かに軍事目的で広く利用されていました。「征露丸」という名称自体が、「ロシアを征する丸薬」という意味合いを持っており、日露戦争前の緊張関係を反映したものでした。
正露丸の主成分である木クレオソートは、1830年にドイツの化学者カール・ライヘンバッハ氏がヨーロッパブナから抽出した成分で、当初は化膿傷の治療に使用されていましたが、後に高い殺菌効果から防腐剤や胃腸薬として利用されるようになりました。日本には江戸時代後期の1839年に長崎のオランダ商館長によって持ち込まれ、「結麗阿曹多(ケレヲソート)」と呼ばれていました。

日清戦争で不衛生な水を飲んだことによる感染症の拡大に悩まされた日本陸軍は、クレオソート剤にチフス菌の抑制効果があることを発見しました。1904年の日露戦争では、「征露丸」として兵士全員に支給され服用させていました。
『明治三十七八年戦役陸軍衛生史』によれば、「戦役ノ初メヨリ諸種ノ便宜上結列阿曹篤(クレオソート)ヲ丸トシテ之ヲ征露丸ト名ケ出世者全部ニ支給」したとあります4。この服用により、下痢や腹痛で戦闘不能になる兵士は激減したとされています。
興味深いことに、当初は脚気の予防を期待して、またチフスや赤痢に対する効果、つまり水あたりや消化器系伝染病の予防薬として陸軍で日露戦争中に多用されました。しかし、脚気に対しては全く効果がなく、日露戦争の全将兵の3分の1に当たる約25万人が脚気に罹り、2万7800人が死亡しています。
軍隊での「征露丸」の配給は、日露戦争が終結した翌年の1906年に廃止されましたが、戦勝ムードに乗って一般家庭に普及しました。戦前は中島佐一薬房が「忠勇征露丸」の商標を持っていましたが、1946年に「忠勇征露丸」の製造・販売を大幸薬品が引き継ぎました4。
1949年には敗戦国の日本が戦勝国のロシアを「征する」という商標は問題だとの行政指導を受け、「忠勇征露丸」から「中島正露丸」に商標を変更し、さらに1954年には単に「正露丸」となりました。
731部隊の医学的役割
731部隊の公的な任務は防疫と給水でしたが、実際には人体実験を伴う細菌戦の研究が主要な活動でした。しかし、公的活動の一環として行われていた技術開発もありました。
その代表例が「石井式濾水機」です。これは731部隊の隊長だった石井四郎が開発した濾水機で、汚水から細菌を取り除く装置として、飲料水確保のため野戦で使用されていました。しかし、常石敬一神奈川大名誉教授(科学史)によれば、この濾水機は実際には欠陥品だったとされています。
731部隊が中国でコレラ菌をまいた1942年の浙贛作戦では、入院1万人、死亡1700人と日本兵の側にも大きな被害が出たと報告されています。石井が濾水機の開発を始めたのは、中国と戦争状態に入った1930年代前半で、陸軍はこれを評価し前線で使用しました。
金沢市内の医療施設から2017年、陸上自衛隊化学学校のある大宮駐屯地(さいたま市)の史料施設に「石井式濾水機」が寄贈されていたことが分かっています。この濾水機が敗戦時に中国から持ち帰られた可能性があるとされています1。
石井式濾水機が優秀と認められたことで石井の発言力が高まり、それが細菌戦の研究と遂行を軍内で認めさせ、非人道的な生体実験につながっていったという指摘もあります。
731部隊には京都帝大医学部をはじめとする当時の一流大学から多くの医学者が参加していました。石川太刀雄丸(病理学)、岡本耕造(解剖学)、田部井和(チフス研究)、湊正男(コレラ研究)、吉村寿人(凍傷研究)、笠原四郎(ウイルス研究)、二木秀雄(結核研究)、貴宝院秋夫(天然痘研究)などが石井の元に集められました。
1945年8月のソ連対日参戦により、731部隊は速やかに日本本土方面への撤退を図りました。敗戦に際して軍は関連文書の処分を命じ、証拠隠滅を図りました。戦後、部隊に所属していた医師たちは、アメリカに研究資料などを提供する見返りとして戦犯免責を受けました。
1947年5月6日、米軍極東司令部は米国防省に軍事機密電報を送り、石井四郎から得た報告書などの資料を含め、関係資料を情報チャンネルに留め置き、戦争犯罪の証拠として使用しないことを提案しました。1948年3月13日、統合参謀本部はマッカーサーに対してこの提案を認める回答を送っています。
最近の研究によれば、これまで終戦時に撤収したと考えられていた731部隊の一部、52人が中国にとどまり、拘束されて旧ソ連に送還されたり、身分を偽って中国国内に潜んだりしていたことが明らかになっています7。
まとめ:日本の軍事医療史から考える倫理と責任
731部隊と正露丸は、日本の軍事医療史において全く異なる役割と意義を持っていました。正露丸は軍事目的で使用され、後に民間の医薬品として成功した例である一方、731部隊は医学の知識と技術を最も非人道的な形で悪用した例です。
両者の共通点は「軍事医療」という広い文脈のみであり、731部隊が正露丸を開発・製造したという事実はありません。正露丸は日露戦争(1904-1905年)の時期に既に軍で使用されていましたが、731部隊が正式に発足したのは1936年であり、時代的にも重なりません。
この誤解が生じる背景には、日本の戦時中の活動に関する情報の断片化や、軍事医療という共通のキーワードで両者が結びつけられやすい状況があると考えられます。
731部隊の非人道的行為は、医学倫理の根本的な問題を提起しています。医学の進歩が人類の幸福につながるためには、強固な倫理観と人道的価値観に基づいた判断が必要です。石井式濾水機の例に見られるように、科学技術の評価と倫理的判断は別次元の問題であり、技術的な「有用性」と倫理的な「正当性」を混同することの危険性を示しています。
一方、正露丸は軍事目的で開発・使用されながらも、その後一般医薬品として平和的用途に転換された事例です。現在も家庭の常備薬として親しまれている正露丸の歴史は、軍事技術の民間転用という観点から見ても興味深い事例と言えるでしょう。
歴史を正確に記憶し、継承することは、過去の過ちを繰り返さないために不可欠です。731部隊と正露丸の歴史は、医学と戦争、科学と倫理の関係について深く考えさせる教訓となっています。現代社会においても、科学技術の発展と倫理的判断の関係は常に問われる問題であり、過去の歴史から学ぶことの重要性は変わりません。
近年、731部隊の歴史を正確に伝え、記憶していこうという動きが強まっています。長野県飯田市の「飯田市平和祈念館を考える会」や石川県でのパネル展など、過去の戦争の事実を伝えることで反戦を呼びかける活動が各地で行われています。これらの活動は、歴史的真実を継承し、平和な未来を構築するための重要な一歩と言えるでしょう。