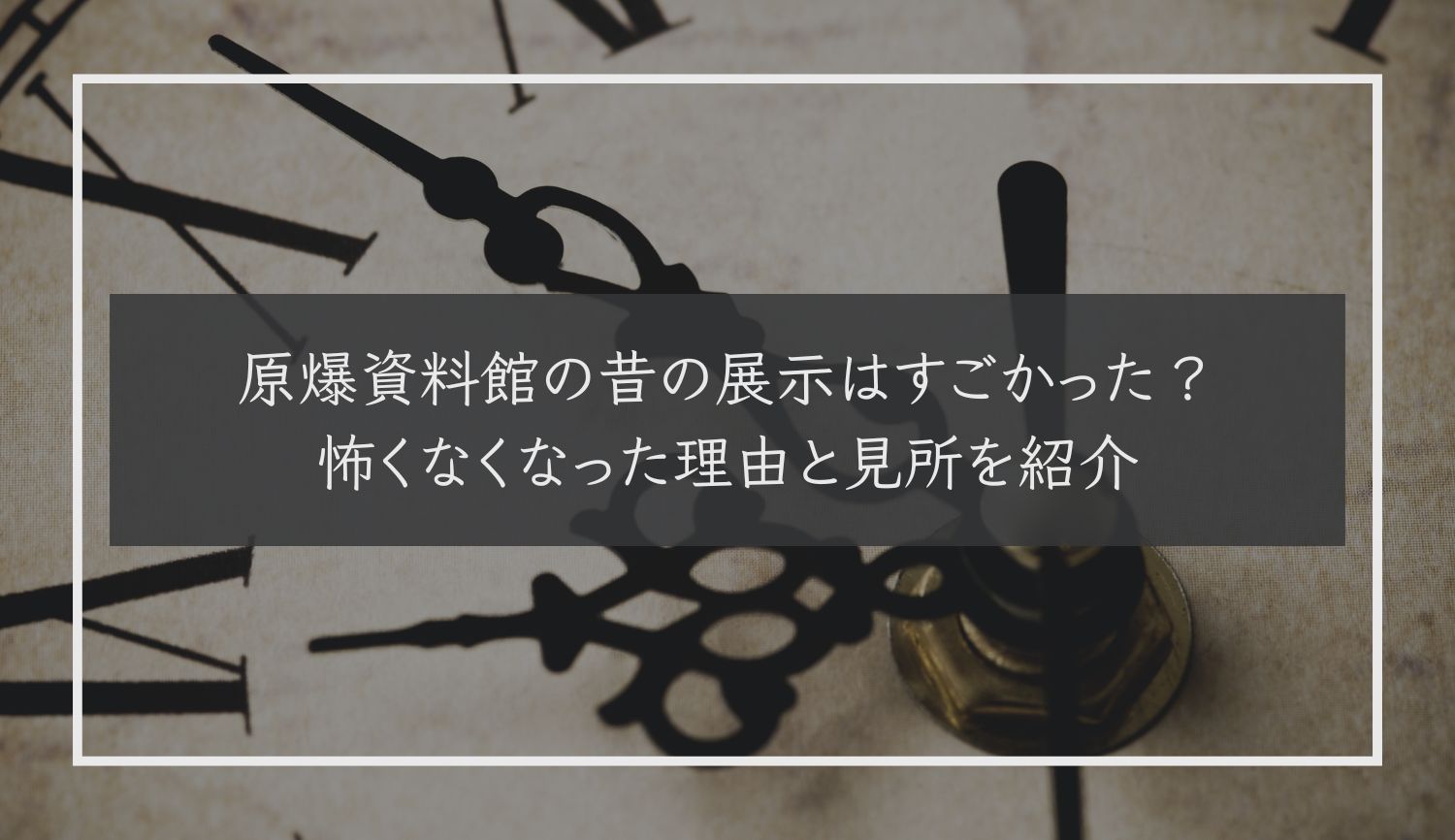広島・長崎に投下された原子爆弾。その惨禍を後世に伝え、核兵器廃絶を訴える原爆資料館は、日本人のみならず多くの外国人観光客も訪れる重要な施設です。
近年、「昔より怖くなくなった」と言われることもある展示ですが、その背景には単なる演出の変更ではなく、被爆者の高齢化や時代の変化に対応した深い意図があります。本記事では博物館展示の専門的視点から、原爆資料館の展示の変遷と現在の見どころを解説します。
原爆資料館の概要
原爆資料館は広島と長崎の2カ所にあり、それぞれ特色があります。
広島平和記念資料館(広島原爆資料館)は1955年に開館し、平和記念公園内に位置しています。本館と東館の2棟構成で約2万点もの資料を所蔵しており、2019年4月に大規模なリニューアルオープンを果たしました。
長崎原爆資料館は長崎市平野町にあり、「1945年8月9日」「原爆による被害」「核兵器のない世界」「ビデオルーム・Q&Aコーナー」の4つのテーマで展示が行われています。長崎でも被爆80年にあたる2025年に向けて展示内容の更新が計画されています。
両施設は単なる歴史博物館ではなく、原爆の記憶を継承し平和を希求するという明確な理念を持った施設です。入館料は一般200円前後と比較的安価で、多くの人が訪問しやすい環境が整えられています。
原爆資料館の昔の展示はすごかった?
「昔の展示はすごかった」と言われる最大の理由は、広島平和記念資料館に展示されていた被爆者のろう人形でしょう。火傷や外傷を負った被爆者の姿を精巧に再現したこれらの展示は、特に修学旅行生や子どもたちに強烈な印象を残していました。当時の子どもたちの感想文はろう人形に関するものが多く、トラウマになる子どもも少なくなかったようです。
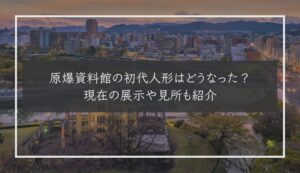
また、展示方法にもかなりの違いがありました。以前は原爆の破壊力に焦点を当て、被害の全体像をマクロな視点から見せる展示が中心でした。焼け焦げた衣服、溶けたガラス瓶、黒焦げになった弁当箱などが並び、原爆の熱線や爆風がいかに強烈だったかを視覚的に伝える内容でした。
展示の構成も大きく異なっていました。以前の広島平和記念資料館では、原爆開発や投下までの経緯などの展示を前半に配置していましたが、平均滞在時間が短いため、多くの訪問者が実際の被爆資料を十分に見ることができないという課題がありました。
当時の展示があまりにもショッキングだったことは、1960年に浜井広島市長が「資料館が被爆者や遺族に残酷な思い出をよみがえらせ苦痛を与えている」と発言し、資料館を美術館に転用する案を検討したことからも分かります。
怖くなくなったと言われる理由
けれども、現代の展示は昔と比べて怖くなくなったと言われています。
一体どうしてなのでしょうか?
理由1:展示手法の進化
原爆資料館の展示が「怖くなくなった」と言われる大きな理由は、展示手法の進化です。特に象徴的なのは、広島平和記念資料館から、かつて多くの訪問者に強烈なインパクトを与えていたろう人形が撤去され、実物資料中心の展示に変わったことです。

ろう人形は被爆直後の惨状を視覚的に伝える一方で、あまりにもショッキングなため、訪問者が恐怖心から展示の本質的な意味を理解できなくなるというデメリットもありました。この変更について修学旅行の引率教員からは「従来は子どもの感想文がろう人形に集中していた。新しい展示で惨状が伝わるのか、子どもの反応に注目したい」という声もあります。
実物資料中心への移行は、博物館学の観点からも理にかなっています。創作されたろう人形よりも、実際の被爆した物や写真の方が真正性が高く、来館者の理解を深める上でより効果的とされています。
理由2:個人の物語重視のアプローチ
今日の展示ではマクロな視点からミクロな視点へのシフトが見られます。以前は原爆の威力や被害の全体像を強調していましたが、現在は被爆者一人ひとりの物語や体験に焦点を当てる展示スタイルへと変わりました。
広島平和記念資料館のリニューアルでは「魂の叫び」と名付けられたコーナーが設けられ、被爆者個人の人生や家族の思いを伝える展示が充実しました。三輪車や弁当箱といった被爆した遺品とともに、その持ち主がどのような人でどのような最期を迎えたかという物語が添えられています。
長崎でも市民団体「長崎の証言の会」が「一人一人の顔が見えるような展示」を要望しており、物理的な破壊だけでなく、被爆者が経験した精神的・社会的苦痛も含めた多面的な展示への変更が期待されています。
このアプローチは現代の博物館理論とも合致しており、訪問者が感情的に共感しやすい物語を通じて理解を深めることを重視しています。グラフィックな「怖さ」は減少したかもしれませんが、個人の悲劇への共感を通じて、より深い心理的影響を与える展示となっています。
理由3:教育的価値とバランスの追求
三つ目の理由は、ショックを与えることよりも教育的価値を高める方向へ展示が進化していることです。現在の展示は、原爆に至る歴史的背景、核兵器の開発史、被爆後の人々の生活や平和運動など、より幅広い文脈で原爆を理解できるよう工夫されています。
広島平和記念資料館では展示順序も変更され、まず被爆前後の広島のパノラマ写真やCG映像による導入展示があり、すぐに「被害の実相」展示に触れるようになりました。限られた見学時間の中でも被爆の実相により多くの時間を割けるよう配慮されています。
長崎原爆資料館でも「被害と加害の両方について多角的な視点から考えられるよう客観的事実に基づいた展示」という方針が示されており、単に恐怖心を喚起するだけではない、より深い考察を促す展示が目指されています。
博物館展示の国際的傾向としても、単なるショック効果に頼らず、訪問者の批判的思考を促し、現代社会との関連性を示す方向へと変化しています。「怖くなった」のではなく、より洗練された教育的アプローチが採用されたと言えるでしょう。
原爆資料館の見所
なお、原爆資料館の見所は具体的にどこにあるのでしょうか?
その1:個人の遺品が語る物語
現在の原爆資料館で最も心に響く展示の一つが、被爆者の遺品とその物語です。広島平和記念資料館の「魂の叫び」コーナーでは、被爆者の遺品を通して、彼らの人生や被爆時の状況、残された家族の思いを伝えています。
特に印象的なのは日常的な品々です。たとえば、ある3歳の男児の三輪車は、全身に大怪我と火傷を負い「水、水…」と訴えながら亡くなった子が遊んでいたものです。父親は子どもと三輪車を庭に埋葬し、40年後に掘り起こした際、鉄兜の中に男児の頭の骨が残っていたという悲痛な物語が添えられています。
また黒焦げになった弁当箱は、建物疎開作業中に被爆した中学1年生が持っていたもので、母親が息子の遺体の下から見つけました。弁当の内容が米・麦・大豆の混ぜご飯とジャガイモの千切り油炒めだったという具体的な説明が、ろう人形よりも強く当時の状況を伝えています。
こうした展示の特徴は、被爆者を「被害者」という抽象的な集団ではなく、一人ひとりの生活と希望を持った個人として描き出している点です。統計的な被害数ではなく、個別の喪失の積み重ねとして原爆の悲劇を伝える手法は、訪問者の共感を引き出す上で非常に効果的です。
その2:被爆の実相を伝える写真と映像
原爆資料館のもう一つの重要な見所は、被爆直後の状況を捉えた貴重な写真と映像です。広島平和記念資料館の入口に展示されている「焼け跡に立つ少女」の写真は特に印象的です。原爆投下の3日後に撮影されたこの写真には、右手を負傷した当時10歳の少女が何かを訴えるような眼差しを向けています14。
長い間身元不明だったこの少女は、73年後の2018年に「藤井幸子さん」と判明しました。写真とともに彼女のその後の人生—結婚して2人の子どもを持ち、がんを患い42歳で亡くなったこと—も展示されており、被爆の影響が一生に渡ることを物語っています。
両資料館とも、被爆前後の街並みの変化を示すパノラマ写真や、原爆投下をCG再現した映像を展示しています。特に広島平和記念資料館の導入展示では、原爆投下前の活気ある街の様子と、投下後の焼け野原となった風景を対比させることで、一瞬にして失われた日常生活の価値を強調しています。
これらの写真や映像は、事実に基づいた記録であるからこそ、来館者の心に深く訴えかけます。創作されたろう人形に比べて、実際の被爆の記録は「本物性」という点でより強い説得力を持っているのです。
その3:核兵器の歴史と現状を考える展示
原爆資料館の三つ目の見所は、核兵器の開発史や現状、そして核兵器廃絶に向けた取り組みに関する展示です。これらは原爆被害を過去の悲劇で終わらせず、現代社会における核の問題として考える機会を提供します。
長崎原爆資料館の「核兵器のない世界」コーナーでは、戦争の歴史を年表で示し原爆投下に至った経緯を説明するとともに、現在も存在する核兵器の脅威について解説しています。
広島平和記念資料館でも、核兵器開発の歴史や原爆投下の背景について、客観的事実に基づいた説明がされています。この部分は感情に訴えかけるというより、事実関係を整理して理解を促す内容となっています。
特筆すべきは、これらの展示が単なる加害・被害の二項対立を超えて、核兵器という人類共通の課題として問題提起している点です。「なぜ原爆が投下されたのか」「核兵器はなぜ危険なのか」「核兵器のない世界はどうすれば実現できるのか」といった問いを投げかけ、訪問者自身に考える機会を提供しています。
まとめ:グロさと学びのバランスが難しい
原爆資料館の展示変化は単に「怖さ」を減らすためではなく、より効果的に原爆の記憶を継承し、核兵器廃絶につなげるための進化と言えます。かつてのろう人形展示は強いインパクトがある一方で、訪問者が恐怖から目を背けたり、ショックだけが残って本質的なメッセージが伝わらなかったりする問題がありました。
現在の展示は、個人の物語に焦点を当て、被爆者一人ひとりの人生や家族の思いを伝えることで、訪問者の共感を呼び起こし、より深い理解を促しています。これは「怖くなった」のではなく、より効果的な記憶継承の方法への変化です。
この変化に対しては様々な意見があります。「あの日の悲惨さが伝わる展示になった」という肯定的評価がある一方、「惨状が『この程度』と思われないよう、被爆者の声を取り入れ、展示を必要に応じて見直してほしい」という要望もあります。
博物館展示の専門家として注目すべきは、この変化が単なる「怖さの軽減」ではなく、被爆80年、90年と時間が経過し、直接体験を語れる被爆者がいなくなる時代に向けた準備という側面です。「長崎の証言の会」が指摘するように、今回の展示更新は「太平洋戦争体験者の考えを反映できる最後の機会になる可能性がある」という重要な意味を持っているのです。