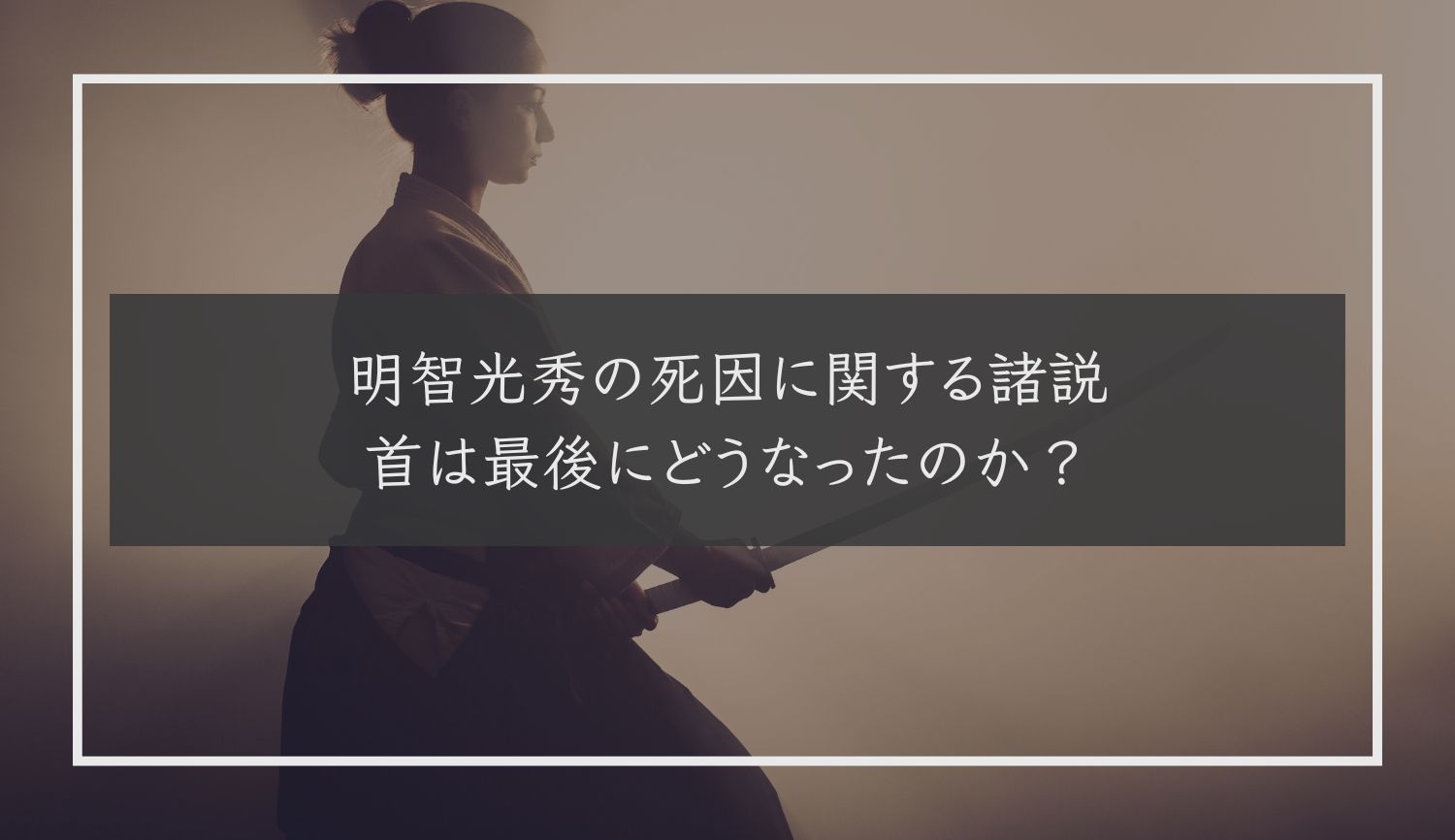本能寺の変で織田信長を討ち取り、歴史の転換点を作った明智光秀。しかし、その大胆な行動から11日後には自らも命を落とすことになります。山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れた光秀の死因と、その後の首の行方については諸説あり、完全な真相は今もなお謎に包まれています。
本記事では歴史資料を徹底検証し、明智光秀の最期と首の行方について、従来の視点とは異なる角度から考察します。戦国時代における「謀反人」の処遇という観点からも、光秀の死と首の運命を読み解いていきましょう。
明智光秀の経歴
明智光秀は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名として知られています。通説では美濃国の明智氏の支流の出身とされますが、出自については諸説あり、前歴についてははっきりしない部分も少なくありません1。
越前国の朝倉義景に仕え、長崎称念寺の門前に十年ほど暮らして医学の知識を身につけたとされています。その後、足利義昭に仕え、さらに織田信長に仕えるようになりました1。元亀2年(1571年)の比叡山焼き討ちへの貢献により坂本城の城主となり、天正元年(1573年)の一乗谷攻略や丹波攻略にも大きく貢献しました1。
政治家としての光秀は、人心掌握にも優れ、丹波地方では現在に至るまで光秀の善政を称える大祭が行われるほど、領民から慕われていました11。また、福知山城の城下町・亀山では、地形を活かした都市設計の才能も発揮していたとされています11。
そして天正10年(1582年)6月2日、京都の本能寺で織田信長を討ち、その息子・信忠も二条新御所で自刃に追い込む「本能寺の変」を起こしました1。しかし、わずか11日後の6月13日に羽柴秀吉との山崎の戦いに敗れ、その最期を迎えることになったのです210。
明智光秀の死因に関する諸説
明智光秀の死因については、主に以下の3つの説が存在します。それぞれの説の内容と信頼性について検証していきましょう。
その1:土民の竹槍による負傷と自刃説
最も広く知られ、多くの史料で支持されているのが、山崎の戦いに敗れた光秀が勝龍寺城から脱出し、少数の家臣とともに秀吉軍の包囲網をかいくぐって逃亡する途中で、京都府伏見区の小栗栖(おぐるす)まで出たところ、落ち武者狩りをしていた土民(地元の農民)に竹槍で襲撃され、致命傷となる深手を負ったというものです。
光秀はもうここまでだと悟り、家臣の溝尾庄兵衛(茂朝)に介錯を頼んで自刃したとされています23。この説は当時の文献にも記載があり、最も信頼性が高いとされる通説です。実際に小栗栖には「明智藪(あけちやぶ)」と呼ばれる場所があったとされますが、現在は宅地化されています2。
ここで注目すべき点は、光秀が自刃したとされる場所が、単なる逃亡ルート上の一地点ではなく、文化的な記憶として「明智藪」という地名で長く記憶されてきたことです。このような地名の残存は、その出来事の信憑性を支える重要な証拠となります。
その2:郷人一揆による討死説
別の説として、光秀は「醍醐の辺りで郷人一揆に討たれ、首が本能寺に届けられた」というものもあります。この説では、光秀は自刃ではなく、直接郷人(地元の人々)によって殺されたとされています。
しかし、この説は比較的新しく、古い文献には見られないため、信頼性はやや低いと考えられます。また、首が本能寺に届けられたという点も、他の史料と食い違いがあります。本能寺は既に焼失しており、首を届ける場所として機能していたかは疑問が残ります。
その3:生存説(天海僧正同一人物説)
最も興味深いのが、実は光秀は死んでおらず、その後「天海」という僧侶として生き延び、徳川家康のブレーンとなったという説です。この説を支持する根拠としては、以下のようなものがあります:
- 日光東照宮(天海が建立に関わった)に結梗紋(光秀の家紋)があること
- 日光に「明智平」という地名があること
- 光秀の部下が江戸幕府に関わりを持っていること
- 明智光秀と徳川家光が同じ漢字を使っていること
また、天海は前半生の記録があまり残されておらず、亡くなった年についても108歳説や132歳説など諸説あるという点も、この説を支持する材料とされています。
しかし、この説は歴史的証拠が十分でなく、結梗紋についても「ただ似ているだけではないか」という反論もあります。多くの歴史学者からは懐疑的に見られている説と言えるでしょう。
これら3つの説を比較検討すると、史料的根拠や伝承の古さから見て、第一の「土民の竹槍による負傷と自刃説」が最も信頼性が高いと考えられます。
明智光秀の首は最後にどうなったのか?
明智光秀の首の行方については、主に以下のような説があります。
その1 溝尾庄兵衛が持ち去った説
光秀を介錯した溝尾庄兵衛(茂朝)は、光秀の首を鞍覆いに包んで竹やぶに隠し、坂本城へ持ち帰ろうとしたという説があります。別の伝承によれば、庄兵衛は光秀の首を京都の妙心寺に納めようとしたものの、敵に囲まれたため山際に埋めたとも言われています。
ここで考えるべきは、なぜ溝尾庄兵衛が主君の首を妙心寺に納めようとしたのかという点です。戦国時代、武将の首は敵に渡れば晒し者にされる可能性が高く、家臣としては何としても守りたいものでした。庄兵衛の行動は、最後まで主君に忠義を尽くす家臣の姿を象徴していると言えるでしょう。
その2 秀吉に発見された説
京に凱旋した羽柴秀吉が三十三間堂で戦後処理(首実験)をした際、明智方の首の中に光秀の首があったため、秀吉は「首と胴体をつなぎ、金具でとめて粟田口で磔にせよ」と命令したという説があります3。また、別の伝承では、秀吉が三井寺で戦後処理をしていたときに、小栗栖の百姓が光秀の首を持参してきたとも言われています。
秀吉が光秀の首を識別できたという点は興味深いところです。当時、首を識別するのは容易ではなく、特に光秀のような著名な武将の場合、多くの偽物の首が持ち込まれた可能性もあります。この点については、後世の脚色が入っている可能性も否定できません。
その3 首塚に祀られた説
現在、京都市東山区の三条白川橋を南に下ったあたりには、明智光秀の首塚とされる場所があります。『京都坊目誌』によれば、隠されていた光秀の首は発見された後、胴体と繋ぎ合わせて粟田口刑場に晒され、その後、現在の蹴上辺り(西小物座町)に他の将兵の首とともに埋められたとされています。
時が経ち、明和8年(1771年)になって、光秀の子孫と称する能楽の笛の演者、明田利右衛門という人物が、その場所にあった石塔をもらい受けて自宅近くに祀りました。さらに明治維新後に現在の場所に移されたとのことです。
現在の首塚には、弘化2年(1845年)に造られた五重石塔、明治36年(1903年)に歌舞伎役者の市川団蔵が寄贈した墓、そして小祠があります。祠の中には光秀の木像と位牌が納められており、かつては衣服の切れ端や遺骨なども安置されていたそうです。
これらの説を総合すると、最も可能性が高いのは、溝尾庄兵衛が光秀の首を持ち去ったものの、途中で秀吉軍に発見され、最終的に首は粟田口刑場に晒された後、埋葬されたという流れでしょう。その後、江戸時代に入って子孫を名乗る人物によって祀られ、現在の首塚につながっているというシナリオが考えられます。
明智光秀が死なずに済んだ道はなかったのか?
ここで一つ考えたいのは、明智光秀が死を避ける可能性はあったのかという点です。本能寺の変後、光秀は「天下人」を名乗りましたが、わずか11日で敗北しました。なぜこれほど短期間で敗れたのでしょうか?
光秀が本能寺の変を起こした動機については、「怨恨説」「野望説」「黒幕説」「四国征伐回避説」など様々な説が唱えられています。特に近年注目されているのは「四国征伐回避説」で、信長による四国攻めを中止させるために光秀が謀反を起こしたのではないかとする説です。
しかし、動機が何であれ、光秀の計画には致命的な欠陥がありました。本能寺の変を成功させたものの、その後の同盟関係の構築や、他の織田家重臣たちの説得に失敗しています。特に毛利氏との講和交渉のために中国地方にいた羽柴秀吉が、驚異的なスピードで京に向かってきたことは、光秀の想定外だったでしょう。
山崎の戦いに敗れた後、光秀は勝龍寺城からの脱出を図りましたが、この逃亡計画も十分なものではありませんでした。「曇天で、星の明かりすらない暗い夜」に、「暗闇に紛れて坂本へ戻ろうと、光秀はひそかに脱出した」とされていますが2、敗戦の混乱の中で十分な警護も確保できなかったと考えられます。
では、光秀が生き延びる可能性はあったのでしょうか?
歴史的な視点から考えると、以下のような選択肢が考えられます:
- より確実な逃亡ルートの確保:坂本城ではなく、味方がいる地域や、海外への逃亡ルートを準備しておくべきでした。戦国時代には、敗北した武将が九州や朝鮮半島に逃れた例もあります。
- 本能寺の変前の同盟関係の構築:行動に移す前に、織田家の他の重臣や外部勢力との同盟関係を密かに構築しておくべきでした。特に毛利氏や徳川家康との事前交渉は不可欠だったでしょう。
- 信長を殺さない選択:信長を捕らえるにとどめ、政治的交渉材料とする選択肢もあったかもしれません。これにより、他の織田家臣団との全面対決を避けられた可能性があります。
しかし、これらはすべて「後の祭り」であり、実際の光秀には、山崎の戦いに敗れた時点で、生き延びる道はほとんど閉ざされていたと言えるでしょう。戦国時代、敗者に対する処遇は厳しく、特に主君を裏切った「謀反人」としての光秀に、生存の道はほぼなかったと考えられます。
まとめ:逃げ切るのは難しい
明智光秀の死因と首の行方について、様々な説を検討してきました。最も信頼性の高い説は、山崎の戦いに敗れた後、小栗栖で土民の竹槍により重傷を負い、家臣の溝尾庄兵衛の介錯により自刃したというものです。その首は一時的に隠されたものの、最終的には秀吉の手に渡り、粟田口刑場に晒された後、埋葬されたと考えられます。
光秀の首塚は現在も京都市東山区に残されており、江戸時代以降に整備されたものが今日まで伝わっています。この首塚を管理しているのは「餅寅」という和菓子屋で、店では桔梗の紋が入った「光秀饅頭」という銘菓も売られているそうです。歴史的悲劇の主人公が、今では観光資源として地域に貢献しているという歴史の皮肉と言えるかもしれません。
明智光秀の悲劇的な最期は、戦国時代における権力闘争の厳しさを物語っています。本能寺の変という大胆な行動に出たものの、その後の展開を十分に計算していなかった光秀の敗北は、いかに周到な準備が必要であったかを示しています。
また、光秀が生き延びたという「天海同一人物説」は、歴史的証拠に乏しいものの、人々の想像力を刺激し続けている魅力的な説です。歴史の真実がどうであれ、明智光秀という人物が日本の歴史と文化に与えた影響は計り知れないものがあります。
本能寺の変から440年以上が経った今も、明智光秀の死と首の行方についての謎は完全には解明されていません。これからも新たな史料の発見や研究によって、さらなる真相が明らかになる可能性があります。歴史の謎を解き明かす旅は、まだ続いていくのです。