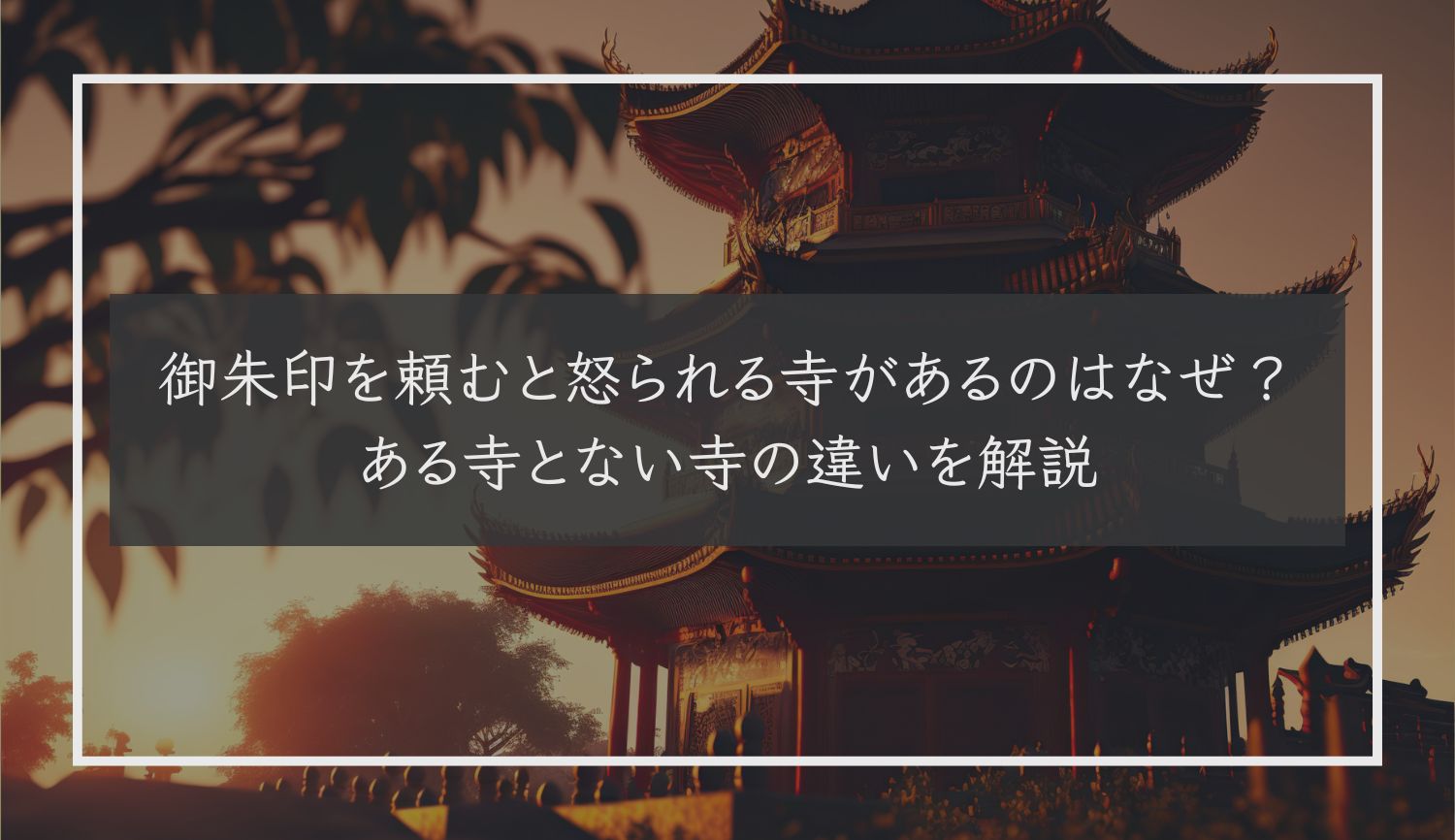近年、「御朱印集め」が日本国内外の旅行者の間で人気を博していますが、中には御朱印を頼んだ際に厳しく叱責されたという体験談も少なくありません。御朱印は単なる記念品ではなく、宗教的な意味を持つ神聖なものです。
本記事では、御朱印を頼んだ際に「怒られる」という現象の背景を探り、御朱印がある寺と無い寺の違いを独自の視点から解説します。また、万一怒られた場合の適切な対応についても具体的なアドバイスを提供します。御朱印巡りを心地よい体験とするための知識を身につけましょう。
御朱印を頼むと怒られる寺があるのはなぜ?
御朱印は元々、寺院に写経を納めた際に僧侶から授与される証でした。江戸時代頃から神社でも授与されるようになり、参拝の記念として一般化していきました。
しかし現代では、コレクションアイテムやSNS投稿の素材としての側面が強調され、その宗教的意義が薄れていることが、寺院側の不快感につながっています。
実際に東北地方の古刹を訪れた際、住職から「御朱印は参拝の証であって、スタンプラリーではない」と諭されたことがあります。参拝せずに御朱印だけを求める観光客が増えていることへの警鐘でした。
近年の「御朱印ガール」「御朱印男子」といった言葉に代表される御朱印ブームは、一部の寺院に大きな負担をもたらしています。特に人気の寺院では、御朱印を求める参拝者の長蛇の列に対応するために、本来の宗教活動に支障をきたしているケースもあるのです。
ある関西の有名寺院では、御朱印の授与時間を制限し、一日の授与数に上限を設けているところもあります。これは単に対応能力の問題だけでなく、御朱印の神聖性を保つための措置でもあるのです。
怒られる理由として最も多いのが、1冊の御朱印帳に神社とお寺の御朱印が混在していることです。「神社とお寺は別物」という考え方は、特に由緒ある寺院では強く持たれています。「先頭(ページ)が寺で、(2ページ目が)神社で怒られた」という事例は少なくありません。
一般的には混在しても問題ないとされていますが、厳格な寺院では忌避されることがあるため、初心者は神社用とお寺用の御朱印帳を分けて持つことをお勧めします。
法隆寺で5つの御朱印を一度に依頼して叱られた体験談が記載されています。投稿者は「あのねぇ、御朱印は一個!そんなに何個も貰うもんじゃないよ!」と粗野な口調で注意されたと報告しています。

これは特定の寺院のルールであり、すべての寺でそうではありませんが、特に由緒ある寺院では御朱印の数に制限を設けているところがあります。これは商業化を避け、御朱印の意義を保つための措置と考えられます。
御朱印がある寺とない寺の違い
御朱印の授与については、宗派によって方針が異なることがあります。天台宗や真言宗など古い歴史を持つ伝統的な宗派では御朱印文化が定着していますが、一部の宗派や新興の宗教団体では御朱印を授与していない場合もあります。
例えば、浄土真宗の一部寺院では「納経」という概念が薄いため、御朱印よりも「参拝印」という形で授与することがあります。また禅宗の厳格な寺院では、観光目的の御朱印授与を制限していることもあります。これは各宗派の教義や歴史的背景に根差したものであり、宗教的多様性の表れと言えるでしょう。
大規模な観光寺院と地域に根差した小さな寺院では、御朱印に対する姿勢が大きく異なります。観光客の多い有名寺院では、御朱印の授与体制が整備されていることが多いですが、小規模な寺院では人員不足から特定の時間や日にちに限定して授与していることもあります。
また、寺院の運営方針によっても違いがあります。積極的に参拝者を受け入れる開放的な寺院もあれば、修行や信仰の場としての静謐さを重視する寺院もあります。後者の場合、御朱印の授与を限定的にしている傾向があります。
世界遺産に登録されているような寺院では、文化財保護の観点から参拝者数を制限し、それに伴って御朱印の授与にも制約を設けているケースがあります。例えば高野山の一部の寺院では、貴重な建造物の保存のため、御朱印の授与時間や場所を厳しく制限しています。
一方で、地域振興や文化伝承の一環として積極的に御朱印を授与し、独自のデザインや特別御朱印を提供することで参拝者を誘致している寺院もあります。京都・東京などの観光地では、季節限定の御朱印や芸術性の高い御朱印を提供する寺院が増えています。
御朱印の授与方法の多様性
御朱印の授与方法も寺院によって様々です。直書き(御朱印帳に直接書く)を基本とする寺院、書き置き(あらかじめ紙に書いておいたものを渡す)のみの寺院、両方に対応する寺院など多様性があります。コロナ禍以降は、感染防止の観点から書き置き対応を増やした寺院も多くなりました。
「コロナから書き置き多くなったよね。やっぱり直書きの方が嬉しいよね」という声もありますが1、書き置きにも良さがあり、「書き置きを受け入れると、多くの神社仏閣とご縁を結んだ証がさらに増え」るという見方もあります。どちらが良いというわけではなく、各寺院の状況や方針に合わせた多様性として理解すべきでしょう。
まとめ:すべての寺と神社にあるわけではない
御朱印は日本の宗教文化の一部であり、その授与には各寺社の歴史や伝統、宗派の違いが反映されています。すべての寺院や神社で御朱印が授与されているわけではなく、また授与されていても、その方法やルールは場所によって大きく異なります。
怒られる主な原因は、御朱印の宗教的意義の理解不足、神社とお寺の御朱印帳の混在、一度に多くの御朱印を求めること、参拝せずに御朱印だけを求めることなどです。これらの点に注意し、各寺院のルールを尊重することで、心地よい御朱印巡りが可能になります。
御朱印集めは単なる趣味や観光の一環ではなく、日本の伝統文化や精神性に触れる貴重な機会です。「怒られた」という経験も、日本文化への理解を深める契機として前向きに捉え、より豊かな御朱印巡りを楽しみましょう。
参拝を第一に考え、御朱印はその記念として謙虚にいただくという姿勢こそが、本来の御朱印の在り方です。そして何より、寺院や神社が信仰の場であることを常に意識し、敬意を持って訪れることが、心地よい御朱印体験への鍵となります。