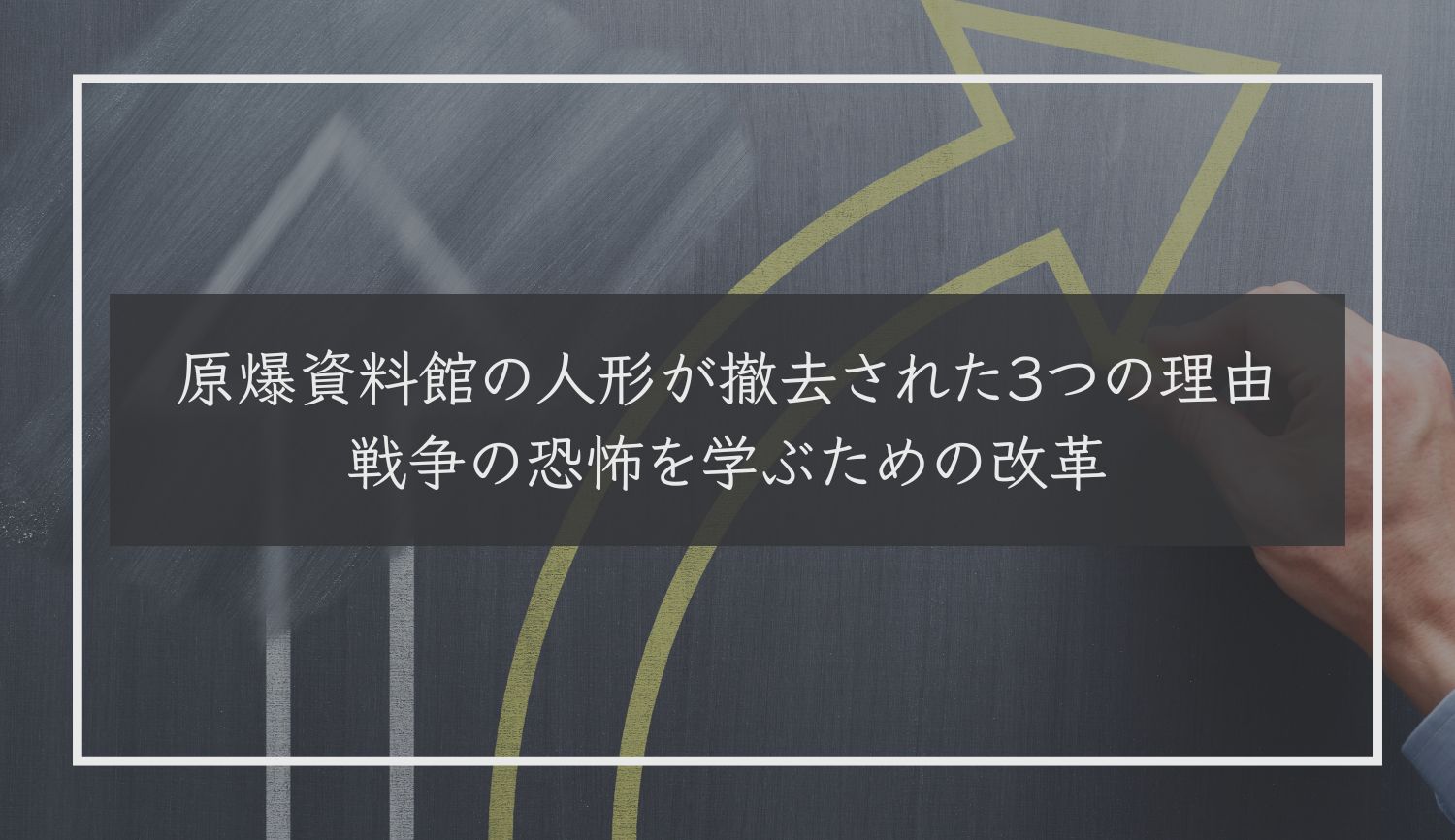広島平和記念資料館(通称:原爆資料館)に長年展示されていた被爆再現人形が2017年に撤去されました。この人形は、原爆投下後の広島で被爆者が焼けただれた皮膚でがれきの中をさまよう姿を再現したもので、多くの来館者に強烈な印象を与えてきました。

しかし、広島市による資料館の全面リニューアルに伴い、この象徴的な展示物が姿を消したことで、「戦争の悲惨さをどう伝えるべきか」という根本的な問いが改めて投げかけられることになりました。本記事では、被爆再現人形が撤去された3つの主な理由を解説するとともに、戦争の記憶をどのように後世に伝えていくべきかという普遍的な課題について考察します。
原爆資料館の人形が撤去された3つの理由
さて、原爆資料館の人形が撤去されたのは、どうしてなのでしょうか?
ここでは、3つの視点から理由を考察していきます。
理由1 実物資料への転換
原爆資料館から被爆再現人形が撤去された第一の理由は、展示方針が「再現」から「実物」へと転換されたことにあります。広島市は2010年、資料館の大規模改修に合わせて展示内容の見直しを行い、実物資料を重視する方針を決定しました。この決定の背景には、被爆者の遺品や写真などの「実物」が持つ真実性と説得力を重視する考え方がありました。
広島平和文化センターによれば、実物資料には被爆者一人ひとりの人生や家族の思いが込められており、来館者に強い印象を与えることができるとされています。実際に、広島平和記念資料館では現在、焼け焦げたシャツや変形した自転車、弁当箱など約2万点の被爆資料から厳選された約200点を効果的に配置する「集合展示」の手法を採用しています。

資料館の学芸員である玉川萌氏は「遺品に皆さん向かい合って頂いて、何か一つでもご自身にひきつけて自分事として考えて頂くきっかけになればいいな」と述べており、実物資料を通じて被爆の実相をより深く理解してもらうことを目指しています。
このように、原爆資料館は「作られたもの」よりも「実際に被爆した物」を展示することで、より事実に基づいた展示を追求する方向へと舵を切ったのです。
理由2 被爆者からの批判
人形撤去の二つ目の理由は、被爆者自身から「人形では実際の被害の様子を正確に伝えられない」という批判の声が上がっていたことです。2013年3月19日に開かれた第14回広島平和記念資料館展示検討会議では、爆心地からわずか1.2kmの場所で被爆し、全身大火傷を負った被爆者の坪井氏が「被爆の実相はこんなもんじゃない、ジオラマはおもちゃである」と発言したことが、人形撤去の決め手になったと報告されています。
実際に被爆を体験した人々にとって、どんなに精巧に作られた人形であっても、原爆による被害の実態を完全に再現することは不可能だったのです。「実際はもっとひどかった」という証言は、人形展示の限界を示すものでした。

また、朝日新聞デジタルの2019年5月16日付の記事によると、被爆者からは「被害はこんなものじゃなかった」という批判が寄せられていたことが報告されています。被爆者の体験に基づく証言は、展示の在り方を検討する上で重要な判断材料となりました。

来館者への配慮
三つ目の理由は、特に子どもを含む来館者への心理的影響を考慮した結果です。被爆再現人形、特に初代の蝋人形は非常に生々しい表現がなされており、来館者に与える心理的衝撃が大きいという懸念がありました。
初代の蝋人形(1973年から1991年まで展示)は、「蝋人形の女性の髪は、焼けて逆立ち、ブラウスとモンペは半分近くが焼けてなくなり、乳房と両手の皮膚がむけて垂れ下がり、すすけてうつろな表情を浮かべている」と描写されており、非常に衝撃的な姿をしていました。
この人形は1991年に二代目のプラスチック製人形に置き換えられましたが、その際に表現の「抑制」が見られたことが報告されています。この変化は、資料館が来館者、特に子どもたちへの心理的影響を考慮して表現を和らげた可能性を示唆しています。
こうした経緯から、最終的に人形展示そのものを廃止することで、事実に基づいた展示を行いながらも、来館者への過度な心理的負担を避けるバランスを取ろうとした面があると考えられます。
人形撤去をめぐる賛否と議論
これまで見てきた3つの理由から、広島市が被爆再現人形を撤去する決断に至った背景がわかりました。しかし、この決定は市民や来館者の間で大きな議論を引き起こしました。ここからは、その賛否両論の声を詳しく見ていきましょう。
撤去反対派の主張
人形の撤去決定に対しては、多くの市民から反対の声が上がりました。
具体的には、安佐南区の派遣社員藤川明秀さん(73)は「核兵器被害の悲惨さが一目で伝わる。残してほしい」と述べ、佐伯区の会社員勝部晶博さん(46)は「人形が与える強いインパクトが間違いだとは思わない」と主張しました。また、東京都世田谷区の会社員西尾完太さん(29)は「実物重視と言うなら科学的に検証し、より実態に近い人形を作り直してはどうか」と提案するなど、撤去に反対する声が各地から寄せられました。
これらの反対意見の根底には、「原爆の恐ろしさを視覚的に強く印象づける展示が必要」という考え方があります。特に戦争を知らない若い世代に対して、原爆の悲惨さを実感させるためには、人形のような強いインパクトを持つ展示が効果的だという主張です。
撤去賛成派の主張
一方で、人形撤去を支持する意見も少なくありませんでした。その中心にいたのは、実際に被爆を体験した方々や展示の専門家たちでした。
先述の坪井氏のように、被爆体験者からは「被爆の実相はこんなもんじゃない」という指摘があり、人形という「模型」や「ジオラマ」では原爆の実態を正確に伝えることができないという批判がありました。実物資料こそが被爆の事実を最も正確に伝えることができるという考え方です。
広島平和記念資料館の展示方針を検討した専門家からも、「実物の資料を重視する」という方針が支持されました。実物資料には一人ひとりの被爆者の人生や家族の思いが込められており、それらを通じて被爆の実相を伝えることが重要だという考え方です。
広島市は公式見解として「凄惨な被爆の惨状を伝える資料については基本的にありのままで見ていただくべきという方針の下、この度被爆再現人形を撤去することとしたものであり、見た目が恐ろしい、怖いなどの残虐な印象を与えることなどを懸念して撤去するものではありません」と説明し、実物資料を重視する方針を強調しています。
このように、「事実」と「再現」のどちらがより効果的に原爆の悲惨さを伝えることができるのかという点で意見が分かれたのが、この人形撤去論争の本質でした。
戦争教育と展示手法の課題
人形撤去をめぐる議論は、単に一つの展示物をどうするかという問題にとどまらず、「戦争の記憶をどう伝えるか」という普遍的な課題を浮き彫りにしました。ここでは、実物資料と再現展示それぞれの役割や、国際的な展示手法との比較を通じて、この問題の本質に迫ります。
実物資料と「作り物」の役割
戦争や原爆のような歴史的悲劇を後世に伝える際、実物資料と再現展示(いわゆる「作り物」)にはそれぞれ異なる役割と効果があります。
実物資料には圧倒的な真実性があります。焼け焦げた衣服や変形した日用品は、原爆の熱線や爆風の威力を直接的に証明するものであり、そこには議論の余地がありません。また、実物資料は一人ひとりの被爆者の実在を示すものであり、個人の物語と結びついた「証拠」として強い説得力を持ちます。
一方、人形のような再現展示には、視覚的なインパクトと分かりやすさがあります。現代アートの美術作家で広島市立大芸術学部講師の菅亮平さん(41)は「フィクションにはリアルなイメージを想起させ、人の心を動かす力がある一方で、事実をねじ曲げて伝えるリスクもある」と指摘しており、再現展示の両面性を適切に捉えています。
実際、原爆資料館を訪れた多くの人々が「人形のインパクトは非常に大きく、今でも記憶に残っている」と振り返るように、視覚的なインパクトは記憶に残りやすいという特徴があります。特に子どもや若い世代に対して、原爆の悲惨さを印象づけるためには効果的な手法でした。
国際的な展示手法との比較
世界各地の戦争・平和博物館では、様々な展示手法が採用されています。それらとの比較を通じて、広島平和記念資料館の展示方針の特徴と課題を考察してみましょう。
アメリカの「9.11メモリアルミュージアム」では、テロの凄惨さを伝える実物資料の展示が目立つ一方で、ストーリー性のある展示や犠牲者の追悼を目的としたアートも印象的な形で展示されています。実物資料とストーリーテリング、アートを組み合わせることで、事実を伝えながらも来館者の想像力を刺激し、感情に訴えかける展示となっています。
ポーランドのアウシュビッツ強制収容所記念館では、犠牲者の遺品(靴、眼鏡、カバンなど)の膨大なコレクションが展示されており、その量自体がホロコーストの規模を物語っています。また、ガス室や焼却炉といった施設がそのまま保存されており、「現場」としての強烈な訴求力を持っています。
こうした国外の事例と比較すると、広島平和記念資料館の現在の展示方針は「実物資料」を最重視する立場にあり、再現展示やアート的要素は限定的になっています。この方針は「事実に基づく展示」としての信頼性を高める一方で、来館者の想像力を刺激し感情に訴えかける面では課題があるかもしれません。
おわりに:継承と改革の未来
被爆再現人形の撤去は、単なる展示物の変更ではなく、「原爆の記憶をどう継承するか」という根本的な問いを私たちに投げかけています。この問題は、広島だけでなく戦争の記憶を継承しようとする世界中の社会が直面している普遍的な課題でもあります。
人形撤去から数年が経った今、改めて考えるべきなのは「何を伝えるか」と同時に「どう伝えるか」という方法論です。実物資料には圧倒的な真実性がある一方で、再現展示には視覚的インパクトと分かりやすさがあります。両者はそれぞれ異なる役割を持ち、相互に補完し合う関係にあると言えるでしょう。
現在、原爆資料館では実物資料を中心としながらも、デジタル技術を活用したCGパノラマや触れる模型なども取り入れられています。また、被爆者の証言をデジタルアーカイブ化する取り組みも進められており、被爆体験を持つ人々が少なくなる中で、その「声」を保存する努力が続けられています。
私たちは今一度、被爆再現人形が投げかけた問いに向き合い、戦争の恐怖と平和の尊さを学ぶために、どのような展示が効果的なのかを考え続けなければなりません。それこそが、被爆から80年近くを経た今も、広島の原爆資料館が私たちに求めている課題なのではないでしょうか。