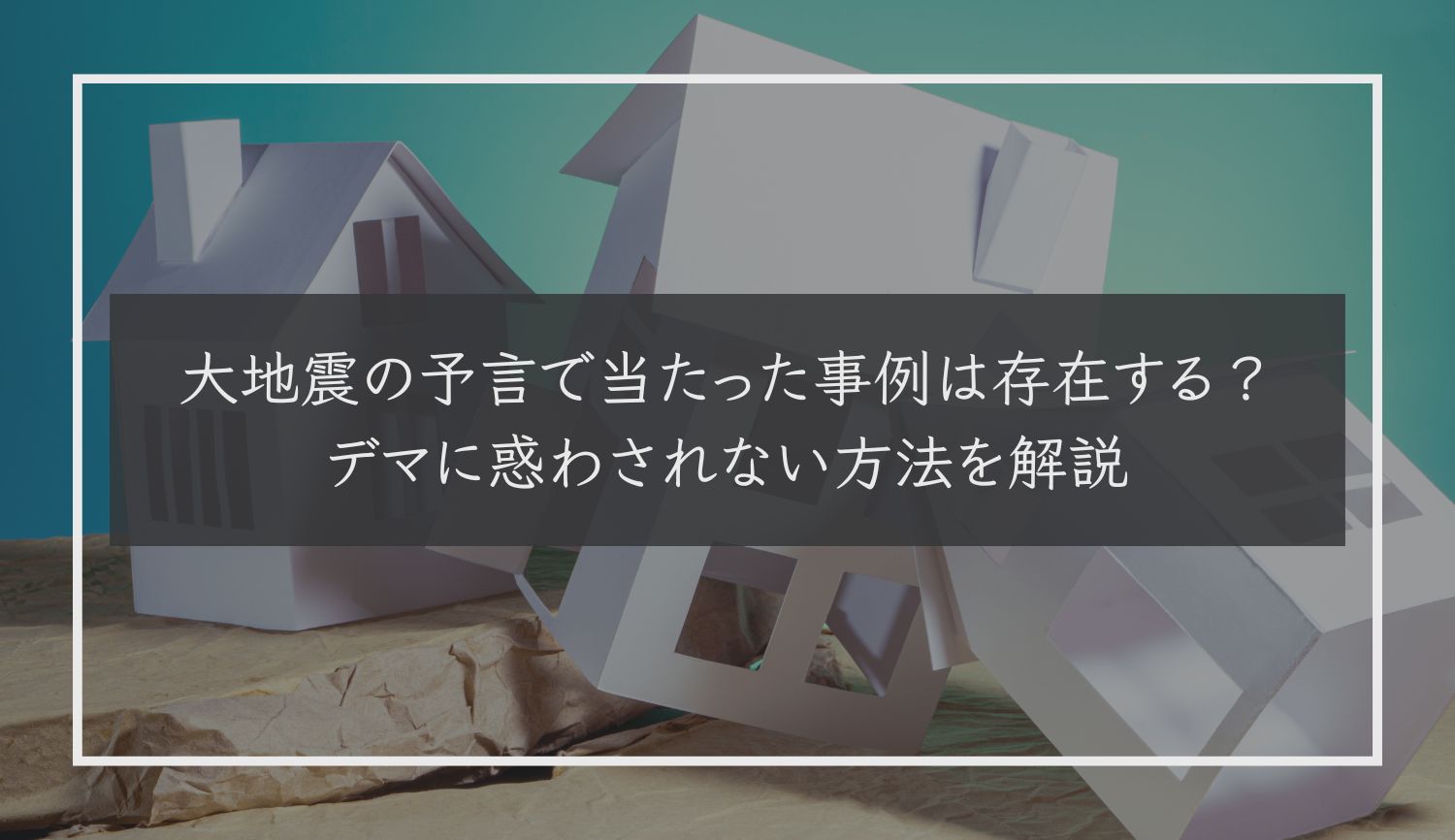近年、大地震が発生するたびにSNSやインターネット上で「実は予言されていた」という話や、次の大地震を予言する情報が拡散される現象が目立ちます。
特に、災害時には不安から、根拠の薄い情報でも信じてしまう傾向があります。こうした情報の中には科学的根拠がない「デマ」も多く含まれており、正確な情報を見極めることが重要です。
本記事では、過去の地震予言の的中事例を検証し、なぜ地震予言が広まるのか、そして災害時のデマに惑わされないための具体的な方法を解説します。
大地震の予言で当たった事例は存在する?
地震予知とは、気象庁の定義によれば「地震の起こる時、場所、大きさの三つの要素を精度よく限定して予測すること」です。この厳密な意味での予知が科学的に成功した事例は、残念ながら現在までのところ確認されていません。
気象庁は公式見解として、「現在の科学的知見では、場所や日時を絞って地震の発生を予測することは極めて難しい」と明言しています。さらに「日時と場所を特定した地震を予知する情報はデマと考えられます」とも述べており、こうした情報に惑わされないよう注意を呼びかけています。
日本の地震予知研究は1962年に「地震予知―現状とその推進計画」が発表されたことに始まります。当初は「10年後には十分な信頼性をもって答えることができるであろう」と期待されましたが、研究が進むほど予知の難しさが明らかになってきました。特、に1995年の阪神大震災は地震予知研究の転機となりました。それまで国の地震予知計画を推進していた地震予知連絡会は、阪神大震災を最後に地震活動の見通しなどの見解を公表することを中止し、単なる議論や意見交換を行う場へと変化したのです。
一方で、非科学的な手法も含めて「的中した」と言われる地震予言の事例はいくつか存在します:
- 東日本大震災に関する予言:一部のマンガや書籍で東日本大震災を思わせる描写があったことが、後になって「予言が当たった」と話題になりました。しかし、こうした事例は偶然の一致か、あるいは後付けで解釈されたものであり、科学的な予知とは言えません。
- 企業による地震予測サービス:例えば、株式会社地震科学探査機構(JESEA)は「MEGA地震予測」というサービスを提供し、2022年3月16日の福島県沖地震(震度6強)などを予測したと主張しています。同社は「ピンポイント予測」という手法で「いつ」・「どこで」・「どのくらいの規模」の地震が起きるかを約1か月以内で予測すると述べています。しかし、こうした民間の予測サービスについても、科学的な検証は十分になされていません。
- 『私が見た未来 完全版』に記載された予言:この本には「本当の大災難は2025年7月にやってくる」という予言が記載されており1、著者は過去の予言が東日本大震災の発生時期に近かったことから注目を集めています。ただし、これは夢に基づく予言であり、科学的根拠はありません。
地震予知研究の現状
実は、日本政府も長年にわたり地震予知研究に力を入れてきました。気象研究所は「地震発生過程の詳細なモデリングによる東海地震発生の推定精度向上に関する研究」などの特別研究を実施し、東海地震の予知精度向上を目指してきました。
しかし、2017年には「2~3日以内に東海地震が発生するという確度の高い予測は、現在の科学的知見では困難」と方針を転換しました。南海トラフ地震に関しても、予知ではなく、統計に基づく発生確率による警戒・注意喚起の方式に改められました。
関西大学社会安全学部の林能成教授は、地震学者を対象に南海トラフ地震の事前予測に関するアンケート調査を実施しました。その結果、地震予知を出せる確率の平均値は5.8%、中央値は1.2%と極めて低い数値となり、予知の的中率も平均で19.7%と低い結果でした。つまり、「100回地震予知を試みても、予知情報を出せるのは5、6回程度で、そのうち、予知が当たるのは1回程度しかなく、予知情報を出してもおおむね地震が起こらない」と地震学者の多くが考えているのです。
どうして地震を予言する人がいるのか?
科学的な地震予知が困難であるにもかかわらず、なぜ地震予言が後を絶たないのでしょうか?
その背景には複数の要因があります。
その1 商業的な利益
一部の予言者や企業は、地震予知サービスを商業的に利用しています。すなわち、有料で地震予測情報を配信するビジネスモデルも存在します。こうしたサービスには一定の需要があるため、科学的根拠が不十分でも提供され続けるわけです。
その2 非科学的な前兆現象への信仰
「地震雲」や動植物の異常行動など、科学的根拠が不十分な「前兆現象」を信じる風潮も根強く存在します。気象庁は「地震雲」について「科学的に説明できない」としており、動物や植物の予知能力についても「科学的な根拠に欠ける」との立場を示しています。しかし、こうした現象を地震の前兆と結びつける傾向は後を絶ちません。
大地震のデマに惑わされない方法
災害時には様々な情報が飛び交い、その中にはデマや根拠のない予言も含まれます。こうした情報に惑わされないためには、具体的な方法があります。以下では、災害時の情報を正しく判断するための3つの重要な方法を紹介します。これから紹介する方法は、専門家が推奨する情報検証の基本ステップです。一つ一つの方法を意識することで、災害時でも冷静な判断ができるようになります。
方法1:公式の情報源を確認する
災害時に最も信頼できる情報源は、公的機関が発表する公式情報です。具体的には以下のような情報源を優先的に確認しましょう:
- 国や自治体の公式発表:気象庁や内閣府防災などの国の機関、および地方自治体が発信する情報は最も信頼性が高いです。気象庁のウェブサイトでは地震情報だけでなく、地震予知に関する正確な見解も公開されています。
- 公式アカウント:Twitter(X)などのSNSでも、国や自治体、電力・ガス・鉄道などのインフラ企業の公式アカウントは信頼できる情報源です。例えば、2018年の大阪北部地震の際には、大阪市の吉村洋文市長(当時)のTwitterによる情報発信が市民の不安軽減に貢献しました。
- 報道機関のニュース:テレビ、ラジオ、新聞、通信社などの報道機関は、情報を発信する前に事実確認を行っていることが多いため、一般的なSNS投稿よりも信頼性が高いです。
「伝聞」情報(「〇〇らしい」「〇〇だそうだ」といった形式)はすぐに鵜呑みにせず、上記の公式情報源で確認することが重要です。特に災害時には、最初の情報源が削除された後も伝聞として拡散し続けるケースが多いため注意が必要です。
方法2:科学的根拠を確認する
地震予言やその他の災害情報を評価する際は、科学的根拠の有無を確認することが重要です:
- 地震予知の限界を理解する:現代の科学では、地震の発生時期・場所・規模を高い精度で予測することは極めて困難です。「〇月〇日に〇〇で大地震が起きる」といった具体的な予言は、科学的根拠に欠けている可能性が高いと考えるべきです。
- 「前兆現象」の科学的評価を知る:「地震雲」や動植物の異常行動などの前兆現象については、科学的根拠が不十分であることを理解しておきましょう。こうした現象が地震と偶然同時期に観察されることはありますが、因果関係は証明されていません。
- 統計的な発生確率との区別:気象庁などが発表する「南海トラフ地震の30年以内の発生確率は70〜80%」といった情報は、過去のデータに基づく統計的な予測であり、具体的な発生時期を予言するものではありません。このような科学的な確率予測と、具体的な日時を指定する予言とは明確に区別する必要があります。
関西大学社会安全学部の林能成教授は「地震予知はとても難しいから、地震は突然来るものだと思って備えましょう」という姿勢を推奨しています。科学的に確立された予知方法がない現状では、いつ地震が来ても対応できるよう日頃から備えることが最も重要です。
方法3:画像や情報の出所を検証する
災害時にSNSで拡散される情報の中には、古い災害の画像を流用したものや、誤解・勘違いに基づくものも少なくありません。情報の信頼性を判断するために以下の検証方法を活用しましょう:
- 画像検索の活用:災害の写真が添付された情報を見かけた場合、Googleなどの画像検索機能を使って、その画像が過去の災害から流用されたものでないか確認できます。これは「創作系のデマ」を見分けるための有効な手段です。
- 複数情報源での確認:重要な情報は、複数の信頼できる情報源で確認することが望ましいです。一つの情報源だけでなく、複数の公的機関や報道機関の発表を照らし合わせて判断しましょう。
- 投稿の種類を見極める:災害時のデマには「創作系」と「誤解・勘違い系」の2種類があります4。例えば2018年の大阪北部地震では「シマウマが脱走した」という完全な作り話と、「京セラドームの屋根に亀裂が入った」という誤解(実際は外階段とその汚れが亀裂に見えただけ)が拡散しました。特に後者は写真付きで拡散されることが多いため、慎重に判断する必要があります。
- 消防の出動情報の確認:地域によっては、消防が管轄内での消防車や救急車の出動情報をWebや自動応答の電話で公開していることがあります。地域の災害情報を確認する際には、こうした公的な出動情報も参考になります。
まとめ:日常的に防災意識を高めよう
地震大国である日本において、大地震はいつどこで発生してもおかしくありません。現代の科学では具体的な地震の発生時期や場所を高い精度で予測することは困難であり、「〇月〇日に〇〇で大地震が起きる」といった予言は科学的根拠に乏しいと考えるべきです。
最も重要なのは、「予知情報が出されることなく、地震が突然発生しても被害が最小限となるように、日頃から地震対策を推進すること」です。家具の固定や非常食の備蓄、避難経路の確認など、日常的な防災対策を着実に進めることが、結果的には最も効果的な地震対策となるでしょう。
私たちに今できることは、デマに惑わされず、科学的知見に基づいた冷静な判断をし、日常的に防災意識を高めていくことなのです。
参考文献
- 文藝春秋「『本当の大災難は2025年7月にやってくる』東日本大震災の予言が的中した漫画家の新たな警告」(https://bunshun.jp/articles/-/58981?page=2)
- 読売新聞「気象庁『予知はデマ』明言、地震雲の発生や動植物の予知能力は『科学的な根拠に欠ける』」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20240812-OYT1T50051/)
- 気象庁「気象研究所における地震予知研究について」(https://www.jma.go.jp/jma/press/0402/19a/kenkyu040219.pdf)
- Yahoo!ニュース「災害時に広まるSNS発の『デマ』『フェイクニュース』その判別法」(https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/bf462a795217081ccec92545b90d6da5e3d423b7)
- 関西大学「南海トラフ地震の予知可能性と防災」(https://www.kansai-u.ac.jp/reed_rfl/archive/58_2.php)
- 気象庁「地震予知について」(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/faq/faq24.html)
- 読売新聞「予知からの転換 地震防災は阪神大震災から始まった」(https://www.bosai.yomiuri.co.jp/feature/1443)