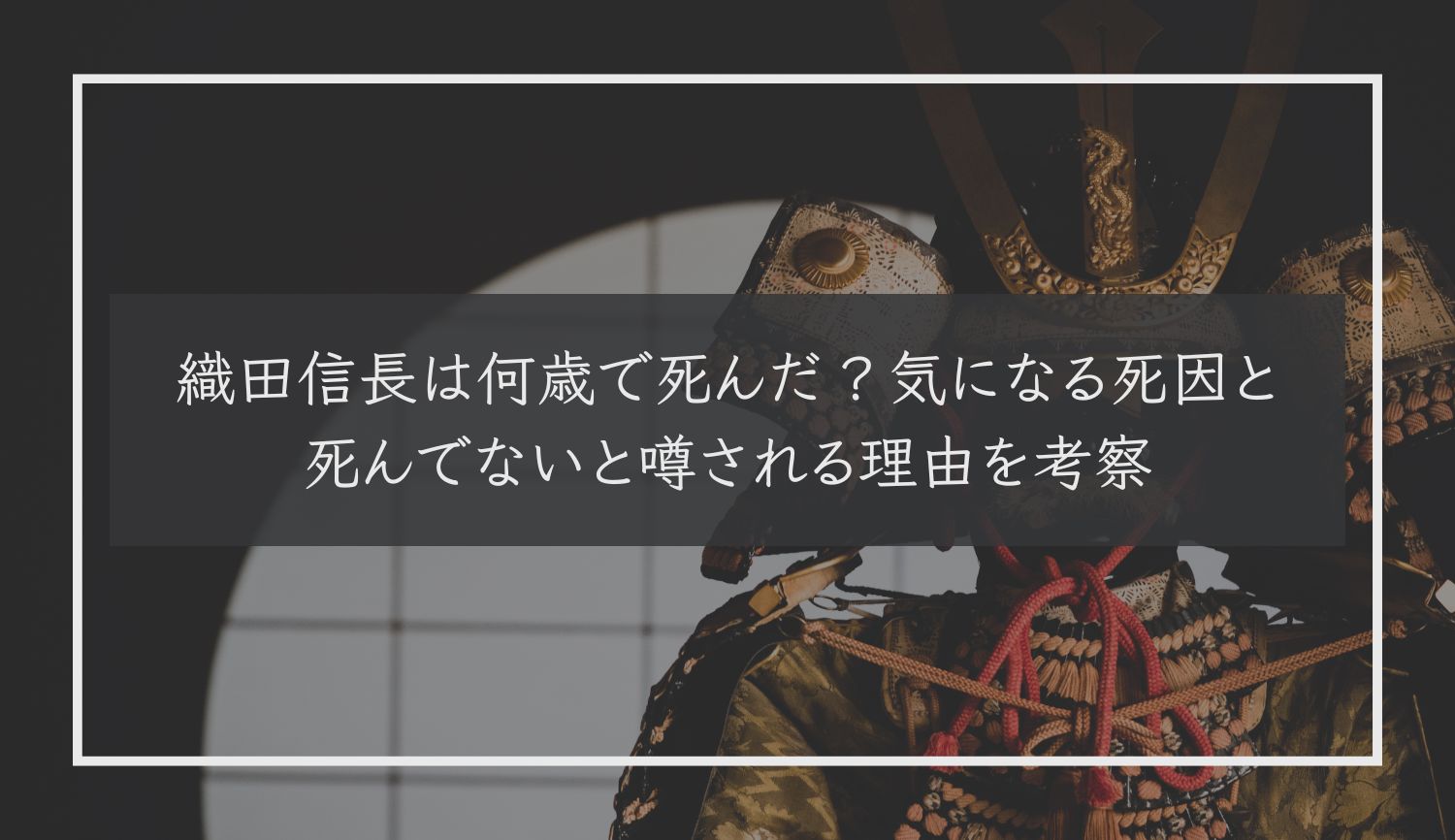織田信長と言えば、「本能寺の変」で生涯を終えたことから「天下統一」まであと一歩届かなかった人物として知られています。本記事では、織田信長が何歳で亡くなったのか、その死因や最期の言葉、さらには「死んでいない」という噂の真相まで、歴史資料に基づいて詳しく解説します。織田信長の生涯の最期に迫る謎と史実を紐解いていきましょう。
織田信長は何歳で死んだのか?
織田信長は、天正10年(1582年)6月2日(西暦では6月21日)に本能寺の変で亡くなりました。生まれは天文3年(1534年)であり、満年齢では48歳、当時の数え方である数え年では49歳でした。
豊臣秀吉が62歳、徳川家康が75歳まで生きたことを考慮すると、信長は比較的若くして生涯を終えたと言えます。しかし、戦国時代を生きた男性の平均寿命は37〜38歳程度だったとされており、時代背景を考えれば、信長は平均以上の長さを生きたことになります。
信長と同時代の著名な武将との年齢差を見てみると:
- 武田信玄:信長より13歳年上
- 上杉謙信:信長より4歳年上
- 豊臣秀吉:信長より3歳年下
- 徳川家康:信長より9歳年下
このように、信長は戦国の「中堅世代」として、先輩武将と後輩武将の両方と関わりながら天下統一を目指していました。
織田信長の死因とその最期
織田信長の死因については、主に二つの説があります。
その1 切腹説
信長が自ら刀を手にし、お腹を切った(切腹)という説です。この説の根拠となっているのは、信長の家臣・太田牛一が書いた『信長公記』にあります。そこには「信長は奥の部屋に入り、扉を閉めて切腹した」と記されています1。
天正10年(1582年)6月2日未明、明智光秀は予定していた中国方面への出陣を変更し、織田信長がいる本能寺を襲撃しました。信長はわずかな手勢しかおらず、明らかに不意を突かれた状態でした。
本能寺では信長の手勢が応戦しましたが、明らかな兵力不足で、短時間で敗勢に追い込まれました。信長自身も弓を取って戦い、弓の弦が切れると今度は槍を手にして応戦しましたが、敵兵に槍で肘に傷を負わされました。
やがて御殿に火が回ると、信長は女中たちに逃げるよう命じ、自らは殿中に入り、納戸を閉じて自害して果てたとされています。
その2 焼死説
本能寺が火に包まれたため、火傷や一酸化炭素中毒で亡くなったという説もあります。本能寺は木造建築で燃えやすい構造だったため、短時間で炎が広がり、信長は逃げられなかったのではないかとも考えられています1。
いずれにせよ、同時代の公家日記などの史料では一斉に信長の死が伝えられており、本能寺で亡くなったことは史実として確かだと考えられています。
明智光秀が織田信長を裏切った理由
本能寺の変で信長を襲った明智光秀の動機については、現在でも明確な定説はなく、様々な説が存在します。
信長からの侮辱説(パワハラ説)
信長は部下に厳しい性格だったと言われており、光秀も何度か信長から厳しく叱責されたことがあります。公衆の面前で暴力を振るわれるなど武士の面目を傷つけられ、「もう我慢できない!」と思ったのではないかという説です。
野望説
光秀は信長の次に天下を取る野望を持っていたという考え方です。当時、信長の勢力は圧倒的で、もし彼を倒せば次のリーダーになれるかもしれません。光秀はそのチャンスを狙ったとも言われています1。また、豊臣秀吉の出世が早いことに焦りを感じていたという見方もあります。
黒幕説
光秀が単独で決断したのではなく、誰かの命令を受けていたのではないかという説もあります。例えば、朝廷や別の有力大名が「信長を倒すべきだ」と考え、光秀に実行させたのではないかという意見もあります。
領地に関する不満説
信長が光秀から領地を取り上げたことへの不満があったという説もあります。信長に対する不信感と日常的な疲労感で光秀が限界に達していた可能性も考えられます。
どの説が真実なのかは明らかではありませんが、信長の政治手法が敵を作りやすいものだったことは確かでしょう。
織田信長の遺体の謎:死んでいないという噂の真相
本能寺の変では、信長の遺体が見つからなかったことが大きな謎を残しました。これが「織田信長は実は死んでいなかった」という噂の発端となりました。本能寺が鎮火した後も、信長の焼死体は焼け跡から発見されませんでした。キリスト教宣教師フロイスの『日本史』には、信長の遺骸について「灰すらも残ることなく燃え尽きた」と記されています。
遺体が発見されなかった理由としては、以下の可能性が考えられます:
- 死体が黒焦げになって誰のものか識別できなかった(当時はDNA鑑定や歯型の照合などの科学的鑑定方法がなかった)
- 家臣が信長の遺体を光秀に奪われないよう持ち出した(阿弥陀寺や西山本門寺に運んだという説もある)
- 完全に燃え尽きて灰になってしまった
生存説の可能性
しかし、同時代の公家日記などの史料を読むと、一斉に信長の死が伝えられています。信長が生きていたと記す確かな史料は存在せず、本能寺で亡くなったことは疑いないと考えられています。
もし信長が生き残っていたとすれば、天下統一のために本能寺の変以後も何らかの行動を取ったはずです。光秀に殺されかけたからといって、その後の天下を秀吉に譲るということは考えにくいでしょう。信長の歴史が本能寺の変で途切れている事実からも、生存説の信憑性は低いと言えます。
是非に及ばず:信長の最期の言葉
信長が最期に残したとされる言葉が「是非に及ばず」です。これは「もうどうしようもない」という意味で、運命を受け入れる決意の言葉だったと考えられています。
この言葉には複数の解釈があります:
- 「どうしようもない」という状況への諦め
- 「運命を受け入れる」という覚悟
- 明智光秀の裏切りを予想だにしなかったという驚き
信長は戦国時代を代表する武将として数々の戦場を生き抜いてきましたが、最も信頼していた家臣の一人に裏切られるという事態は想定外だったのでしょう。
天下統一を目前に命を落とした織田信長
天下統一を目前に命を落とした織田信長の無念は計り知れません。しかし、本能寺に火を放ち、自ら命を断つ潔さは信長の人間離れした覚悟を示しています。
信長が亡くなった1582年当時、信長の勢力は着実に拡大していました。東国では後北条氏が信長に恭順し、伊達氏・最上氏・蘆名氏といった東北の大名も信長に従う姿勢を見せていました。西では毛利氏との争いが続いていましたが、九州の大友氏とは友好関係を築いていました。
「日本全国残るところなく信長の支配下に置く決意」を表明していた信長にとって、光秀の裏切りによって命を落とすことは、まさに「天下取り」の最終段階での挫折でした。
しかし、信長亡き後、わずか11日後の山崎の戦いで羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)が明智光秀を撃破して命を奪い、信長の仇討ちを果たします。その後、秀吉は信長の路線を引き継ぎ、天下統一へと邁進していきました。
信長が目指した天下統一は、弟子の秀吉、そして家康によって最終的に実現することになります。その意味で、信長の志は後世に受け継がれ、日本の歴史に大きな影響を残したと言えるでしょう。