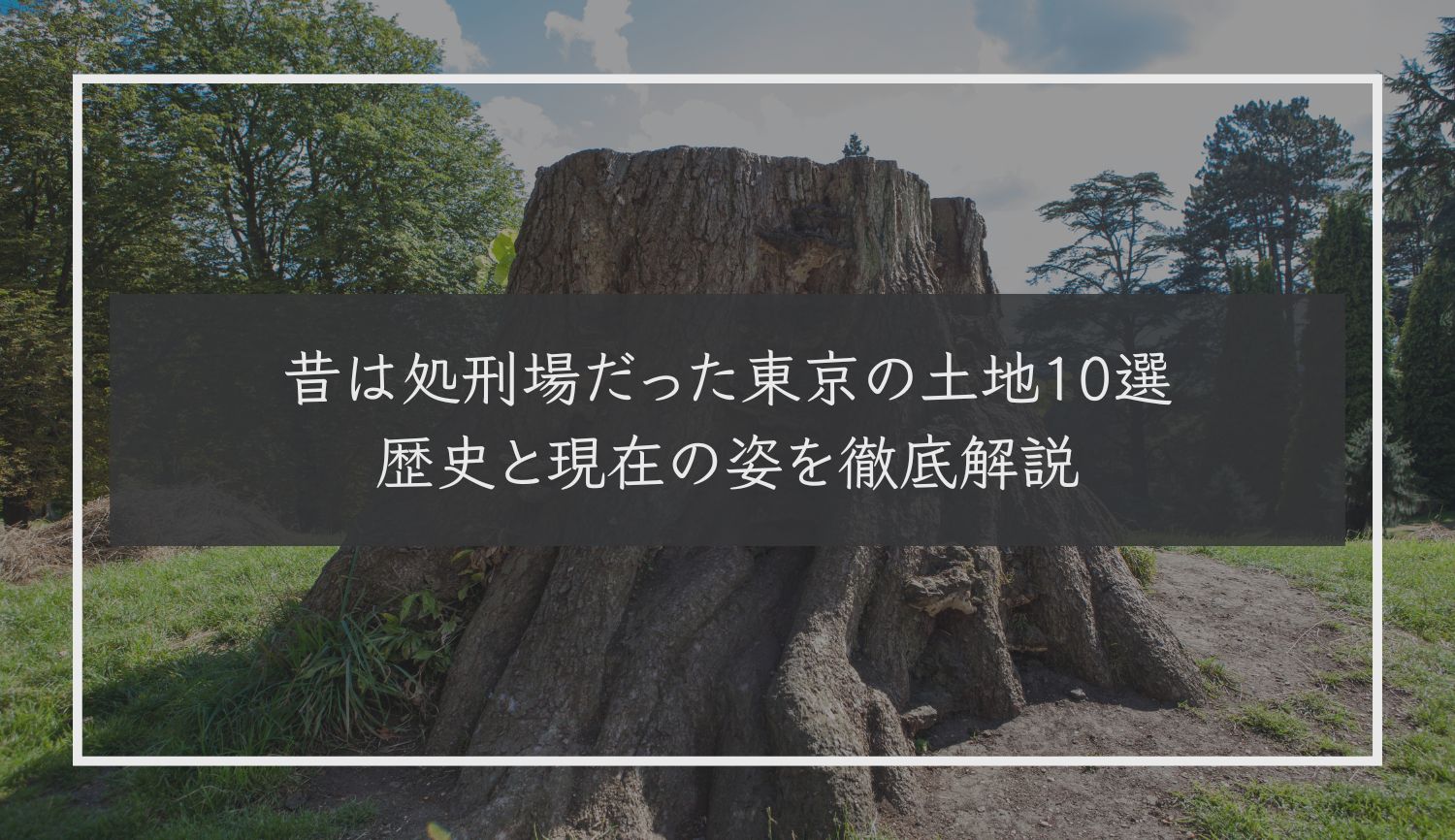江戸時代、犯罪者の処刑は公開の場で行われ、その多くが街道沿いに設置された刑場で執行されていました。見せしめとしての効果を狙い、江戸への入り口となる主要街道沿いに配置されたこれらの刑場は、明治時代の刑法改正までの約200年間、多くの人々の命が失われた場所です。
現在の東京には、かつて処刑場だった土地が都市開発によって姿を変えながらも、歴史の断片として残されています。本記事では、東京に存在した処刑場跡とその歴史、現在の姿について徹底解説します。
昔は処刑場だった東京の土地10選
その1 鈴ヶ森刑場跡(品川区南大井)
江戸三大刑場の一つとして知られる鈴ヶ森刑場は、慶安4年(1651年)に開設されました。東海道に面した江戸の南側入口に位置し、明治4年(1871年)に閉鎖されるまでの220年間で、推定10万人以上が処刑されたとされています。最初に処刑されたのは「慶安の変」の首謀者とされる浪人・丸橋忠弥でした。
鈴ヶ森刑場の特徴は、他の刑場では行われなかった「火炙り(ひあぶり)」と「磔(はりつけ)」という残酷な処刑方法が用いられていたことです。八百屋お七が放火の罪で火炙りの刑に処されたのはこの地でした。記録によると、八百屋お七の悲鳴は数キロ四方まで届いたとされています。

現在、刑場跡は国道15号線に面した大経寺の敷地内にあり、「首洗いの井戸」や磔や火炙りの台石が保存されています。京浜急行「大森海岸駅」から徒歩5分、またはJR「大森駅」から徒歩15分でアクセスできます。
その2 小塚原刑場跡(荒川区南千住)
日光街道沿いの江戸北側入口に位置していた小塚原刑場は、鈴ヶ森刑場、大和田刑場とともに江戸三大刑場の一つとされていました。ここでは安政の大獄で処刑された吉田松陰をはじめ、数多くの歴史的人物が命を落としています。
「泪橋」で最後の別れをした後、小塚原刑場で処刑され、回向院で埋葬・供養される、という江戸時代のダークな歴史の一部をなしていました。平成に入り周辺工事の際に数百の頭蓋骨や無数の四肢骨が出土し、当時の処刑後の扱いの実態が明らかになっています。
現在、刑場跡地には延命寺があり、寛保元年に造立された「首切地蔵」が安置されています。JR南千住駅から徒歩2〜3分でアクセス可能です。
その3 板橋刑場跡(板橋区板橋・北区滝野川)
江戸時代末期に一時的に存在した板橋刑場は、中山道板橋宿手前の平尾一里塚付近、現在のJR板橋駅北付近にありました。この刑場で最も有名な処刑は、慶応4年(1868年)に処刑された新選組局長・近藤勇です。近藤は平尾宿脇本陣で20日間留置された後、板橋宿入り口近くの馬捨場で斬首されました。
首は京都三条河原にさらされ、胴体は滝野川三軒家の無縁塚に埋葬されました。近藤勇の最期の地とされる場所は、新政府軍がたまたま処刑に使った「馬捨て場(馬の埋葬場)」で、元からの刑場ではなかったとされています。
現在、JR板橋駅東口から徒歩約1分の場所に、近藤勇と新選組隊士の供養塔があります。この供養塔は、新選組隊士・永倉新八が発起人となり、旧幕府典医松本順(良順)の協力を得て明治9年に建てられたものです。
その4 大和田刑場跡(八王子市大和田町)
八王子市大和田町の浅川河原に位置していた大和田刑場は、江戸の西側を担当する刑場として、鈴ヶ森刑場、小塚原刑場と並ぶ江戸三大刑場の一つでした。ここでも見せしめとしての公開処刑が行われ、処刑された人々の遺体はその場に埋葬されるか、川に流されることが多かったとされています。
刑場跡地には戦後、工場が建設されましたが、事故が相次いだため1954年(昭和29年)に慰霊碑が建立されました。しかし、その後慰霊碑も撤去され、現在では当時の痕跡は残っていません。
現在の大和田刑場跡には、学生用賃貸マンション「カレッジタウン」と「八王子ホテルニューグランド」が建っているとされています。京王八王子駅から徒歩約11分でアクセスできますが、特に目立った遺構は残っていません。
その5 伝馬町牢屋敷跡(中央区日本橋)
伝馬町牢屋敷は厳密には刑場ではありませんが、多くの政治犯が処刑された場所として知られています。安政の大獄で処刑された橋本左内や頼三樹三郎など、幕末の重要な思想家たちはここで処刑された後、小塚原回向院に葬られました。
通常の死刑は伝馬町で執行され、獄門の場合は獄内で打ち首の後、鈴ヶ森で3日間「さらし首」にされました。現在は日本橋の高層ビル街となっており、往時の面影はほとんど残っていません。
その6 涙橋(品川区南大井)
涙橋は直接的な処刑場ではありませんが、鈴ヶ森刑場に護送される罪人の肉親がこの橋まで見送って涙で別れることから、そう呼ばれるようになった場所です。
立会川(浜川)に架かる浜川橋として現存しており、鈴ヶ森刑場跡から旧東海道を北に行くとあります。現在も橋としての機能を保ちながら、歴史の一部として残されています。
その7 獄門場跡(品川区南大井)
鈴ヶ森刑場の前の浜にあった一本松は「一本松の獄門場」として恐れられていました7。ここでは死刑囚の首が晒されていました。現在は都市開発により完全に姿を消しています。
その8 三軒家(北区滝野川)
北区滝野川にあった三軒家は、近藤勇の胴体が埋葬された無縁塚のあった場所です14。現在は住宅地となっており、当時の面影は残っていませんが、寿徳寺境外墓地に近藤勇と新選組隊士の供養塔があります。
その9 平尾一里塚跡(板橋区板橋)
中山道の板橋宿の入り口にあった平尾一里塚は、近藤勇が処刑された板橋刑場のすぐ近くにありました。一里塚とは、旅行者のための目印として作られた塚で、休憩場としても機能していた場所です。現在はJR板橋駅周辺の都市開発により、その面影はほとんど残っていません。
その10 馬捨て場跡(北区滝野川)
北区滝野川にあった馬捨て場は、近藤勇が実際に処刑された場所とされています。当時は寿徳寺の土地で、馬の埋葬場になっていました。
「2つの上水に囲まれた角には、深い大やぶがあり、その向こうが馬捨て場」と記録されており、板橋駅の踏切から東口方面に少し歩いたあたりが現在の位置と推定されています。北区滝野川6-62あたりには馬頭観音が現存しています。
心霊スポットになりやすいのか?
江戸時代の処刑場跡は、その歴史的背景から心霊スポットとして認識されることが多いです。特に、大和田刑場跡には、「幽霊が目撃される」「不幸になる」「自殺や事故が起きる」といった噂が絶えません。鈴ヶ森刑場跡でも、首洗いの井戸の近くで着物姿の幽霊が写り込んだという写真が書籍『関東近郊ミステリースポット紀行』で紹介されています。
これらの噂が広まる背景には、処刑場で非業の死を遂げた多くの人々への想像と、慰霊碑撤去などの出来事が関連しています。大和田刑場跡では、1954年に建立された慰霊碑が撤去された後、再び心霊現象が頻発するようになったという噂が広がっています。
また、冤罪で処刑された者も多かったと推察され、その遺恨の思いが心霊現象として語り継がれる要因になっているという見方もあります。しかし、これらの噂のほとんどは検証困難なものであり、歴史的事実と民間伝承が混ざり合った都市伝説として捉えるべきでしょう。
昔処刑場だったところを訪れるときの注意点
注意1:現在の土地利用を尊重する
かつての処刑場跡の多くは現在、寺院や住宅地、商業施設として利用されています。鈴ヶ森刑場跡は大経寺の敷地内にあり、大和田刑場跡はホテルやマンションが建つ一般的な市街地になっています323。これらの場所を訪れる際は、現在の土地利用状況を尊重し、静かに見学することが重要です。
特に寺院内にある遺構を見学する場合は、参拝者としてのマナーを守り、写真撮影の際には事前に許可を得るようにしましょう。
注意2:歴史的事実と都市伝説を区別する
処刑場跡を訪れる際は、歴史的事実と都市伝説を明確に区別することが重要です。例えば、鈴ヶ森刑場で処刑された人物として、八百屋お七や平井権八、天一坊などが挙げられますが、鼠小僧次郎吉がここで処刑されたという説は諸説あるとされています。
歴史的背景を正しく理解するためには、現地の説明板や資料館、図書館などで信頼できる情報を得ることをお勧めします。都市伝説に惑わされず、歴史的事実に基づいて場所の歴史的意義を理解しましょう。
注意3:適切な時間帯に訪問する
処刑場跡の中には、現在も寺院や住宅地に位置しているものがあります。これらの場所を訪れる際は、周辺住民の生活に配慮し、早朝や深夜の訪問は避けるべきです。
特に鈴ヶ森刑場跡や小塚原刑場跡など、寺院内にある遺構は、寺院の開門時間内に訪れるようにしましょう。また、大和田刑場跡のように痕跡が残っていない場所は、現在の土地利用者(ホテルや住宅の居住者)への配慮が必要です。
まとめ:その土地によって必ず何かは起きている
江戸時代の処刑場跡は、時代の変遷とともにその姿を大きく変えてきました。鈴ヶ森刑場跡のように一部の遺構が残されている場所もあれば、大和田刑場跡のように完全に痕跡が消えた場所もあります。
しかし、これらの場所で起きた歴史的出来事は、現代の東京の文化や都市伝説の中に影響を残し続けています。近藤勇が処刑された板橋刑場跡近くでは「おこり」という病気が治るという言い伝えが生まれ、大和田刑場跡では慰霊碑撤去後の不可解な事故が噂されるなど、土地の記憶は形を変えて現代にも息づいています。
これらの場所を訪れることは、単なる心霊スポット巡りではなく、日本の歴史や文化、司法制度の変遷を学ぶ貴重な機会となります。歴史的事実に基づき、適切な敬意を持って訪問することで、過去と現在をつなぐ貴重な体験となるでしょう。