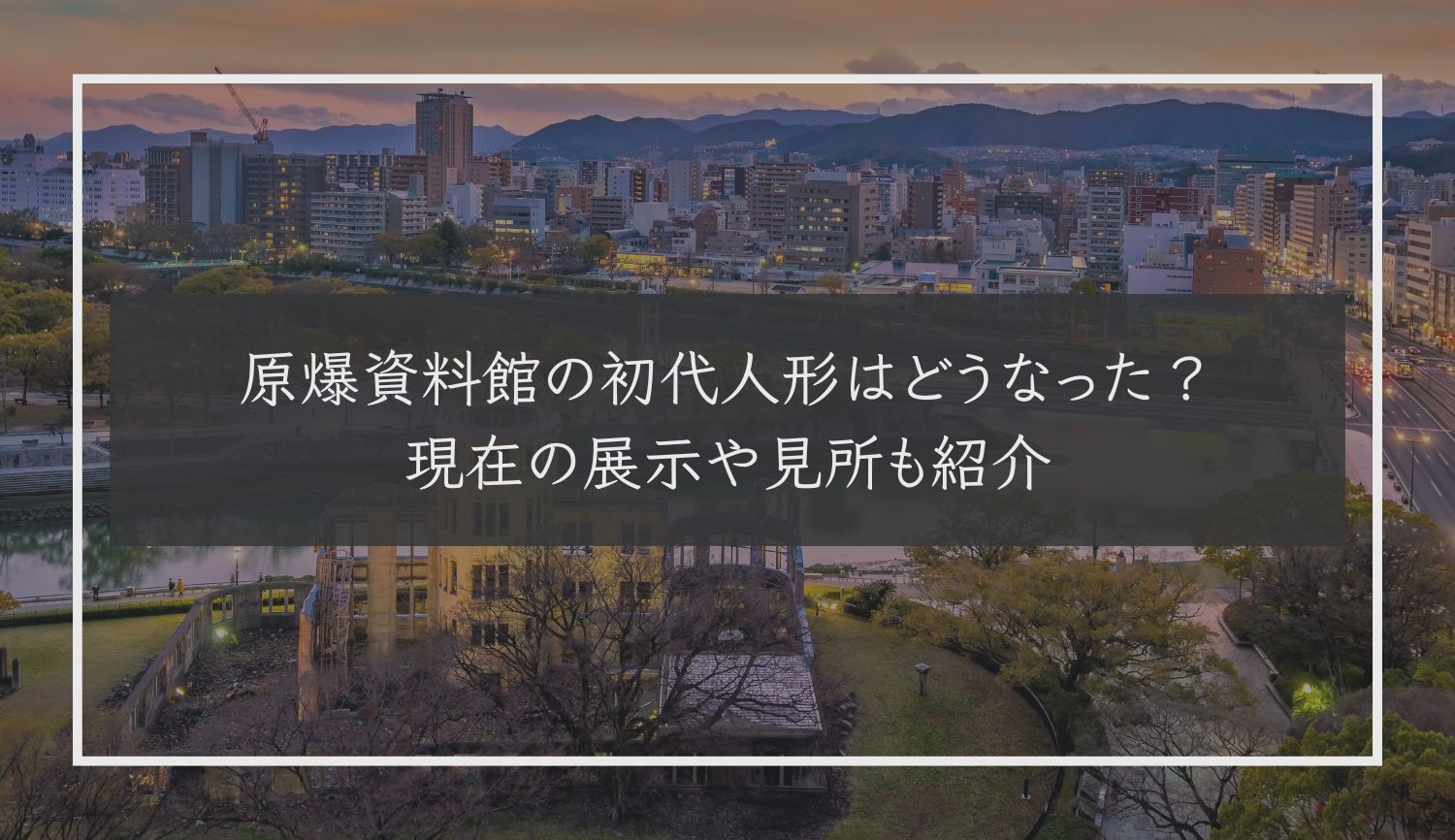広島平和記念資料館(原爆資料館)で長年展示されていた被爆再現人形は、2017年に撤去されるまで多くの来館者に強烈な印象を与え続けました。特に初代の蝋人形は、その生々しさから「都市伝説」とも呼ばれるほど強いインパクトを持っていました。本記事では、初代人形の実態と歴史的意義、そして現在の原爆資料館の展示について、新たな視点から探究していきます。
原爆資料館の初代人形とは?

1973年に設置された初代蝋人形は、原爆投下直後の被爆者の姿を等身大で再現した展示物でした。第4代館長の浜崎一治さん(後に88歳・呉市在住)の指揮のもと、被爆者治療を行った医師の知見を取り入れながら制作されました。職人は被爆直後の皮膚の状態について細部まで検討し、さらに実際に被爆者が着用していたもんぺや防空ずきんを人形に着せることで、リアリティを追求したのです。

この初代蝋人形の姿は、研究者の鍋島唯衣さんによると「蝋人形の女性の髪は、焼けて逆立ち、ブラウスとモンペは半分近くが焼けてなくなり、乳房と両手の皮膚がむけて垂れ下がり、すすけてうつろな表情を浮かべている」と描写されています。また、母親らしき女性に手を引かれて歩く男児も「全身に火傷を負い、白いランニングシャツの一部と帽子をかぶった部分の髪の毛しか残っていない」状態でした。
現在では初代蝋人形の写真はわずか3枚しか確認されていません。そのうち1枚は出所不明のネット上の写真、もう1枚は『忘却の記憶 広島』(東琢磨他編)に掲載されたもの、そして最も詳細に見られるのが『きみはヒロシマを見たか 広島原爆資料館』(高橋昭博他)に収められた写真です。
興味深いのは、これらの写真を詳細に分析すると、人形の火傷の表現と着衣の破損状態に不自然さが見られる点です。例えば、女性の両手の指先から皮膚が垂れ下がっているのに、袖口にゴムの入った着物の袖は無傷という矛盾があります。また、上衣の右胸部分だけが焼け、左胸は無事という不自然さもあります。
原爆資料館の初代人形はどうなった?
初代蝋人形は1991年に二代目のプラスチック製人形に置き換えられました。この変更の際に注目すべきは、表現の「抑制」が見られたことです。
鍋島唯衣さんによれば、二代目人形は「人形の髪は縮れ、顔は腫れているが、皮膚が焼き爛れているのは腕と手だけ」で、「着ている衣服もボロボロだが、女性と女学生の乳房が剥き出しになるほどではない」と説明されています。この変化は、資料館が来館者、特に子どもたちへの心理的影響を考慮して表現を和らげた可能性を示唆しています。二代目人形は2017年4月25日まで展示された後、広島市の大規模改修に伴って撤去されました。

初代人形の不自然さや二代目への変更の背景には、当時の資料館が直面していた課題も関係していると考えられます。1995年まで資料館の職員数は嘱託を含めてもわずか7人で、膨大な資料の整理も十分にできていない状況でした。「市長のトップダウンで「リアルに被爆状況を再現できるろう人形」をつくれといわれても、人形のコンセプトにしても資料収集にしても、僅かな人員では十分取り組むことが難しい状況だった」と指摘されています。
撤去された人形たちは現在、収蔵庫に保管されています。2024年には広島市立大の菅亮平講師(41)が資料館から人形を借り受け、素材や構造、モデルとなった被爆者の存在などを調査・分析する取り組みが始まっています2。この研究により、人形の歴史的・文化的意義が再評価される可能性があります。
原爆資料館で現在展示されている人形
被爆再現人形が撤去された現在の資料館ですが、「三位一体の人形」と呼ばれる別の展示は継続されています。これは1955年の資料館開館当初から展示されてきたもので、再現人形とは異なり、実際に原爆で亡くなった3人の中学生の遺品を使用して作られています。
津田栄一君の帽子とベルト、上田正之君のゲートル、福岡肇君の上着とズボンを、それぞれの母親(アヤ子さん、キヨさん、とみゑさん)が資料館に寄贈したものです。当時の長岡省吾館長は、津田アヤ子さんが大切な遺品を寄贈した際に「手放しにくいものを、よう入れてくれた」と涙を流したといいます7。
この「三位一体の人形」には、3人の母親の消えることのない悲しみと、原爆の悲劇を伝え続けたいという強い思いが込められています。リニューアル後も「三位一体の人形」が展示され続けているのは、「物言わぬ語り部」とも呼ばれる実物の遺品を重視する資料館の新方針にも合致しているからです。
この展示が80年近く継続されていることは、個人の物語を通じて歴史を伝える手法の有効性を示しています。実際の遺品が持つ力は、いかなる再現展示にも代えがたいものがあるのです。
原爆資料館の見所
2019年にリニューアルされた広島平和記念資料館の最大の特徴は、被爆者の遺品など実物資料の展示を重視している点です。焼け焦げた学生服や防空頭巾、溶けた瓶、変形した時計など、実物資料は言葉を超えた力を持っています。
広島市がこのような方針転換を行った背景には、「原爆の被害はやけどや爆風だけではない」という認識があります。確かに原爆被害は外見の損傷だけでなく、放射線による内部被曝や長期的な健康被害、社会的差別など、複雑で多面的な要素を含んでいます。被爆再現人形では表現しきれなかったこれらの側面を、実物資料と詳細な解説によって伝えようとする試みと言えるでしょう。
高齢化で直接の証言者が減少する中、「証言も聞けなくなりつつある時代だからこそ、作り物ではなく実物展示にこだわった」という方針は、被爆の実相をいかに後世に伝えるかという課題への一つの回答と言えます。
被爆再現人形論争から考える展示のあり方
第2に、被爆再現人形の撤去は2013年頃から「人形論争」と呼ばれる活発な議論を引き起こしました。この論争は、歴史的悲劇をどのように後世に伝えるべきかという普遍的な問いを提起しています。
撤去に反対する声としては、「インパクトがすごい。被害の実態を伝えるには必要」「立体的な人形こそ、最も心に残るはず」というものがありました。特に言葉の壁を超えて直感的に理解できる展示としての価値を評価する意見です。
一方、撤去を支持する意見としては、「胸に迫るのは焼け焦げた遺品。実物にしかない力だ」「『本物』の展示を追求してほしい」というものがありました。特に被爆者からは「被害はこんなものじゃなかった」という批判も寄せられていました。
爆心地からわずか1.2kmの場所で被爆し、全身大火傷で何度も死の淵に立った坪井さんは「被爆の実相はこんなもんじゃない、ジオラマはおもちゃである」と述べ、その言葉が人形撤去の決め手となったとも言われています。
この議論は、「再現」と「実物」、「インパクト」と「正確さ」のバランスという、歴史展示の本質的な問題に関わるものです。異なる見解があることは自然であり、両方のアプローチにはそれぞれ意義があると言えるでしょう。
原爆資料館は時代と共に変化してきました。1994年には「広島平和記念資料館条例」が全面改正され、資料収集や調査研究に加え、平和学習や被爆体験継承事業も業務に追加されました3。1995年からは膨大な遺品の整理・データベース化が始まり、デジタル技術を活用した新しい展示方法も導入されています。
リニューアル後の資料館では、CGパノラマや触れる模型なども取り入れられていますが、これらに対しても賛否両論があります。テクノロジーを活用することで没入感を高め、若い世代にも訴求しやすくなる一方で、過度の演出によって本質が薄れることへの懸念もあるのです。
被爆体験継承の課題は世界各国の戦争・平和博物館も直面している普遍的なものです。例えば、アメリカの「9.11 メモリアルミュージアム」では、実物資料の展示だけでなく、ストーリーテリングやアートを通じた展示も取り入れられています。原爆資料館もまた、実物重視の方針を維持しつつ、補完的なアプローチとしてデジタル技術やストーリーテリングの手法を統合していくことが今後の課題と言えるでしょう。
まとめ:記憶を未来へつなぐ使命
広島平和記念資料館の被爆再現人形の変遷は、「原爆の実相をどう伝えるか」という永続的な課題への取り組みの一部です。初代蝋人形から二代目プラスチック人形、そして実物資料中心の現在の展示まで、時代と共に変化してきた表現方法には、それぞれの時代の思想や制約が反映されています。
重要なのは、展示方法の是非を単純に判断することではなく、複数のアプローチの可能性を認識することでしょう。被爆再現人形が多くの人々に与えた強烈な印象は確かに貴重であり、実物資料が持つ真実性と迫力もまた代替不可能です。
現在、被爆者の高齢化が進み、直接体験を語れる方が少なくなる中、資料館の役割はますます重要になっています。2024年に始まった菅亮平講師による人形の調査分析2は、過去の展示物を単に歴史的遺物として扱うのではなく、その意義を現代