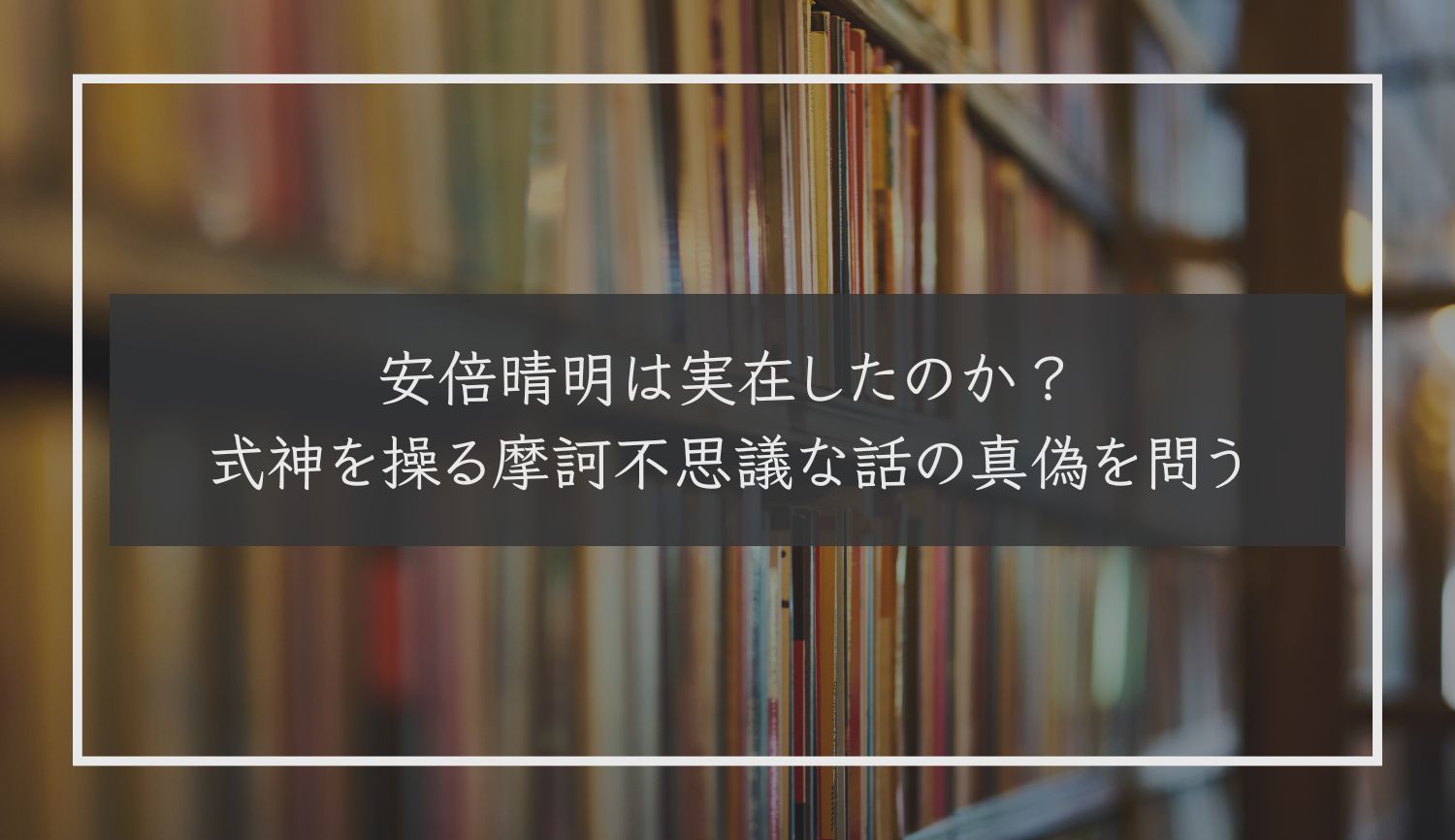平安時代の陰陽師として名高い安倍晴明。現代においてもドラマや小説、映画など多くのメディアに登場し、神秘的な力を持つ人物として語り継がれています。しかし、彼が実際に存在した人物なのか、そして伝説として語られる能力は真実なのでしょうか。
本記事では、歴史資料とともに安倍晴明の実像に迫り、式神を操ったとされる摩訶不思議な話の真偽について検証します。平安時代の公文書から現代の研究まで、様々な視点から安倍晴明の姿を浮かび上がらせ、なぜ1100年を超えて人々を魅了し続けるのかを探ります。
安倍晴明の経歴
安倍晴明(あべのせいめい)は延喜21年(921年)2月21日に生まれ、寛弘2年(1005年)10月31日に85歳で没したとされています。「晴明」の読み方は現代では「せいめい」と呼ばれていますが、当時の正確な読み方は「はるあき」「はるあきら」という説もあり、確定していません。彼の出生地については、現在の大阪市阿倍野区だとする説と、奈良県桜井市安倍だとする伝承があります。
晴明の系譜については明確な記録がなく、安倍益材(あべのますき)または安倍春材の子とされていますが、様々な説があります。中には、阿倍御主人(『竹取物語』に登場する右大臣)の子孫、あるいは阿倍仲麻呂の子孫だとする説話も残されています。
彼の職歴を紐解くと、天暦2年(948年)に大舎人となり、天徳4年(960年)に40歳で天文得業生(陰陽寮に所属し天文博士から天文道を学ぶ学生)として記録に登場します。この頃から村上天皇に占いを命じられるなど、才能が認められ始めていたようです。50歳頃に天文博士に任じられ、その後、貞元2年(977年)に師である賀茂保憲が没してから陰陽道の世界で頭角を現し始めました。
晴明は陰陽頭(陰陽寮の長)には就任しませんでしたが、位階はその長よりも上位にありました。天元2年(979年)には59歳で当時の皇太子師貞親王の命で那智山の天狗を封じる儀式を行い、これを機に花山天皇の信頼を得たとされています。その後、一条天皇や藤原道長の信頼も集め、様々な儀式や占いを行いました。特に注目すべきは、正暦4年(993年)に一条天皇が急病に伏せった際、晴明が禊を行うとたちまち回復したとされる逸話で、この功績により正五位上に叙されています。
晴明は天文道での計算能力を買われて主計寮に異動し、主計権助を務めた後、左京権大夫、穀倉院別当、播磨守などの官職を歴任し、位階は従四位下にまで昇りました。彼の息子たちも陰陽道の家として地位を確立し、晴明一代の間に賀茂氏と並ぶ家系となりました。
安倍晴明は実在したのか?
安倍晴明が実在したかどうかという問いには、明確に「実在した」と答えることができます。多くの歴史資料に彼の名前と活動が記録されているからです。平安時代の公家たちの日記や歴史書には、晴明が実際に朝廷に仕え、天皇や貴族のために占いや儀式を行った記録が残されています。

例えば、藤原実資の日記『小右記』には984年(永観2年)に円融天皇から花山天皇への譲位の日時を選定したこと、986年(寛和2年)に太政官官舎に現れた蛇の怪異を占ったことなどが記されています。また、藤原道長の日記『御堂関白記』には1000年(長保2年)に道長の娘・彰子の立后の日時を選んだこと、1004年(寛弘元年)に彰子の行啓(外出)の是非を占ったことなどが記録されています。
さらに、989年(永祚元年)に一条天皇の病気に禊祓を行い天皇が回復したこと、同年に一条天皇のために泰山府君祭を行ったこと、1004年に日照りが続いた際に晴明に雨乞いをさせたところ30日余りぶりに大雨が降ったことなども記録されています。これらの歴史的記録は、晴明が単なる伝説上の人物ではなく、実在した陰陽師であったことを裏付けています。
京都には晴明神社が存在し、彼の墓も現存していることも、彼の実在を示す物理的証拠となっています。晴明神社は彼の功績を称えて建てられたもので、現在も多くの参拝者が訪れています。
しかし、晴明の実像と後世に語られる伝説の間には大きな隔たりがあります。彼は確かに実在した人物ですが、超自然的な力を持つヒーローというイメージは、主に江戸時代以降の創作や、1980年代後半から始まった夢枕獏の小説シリーズ『陰陽師』などによって形作られたものと言えるでしょう。
安倍晴明は何をした人物なのか?
史実の安倍晴明は、霊能力者というよりも、朝廷で天体観測などを行い、暦づくりを担当する陰陽寮に勤める役人、つまり「公務員」でした。陰陽寮は7〜10世紀の律令制下に置かれた国家機関の一つで、陰陽・暦・天文・漏刻(水時計で時刻を計る)の4つの政務を担当していました。
晴明は特に天文博士として、天体や気象を観測する役割を担っていました。本来、天文博士は陰陽(占い)を行う立場ではありませんでしたが、晴明が生きた時代には暦・天文担当者も陰陽を行っており、こうした境界は曖昧になっていたようです。
晴明の主な仕事は、貴族や朝廷のために卜占(占い)を行うことでした。例えば、貴族の女性が天皇の妻となる際の吉日を占ったり、屋敷に蛇が入り込むなどの怪異(不思議な出来事)が何を予兆しているのかを判断したりしました。また、特定の日や方角に関する禁忌(タブー)についても助言を行いました。
晴明の占いの的中率は約7割程度だったとされ、通常は5割も当たれば優秀とされる中、彼の能力は際立っていました。藤原行成の日記『権記』では「(陰陽)道の傑出者」と評されているほどです。
さらに、晴明は様々な願望をかなえるための呪術や祈祷の達人でもありました。一条天皇の病気を治したり、日照りが続いた際に雨乞いをしたりと、その技術は多岐にわたります。
特筆すべきは、晴明が陰陽道に日本独自の解釈をもたらしたことです。当時、陰陽寮の研究者たちは大陸から渡来した最新技術を学び模倣することが一般的でしたが、晴明はそれらをただなぞるだけでなく、中国と日本の条件や環境の違いを考慮して日本独自の形を作り上げました。これは当時の社会にとって革新的であり、貴族たちは競って晴明の意見を取り入れるようになりました。
式神を操る摩訶不思議な話の真偽
安倍晴明が式神(しきがみ)と呼ばれる霊的な存在を操ったという伝説は広く知られていますが、これは主に後世の創作によるものと考えられています。晴明を霊能力者として描いたのは、1980年代後半から続く夢枕獏の小説シリーズ『陰陽師』が初めてだという説もあります。
しかし、式神に関する記述が全くなかったわけではありません。平安時代末に成立した説話集『宇治拾遺物語』には、晴明に関連する式神の逸話が収録されています。この話によると、藤原道長が自身の邸宅に隣接する法性寺に参詣しようとした際、飼っていた白い犬が鳴いたため、不吉な予感を覚えた道長が晴明を呼び寄せたところ、晴明の弟子筋にあたる道摩法師から「式神」を使った呪いがかけられていることが判明したというものです。
興味深いのは、この時の「式神」が現代のイメージする使い魔のようなものではなく、2つの土器を重ねてその中に「呪」と書いた黄色い紙を入れただけの装置だったという点です。つまり、当時の「式神」とは術者が呪力を込めた物理的な装置であり、現代のファンタジー作品に登場するような霊的な存在ではなかったのです。
また、安倍晴明の母親が狐であったという伝説も広く知られていますが、これも史実ではなく後世の創作です。この伝説では、晴明が幼少の頃、母親が自らの正体を明かした後に彼の元を去り、以降は霊的な力で見守り続けたとされています。この物語は晴明の非凡な能力の由来を説明するために作られたものと考えられます。
歴史的な記録によると、当時の陰陽師は「物の怪」(霊的な存在)とは戦わず、「神の怪」(神通力を使う同業者の陰陽師)と戦っていたとされています。つまり、史実の晴明は霊的な存在と戦うヒーローというよりも、同業者間の競争の中で頭角を現した専門家だったのです。
まとめ:最も有名な陰陽師だった
安倍晴明は確かに実在した人物であり、平安時代を代表する陰陽師として、朝廷や貴族社会で重要な役割を果たしました。彼は単なる霊能力者ではなく、天体観測や暦作成を担当する国家公務員であり、占いや儀式を通じて当時の社会の安定に貢献しました。
晴明の最終官位は従四位下であり、これは同時代の紫式部の父・藤原為時(正五位下)や清少納言の父・清原元輔(従五位上)よりも高い地位でした。このことからも、彼が当時の社会で高い評価を受けていたことがうかがえます。
特に注目すべきは、晴明が中国から輸入された陰陽道に日本独自の解釈を加え、日本の風土や文化に適した形に発展させたことです。これは単なる技術の模倣ではなく、創造的な適応であり、日本文化の発展における彼の重要な貢献と言えるでしょう。