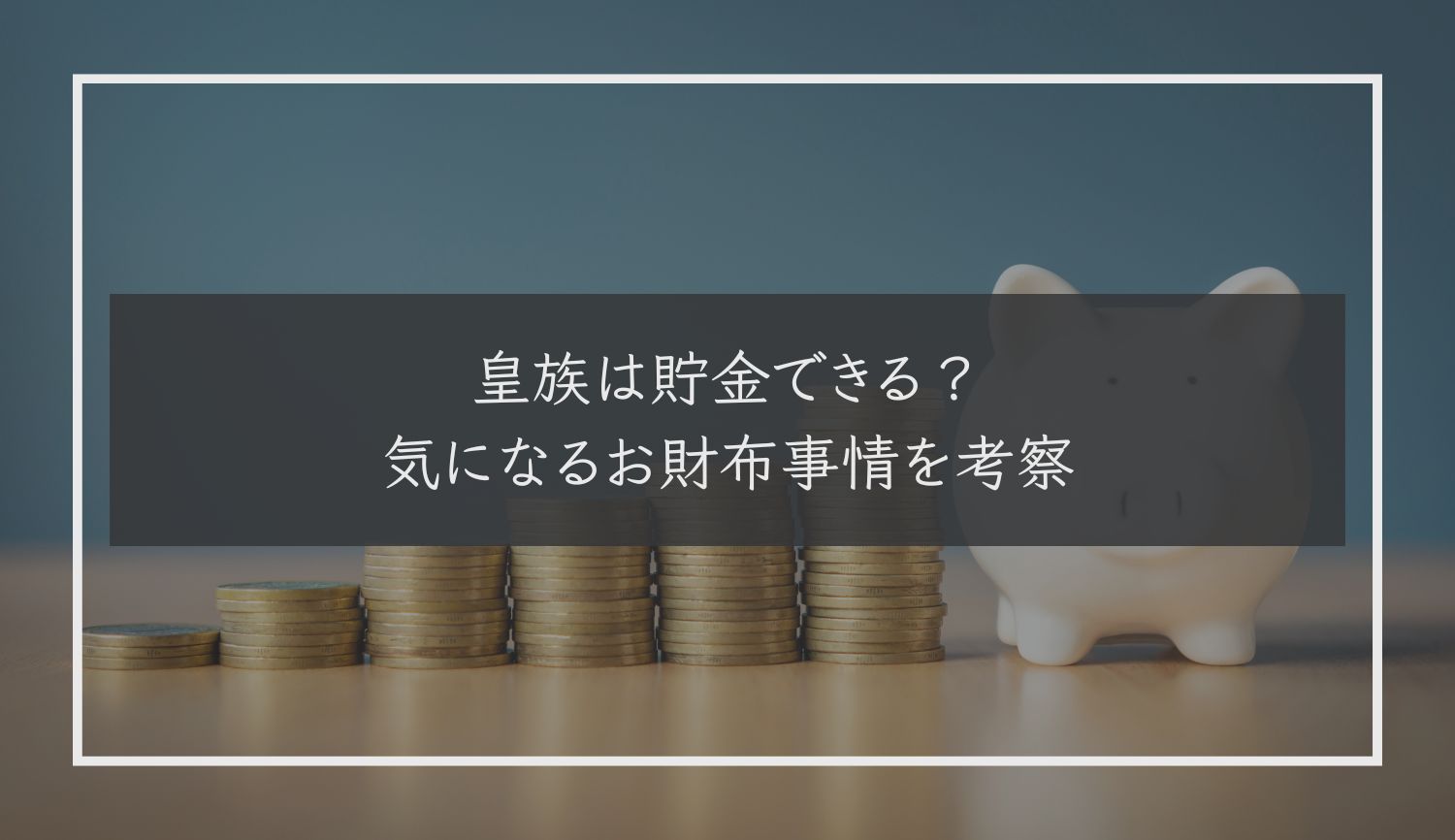日本の皇室は国民にとって特別な存在ですが、その経済状況については意外と知られていないことが多いものです。「皇族はお金持ち」というイメージを持つ人も多いでしょうが、実際の皇室の財政状況はどうなっているのでしょうか?
皇族は一般の人々のように貯金ができるのか、必要な時にはどのようにお金を工面するのか、年間でどれくらいの予算を消費できるのかなど、皇室のお財布事情について詳しく見ていきましょう。
皇族は貯金できる?
日本国憲法第88条では「すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」と定められています。つまり、皇室の財産は基本的に国のものであり、皇室に関わるすべての費用は国会で審議・決定されるのです。この点は戦前と大きく異なり、現在の皇室は憲法によって財産の所有や使用に厳しい制限が設けられています。
皇室には私的費用に使用される「内廷費」が毎年3億2400万円支給されていますが、さまざまな経費が支出されるため、多くを貯蓄に回すことは困難だと言われています。この金額は1996年から変わっていないことも注目すべき点です。
内廷費の使途として公表されている内訳は、人件費(33%)、衣類など身の回りのもの(18%)、食費など(13%)、医療その他(12%)、交際費・災害見舞金(10%)となっています。特に人件費に多くの割合が割かれているのは、宮中祭祀を担当する神職を私的に雇用しているためです。憲法の政教分離の原則から、公費で神事に関わる人件費を賄うことができないため、内廷費から支出しているのです。
戦前の昭和天皇は、日本銀行などの金融機関のほか、鉄道会社、ホテルなど約30社の企業の株式や債券を保有していました。崩御の際、20億円の金融資産を残していたため、上皇陛下(当時の今上天皇)は約4億2400万円の相続税を納めています。

一方、現在の上皇陛下の金融資産については、「内廷費」からの余剰金が少ないため、多くの貯蓄ができていないと推測されています。また、生前退位の際には新天皇陛下に対して資産相続はしなかったとされており、このことからも皇室の資産状況がうかがえます。
皇族はお金が必要なときにどうするのか?
皇室の財産の授受については非常に厳しい制限があります。皇室経済法施行法第2条によると、以下の金額の範囲内を除いて、財産の授受には国会の議決が必要とされています:
- 天皇・内廷皇族:年間1,800万円(賜与の限度額)、600万円(譲受の限度額)
- 宮家の皇族(成年):各160万円(賜与・譲受とも)
- 宮家の皇族(未成年):各35万円(賜与・譲受とも)
例えば、親から子へのお祝い金なども、これらの制限内でしか渡すことができません6。一般的な家庭では当たり前の金銭のやり取りでも、皇族の場合は厳しく制限されているのです。
皇室に関わる特別な支出が必要な場合、例えば結婚や即位といった特別な機会には、憲法第8条に基づき国会の議決を求める必要があります。過去の事例としては、昭和34年の明仁親王(上皇陛下)のご結婚、平成2年の天皇陛下のご即位、平成5年の徳仁親王(現在の天皇陛下)のご結婚、令和元年および令和2年の天皇陛下のご即位などがあります。
天皇は憲法上の地位から職業に就くことができませんが、書籍出版による印税など一部の収入を得ることは可能です。一方、他の皇族には職業選択の自由を制限する規定はなく、実際に公益財団の職員、認可法人の委託職員、大学講師などの職業に就いている皇族もいます。
これらの収入は「内廷費」「皇族費」「宮廷費」以外に該当するため、所得税の納税義務が発生します。つまり、皇族も一般国民と同様に、収入に対しては税金を納めなければならないのです。
皇族が年間で消費可能な予算
皇室関係の予算は「皇室費」と「宮内庁費」に大別されます。「皇室費」は天皇家と宮家に直接関係する予算で、2021年度は124億2147万円でした。これに対し、「宮内庁費」は宮内庁の運営のために必要な人件費・事務費で、同年度は125億8949万円となっています。
「皇室費」はさらに以下の三つに分けられます:
1. 内廷費(2021年度:3億2400万円)
天皇・上皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものです。使途の割合は先に述べた通りですが、特筆すべきは神事に関わる人件費や、上皇陛下のハゼの研究を行う皇居内の生物学御研究所や養蚕を行っている御養蚕所の職員給与なども、この内廷費から支出されていることです。
2. 皇族費(2021年度総額:2億6372万円)
皇族としての品位保持の資に充てるためのもので、各宮家の皇族に対し年額により支出されます。基本となる定額は皇室経済法によって定められています。
各皇族への支給額を見ると、例えば秋篠宮家の場合:
- 皇嗣(皇位継承順位1位の皇族)である秋篠宮さま:9150万円(定額の3倍)
- 紀子さま:1525万円(定額の2分の1)
- 成人した子である眞子さまと佳子さま:各915万円(定額の10分の3)
- 悠仁さま:305万円(定額の10分の1)
となっており、合計で1億2810万円となります。
また、皇族が初めて独立の生計を営む際や、皇族がその身分を離れる際には一時金も支給されます。例えば、民間人と結婚して皇族の身分を離れる場合の一時金は最大で1億5250万円となりますが、眞子さまは辞退されたことが報じられました。
3. 宮廷費(2021年度:91億7145万円、2025年度要求:95億5381万円)
儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居等の施設の整備に必要な経費などです。ティアラなどの装飾品もこの予算から支出されますが、愛子さまのティアラが新調されていない状況が続いているとの報道もあります。
まとめ:貯金はできないけど資産はある?
皇室は一般に「お金持ち」というイメージがありますが、実際には厳しい財政的制約の中で生活しています。内廷費や皇族費からの余剰金は限られており、大きな貯蓄は難しい状況にあるようです。
皇居や京都御所などの施設は国有財産であり、皇室の私有財産ではありません。相続税がかかるのは、皇室が個人で所有している美術品などに限られ、皇位継承の証である三種の神器は法令で相続税の対象外となっています。
皇族の数の減少は、皇室の財政面でも課題となっています。2025年3月10日には、皇族数確保に関する全体会議が開かれ、「皇統に属する男系男子の養子縁組を認める案」が議論されました。こうした議論の背景には、皇室の継続性とともに、皇室の財政基盤の維持という側面もあると考えられます。
また、社会情勢の変化や物価の上昇に対して、内廷費が1996年から変わっていないことも注目すべき点です。今後、皇室の財政状況がどのように変化していくのかも見守っていく必要があるでしょう。
皇室の生活は「みやび、華やか、きらびやか」というイメージがありますが、実際には「豪華絢爛」と感じる機会はあまりないという指摘もあります。例えば、天皇、皇后両陛下の長女愛子さまのティアラが新調されていない状態が続いていることなどは、皇室の質素な一面を示しているのかもしれません。
2025年に介護についての不安が高まっている日本社会において、皇室も同様の課題に直面している可能性があります。皇族の高齢化に伴い、医療費などの支出が増加する可能性も考えられるでしょう。以上のように、皇室のお財布事情は一般のイメージとは異なる面が多くあります。国民の代表である国会の議決に基づいて決定される皇室の予算は、皇室の公的活動と私的生活の両方を支える重要な基盤となっているのです。