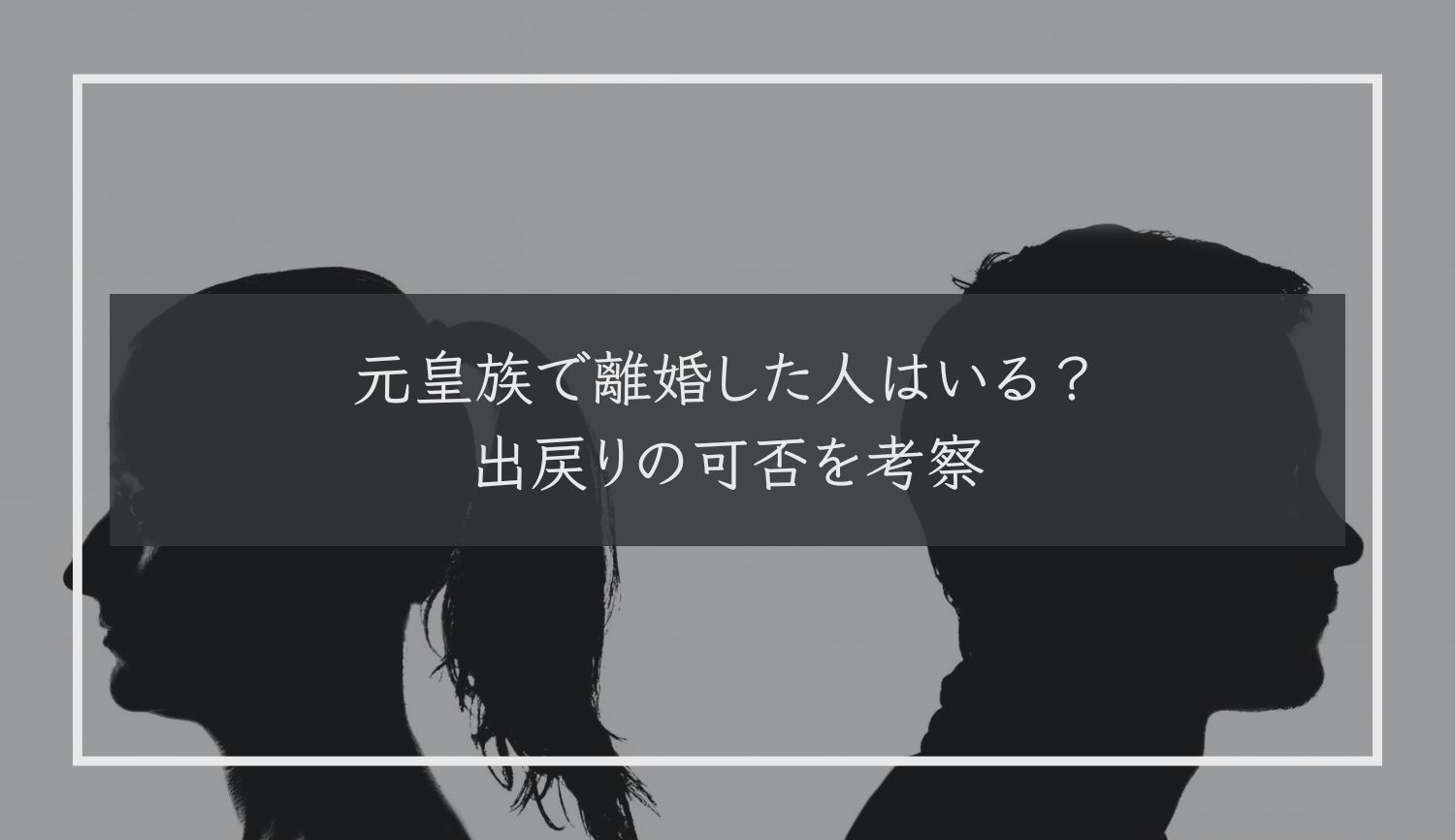戦後日本の皇室と離婚に関する歴史は、意外にも知られていない側面が多い。皇族が一般人と結婚して皇籍を離れた後に離婚した場合、二度と皇室に戻ることができないという事実は、皇室典範と日本国憲法によって厳格に規定されている。
実際に離婚を経験した元皇族の事例は数少ないが、それらは時代の価値観の変化を映し出す鏡となっている。本稿では、華頂博信・華子夫妻や久邇宮朝融王の三女・通子さんの事例を詳細に分析しながら、皇族の離婚と「出戻り」の問題について、法的根拠と社会的背景の両面から考察していく。
元皇族で離婚した人はいる?
戦後の日本社会において、旧皇族の離婚は稀ではあったが確かに存在し、その度に大きな社会的関心を集めてきた。最も著名な事例として、1951年に離婚した華頂博信・華子夫妻の「華頂事件」がある。博信(1905-1970年)は、伏見宮家の三男として生まれた皇族だったが、1926年に21歳で結婚するにあたり臣籍降下し、華族となった。妻の華子(1909-2003年)は閑院宮家の五女で、かつては秩父宮妃の候補として名前が挙がったこともある高貴な出自の持ち主だった。
彼らの離婚は、1951年7月18日の夜、博信が客間に隣接する衣装部屋(クローク・ルーム)で、妻の華子と実業家の戸田豊太郎(当時51歳)の不貞行為を目撃したことから始まる。『毎日新聞』の1951年8月22日付の社会面では、「私は離婚せざるを得ない」「許せない歪んだ自由」という見出しで、この衝撃的な出来事が報じられた。
この報道は三流映画のようなセンセーショナルな描写で、社会に大きな衝撃を与えた。

離婚後、華子は翌年に戸田と再婚し、その後のメディアでは「女の幸福を愛情の歓びに」「再婚して新生活をきずく戸田華子さん」といった肯定的な見出しで取り上げられるようになる。この転換は、戦後の「婦人の解放と因習の打破」という社会的風潮を反映していた。
もう一つの注目すべき事例は、昭和天皇の妻である香淳皇后の兄、久邇宮朝融王の三女・通子さんの離婚である。通子さんは学習院大学在学中に一般学生と恋に落ち、1959年に家族の強い反対を押し切って結婚した。
いわゆる「駆け落ち婚」と呼ばれるこの結婚は、家族からの勘当という厳しい結果をもたらし、東京・飯田橋の2部屋しかないアパートでの簡素な新婚生活が始まった。しかし、この結婚は4年後に破綻し、離婚に至った。注目すべきは、通子さんがその後再婚し、現在88歳となった今も東京郊外の団地で静かに暮らしているという点である。初婚は失敗に終わったものの、その後の人生で幸せを見出したという事実は、元皇族の離婚後の人生が必ずしも不幸で終わるわけではないことを示している。
これらの事例は、戦後日本社会における価値観の変化と、皇族を含む上流階級の人々の生き方の変容を如実に表している。特に女性の社会的立場と結婚観に関する急速な変化は、「華頂事件」や通子さんの「駆け落ち婚」を通じて鮮明に浮かび上がってくる。旧皇族の離婚は、単なる個人的出来事を超えて、時代の転換点を象徴する社会現象としての意味を持っていたのである。
皇族は離婚した後に出戻りできるのか?
皇族が結婚後に離婚した場合、「出戻り」として皇室に戻ることができるのか—この問いに対する答えは明確である。皇族、特に女性皇族が一般人と結婚して皇籍を離れた場合、離婚しても二度と皇族の身分に戻ることはできない。
この原則は、日本の皇室制度の根幹に関わる重要な規定であり、法的・社会的に強固な基盤を持っている。
まず、皇族の身分について理解すべき重要な点がある。一般的に日本国民は「戸籍」に登録されるが、皇族には戸籍がなく、代わりに「皇籍」に登録される。女性皇族が一般人と結婚すると、皇籍から離脱し、新たに戸籍が作られる。ここで重要なのは、一度皇籍を離れると、離婚後であっても皇籍に復帰することはできないという点である。
この原則の法的根拠は、主に二つある。第一は、皇室典範第15条の規定である。同条では「皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族になることがない」と明確に定められている。つまり、天皇や男性皇族との婚姻を介さない限り、一般人が皇族になることはできないのである。

第二の根拠は、日本国憲法第14条第1項に基づく平等原則である。「すべて国民は、法の下に平等であつて…門地により…差別されない」という憲法の規定により、元皇族だからという理由で特別に皇籍を再取得することは、他の一般国民との平等を損なうことになるため認められない。
皇族の離婚に関連して、「皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律」第3条では、「(婚姻によって皇籍離脱された元皇族の女性が)離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する」と定められている。
つまり、離婚後も皇籍に復帰できないため、一般国民としての新たな戸籍が必要となるのである。
皇室典範の制定過程で、当時の法制局(現在の内閣法制局)は、この原則について「臣籍に降下したもの及びその子孫は、再び皇族となり、又は新たに皇族の身分を取得することがない原則を明らかにし…皇位継承資格の純粋性(君臣の別)を保つため」と説明している。この説明からは、皇族と一般国民(臣下)の区別を明確にし、皇位継承に関わる資格の「純粋性」を維持することが重視されていたことがわかる。
一方、現在の皇室において、天皇と皇后には離婚の権利そのものが認められていない点も注目に値する。皇太子や親王の段階では離婚は可能であるが、一度天皇に即位すると、離婚することは不可能となる4。これは、天皇の地位の安定性と継続性を重視する考え方に基づいていると考えられる。
以上のように、皇族の離婚と「出戻り」の問題は、単なる家族法の問題ではなく、日本の国家制度の根幹に関わる原則に基づいている。一度皇籍を離れた者が皇族に戻れないという規定は、皇位継承の純粋性を保ち、皇族と一般国民との区別を明確にするという、日本の皇室制度の基本理念を反映しているのである。
人間ならば離婚する可能性もある
皇族も人間である以上、結婚生活に困難を抱え、離婚を考える状況に直面することもあり得る。この視点から皇族の離婚について考えることは、皇室を神聖視するだけでなく、その人間的側面を理解する上で重要である。
華頂博信と華子の離婚事例を詳しく見ると、彼らの不和の背景には人間関係の普遍的な課題が見え隠れする。博信は元々海軍軍人で、「学究肌」と報じられており、一方の華子は「社交好き」とされていた1。こうした性格の不一致は、どのような夫婦にも起こり得る摩擦の原因である。さらに、戦後の混乱期という時代背景も彼らの関係に影響を与えたと考えられる。博信は敗戦時に海軍中佐で、戦後は本宅を焼き出され、養鶏やダンス教師などの職業を転々としていた。こうした急激な生活環境の変化は、夫婦関係に大きなストレスをもたらしたことだろう。
華子自身は離婚後のインタビューで、「私共の仕事の面でもいろ〳〵面倒をみていたゞくこともあるようになり、家へも時々遊びにいらつしておりました。そのうちにだん〳〵私の生活の不満、さびしさが戸田さんとの間を更に深いものとするようになり、昨年のクリスマスのころから私の気持は急速に傾いていつたのです」と心境を吐露している。
この告白からは、孤独感や満たされない思いが、彼女を別の関係へと導いていった過程が垣間見える。これは皇族特有の問題というよりも、むしろ人間関係の普遍的な課題を反映していると言えるだろう。
また、久邇宮家の通子さんの「駆け落ち婚」とその後の離婚も、人間の感情と社会的制約の間の葛藤を示している。彼女は学生時代に恋に落ち、家族の強い反対を押し切って結婚したが、その関係は4年で終わりを告げた。愛情だけでは乗り越えられない現実的な障壁が存在したことを示唆している。
興味深いのは、こうした皇族や元皇族の離婚が、当時の社会に与えた影響である。特に戦後の民主化の流れの中で、「婦人の解放と因習の打破」が進む社会において、皇族を含む上流階級の人々の離婚は、新しい時代の価値観を象徴する出来事として捉えられた。華子や高松宮家出身の佳子(李鍵の元妻)は「メディアの寵児」となり、彼女たちの再婚生活は「女の幸福を愛情の歓びに」といった肯定的な文脈で報じられるようになった。
現代においても、皇族の結婚と離婚に対する社会的関心は高い。眞子さま(現・小室眞子さん)と小室圭さんの結婚をめぐる一連の出来事は、皇族の結婚と離婚に関する議論を再び活性化させた。仮に離婚となった場合、眞子さんが皇族に戻れないこと、一時金として支給された約1億3000万円の扱いが問題になる可能性があることなどが指摘された。
日本の皇室において離婚率が一般の国民と比べて低いのは事実であるが2、これは単に制度的な制約だけでなく、結婚に対する覚悟の違いも反映していると考えられる。皇族、特に女性皇族の結婚は、単なる個人的選択ではなく、皇籍を離れるという不可逆的な人生の転換点となる。そのため、結婚の決断には並々ならぬ覚悟が必要となり、それが離婚率の低さにつながっている可能性がある。
しかし、どれほど慎重に結婚を決めたとしても、人間である以上、関係が破綻する可能性は常に存在する。皇族や元皇族の離婚事例は、彼らも普通の人間として喜びや苦しみを経験することを私たちに思い出させる。そして、離婚後に新たな幸福を見出した通子さんの例は、人生には常に再出発の可能性があることを示している。皇族という特別な立場にあっても、人間の感情と関係性の複雑さは変わらないのである。
まとめ:デマに踊らされないように!
皇族の離婚に関する話題は、時に誤解や憶測、さらには意図的な誤情報が流布されることがある。正確な情報に基づいて理解することが重要である。
まず、明確にしておくべき事実がある。皇族、特に女性皇族が一般人と結婚して皇籍を離れた場合、離婚しても皇族に戻ることはできない。この原則は、皇室典範第15条と日本国憲法第14条に基づく確固たる法的根拠を持っている。「離婚すれば皇室に戻れる」といった誤解は、法的根拠を欠いた思い込みに過ぎないのである。
また、皇族の離婚可能性についても正確な理解が必要だ。親王や王は離婚することができるが、天皇と皇后には離婚の権利が認められていない。これは皇位の安定性を確保するための重要な制度的枠組みである。
歴史的に見ると、元皇族の離婚事例は確かに存在する。華頂博信・華子夫妻の「華頂事件」や、久邇宮家の通子さんの離婚などは、戦後日本社会における価値観の変化を映し出す重要な事例である。しかし、こうした事例を単なるゴシップとして消費するのではなく、その背景にある社会的・歴史的文脈を理解することが大切だ。
特に注意すべきは、皇族の離婚に関する議論が、しばしば憶測や個人的な願望に基づいて展開されることである。例えば、「皇籍に戻れない根拠」について述べる際に、憲法第8条を引用し「皇室から民間への財産の使用は国会の議決なしにはできず、事実上禁じられているから」と説明する例が見られたが、これは明らかな誤りである。憲法第8条は皇室と外部との財産の授受に関する規定であり、皇籍復帰の可否とは無関係である。こうした誤った解釈が広まると、皇室制度への理解が歪められる恐れがある。
最後に、皇族や元皇族も一人の人間であるという視点を忘れてはならない。彼らの結婚や離婚を単なる制度的・政治的問題として議論するだけでなく、その背後にある人間的な葛藤や感情にも想像力を働かせることが、より深い理解につながるだろう。通子さんが離婚後に再婚し、静かな幸福を見出した例5は、どのような境遇であっても、人生には常に再出発の可能性があることを教えてくれる。
皇室に関する話題に接する際は、センセーショナルな見出しや根拠のない憶測に惑わされることなく、正確な事実に基づいて考えることが大切である。そうすることで、日本の伝統と文化の重要な一部である皇室への理解が深まり、より建設的な社会的議論が可能になるだろう。