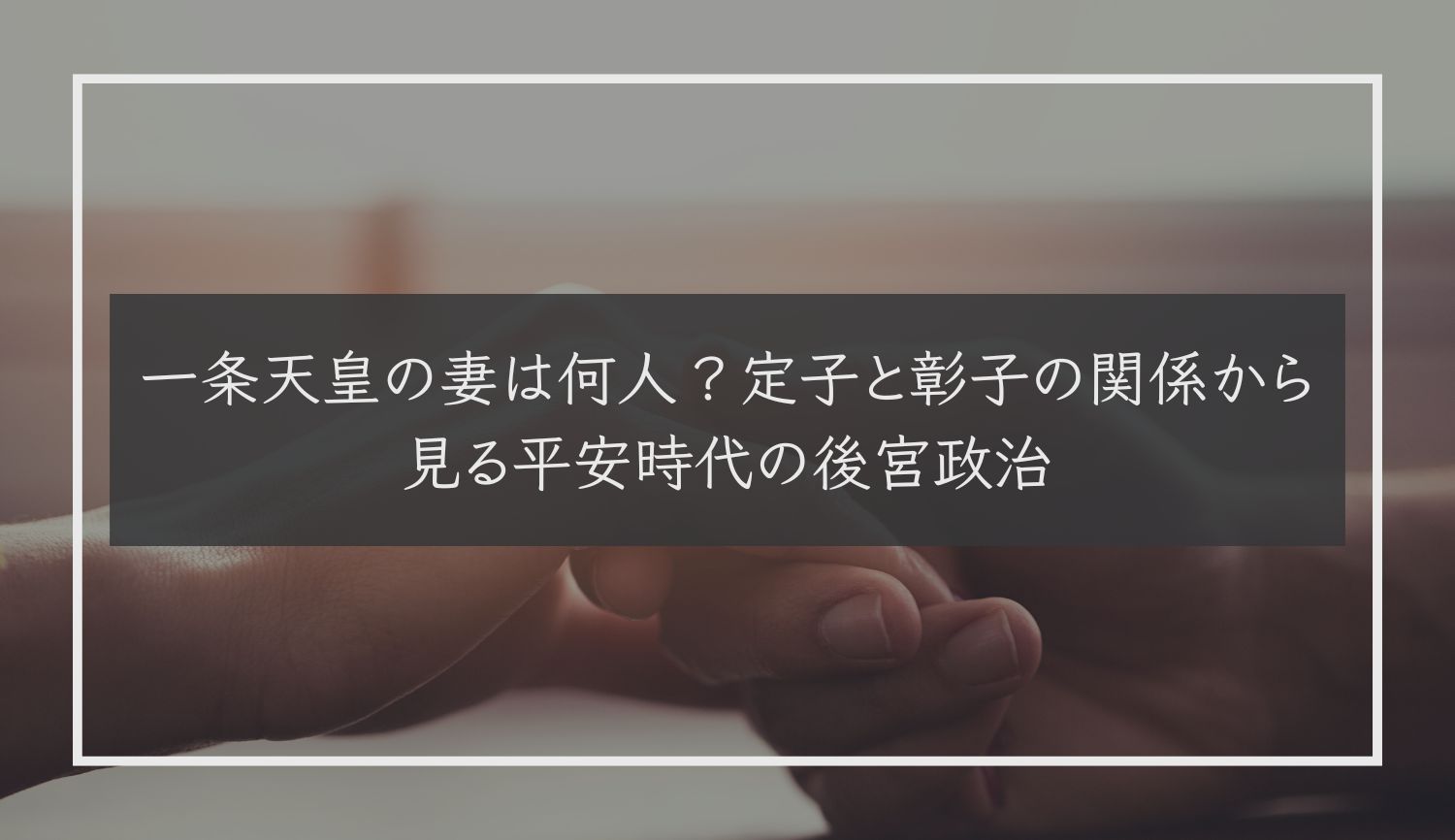平安時代中期に在位した第66代天皇・一条天皇は、「一帝二后」という前例のない状況を生み出した天皇として知られています。華やかな平安文化が花開いた時代の中心にいた一条天皇の後宮には、どのような女性たちがいたのでしょうか。また、二人の正妻・藤原定子と藤原彰子の間にはどのような関係があったのでしょう。本記事では、一条天皇の妻たちと後宮政治の実態に迫ります。
一条天皇の妻は何人?
一条天皇は980年(天元3年)に生まれ、わずか7歳で即位するという若さで天皇となりました。彼の母は藤原詮子、父は円融天皇です。一条天皇の正式な妻としては、主に以下の女性たちが記録に残っています。
- 藤原定子(ふじわらのさだこ/ていし):関白・藤原道隆の長女。最初は「中宮」を号し、のちに「皇后宮」となる。
- 藤原彰子(ふじわらのあきこ/しょうし):藤原道長の娘。「中宮」を号した。
- 藤原義子:太政大臣・藤原公季の娘。弘徽殿女御と呼ばれる。
- 藤原元子:左大臣・藤原顕光の娘。承香殿女御と呼ばれる。
- 藤原尊子:関白右大臣・藤原道兼の娘。前御匣殿女御と呼ばれる。
興味深いのは、当初は定子一人だけが一条天皇の妃でしたが、定子の父・道隆が亡くなった後、次々と他の貴族の娘も入内したことです。これは、当時の後宮の動向が貴族社会における最大の関心事であり、誰が天皇の寵愛を受け、男子を産むかが、摂関政治において極めて重要だったことを示しています。
一条天皇の正妻は誰なのか?
一条天皇の正妻を考える上で興味深いのは、二人の女性が同時に正妻の位置にいたという前例のない状況です。これは「一帝二后」と呼ばれ、日本の皇室史上でも特異な出来事でした。
藤原定子は990年(正暦元年)、数え年15歳で一条天皇に入内し、同年10月には皇后に冊立され「中宮」を号しました。これは当時7歳だった一条天皇よりも4歳年上だったことになります。
一方、藤原彰子は999年(長保元年)11月に一条天皇に入内し、翌1000年(長保2年)2月に「中宮」となりました。この時点で定子は「皇后宮」と号されるようになりました。この結果、形式上は「一帝二后」という状態が生まれたのです。
この状況は、摂関政治の中心にいた藤原道長の政治的手腕によって生み出されたもので、定子の父・道隆が亡くなった後、その弟である道長が権力を掌握し、自分の娘・彰子を皇后にする一方で、定子も皇后の地位に留めるという前代未聞の状況を作り出したのでした。
定子と彰子の関係から見る平安時代の後宮政治
定子と彰子は従姉妹の関係にありながらも、父親たちの政治的対立によって、後宮内での立場は対照的なものでした。二人の関係と周囲の動向を通じて、平安時代の後宮政治の実態が見えてきます。
定子の父・藤原道隆は藤原氏北家の嫡流として関白を務め、娘を一条天皇の中宮とすることで権力基盤を強化していました。しかし長徳元年(995年)に道隆が亡くなると、その弟・道長と定子の兄・藤原伊周が権力を争うようになります。
翌996年(長徳2年)には「長徳の変」と呼ばれる事件が起こり、伊周と弟の隆家が花山法皇を侮辱した罪で流罪となりました。この時、懐妊中だった定子は内裏を出て二条宮に移り、兄たちを匿ったとされています。兄たちが捕らえられる際、定子は発作的に自ら髪を切り、出家したと見なされました。
この事件を機に定子の立場は大きく揺らぎ、道長は天皇の生母・藤原詮子の推挙を受けて内覧となり、実権を掌握しました。彼は自分の娘・彰子を入内させ、「中宮」の称号を与えたのです。
定子と彰子の居所からも、二人の立場の違いが見て取れます。彰子は藤壺に局を持ち、これは天皇の寝所である後涼殿からもっとも近い位置にありました。一方、定子の局は登華殿もしくは梅壺だったとされ、清涼殿からはやや離れていたのです。
しかし、興味深いことに彰子は当初、一条天皇と定子の間に生まれた敦康親王を養育していました。当時彰子はわずか数え年13歳の幼さでしたが、この行動は後の政治的駆け引きの一環だったとも考えられます。
一条天皇が心から愛した人は誰なのか?
一条天皇の感情面に焦点を当てると、彼が最も深く愛したのは定子だったとする見方が強いです。定子と一条天皇は互いに深く愛し合っていたとされ、定子が出家した後も、一条天皇はさまざまな策を駆使して彼女との関係を続けようとしました。

一方で、彰子との関係については、当初はあまり良好ではなかった可能性があります。彰子が入内した際、彼女はまだ数え年12歳と幼く、一条天皇が彰子の前で自分を「おじいさん」と呼んだというエピソードが残っています。当時一条天皇はまだ20歳前後だったことを考えると、これは彰子との年齢差に対する自虐的な表現だったのでしょう。
また、興味深いことに一条天皇は定子だけでなく、藤原元子にも寵愛を示していました。元子は997年(長徳3年)に懐妊したものの、「生まれたのは水だった」という不可解な結果に終わり、その後は里に引きこもりがちになったとされています。
一条天皇の人間性を知る上で興味深いのは、彼が大変な愛猫家だったという逸話です。内裏で生まれた猫「命婦の御許」(みょうぶのおとど)のために儀式を執り行い、乳母まで付けたと伝えられています。この猫に関するエピソードは『枕草子』にも記載されており、一条天皇の優しい性格が窺えます。
まとめ:正妻が2人いたのは珍しい
一条天皇の時代に生まれた「一帝二后」の状態は、日本の皇室史上でも特異な出来事でした。これは藤原氏の権力闘争の結果生まれたものであり、摂関政治が頂点に達した証でもあります。
一条天皇と定子、彰子の三角関係は、平安文学にも大きな影響を与えました。定子に仕えた清少納言の『枕草子』、彰子に仕えた紫式部の『源氏物語』など、現代にも残る名作が生まれたのも、この複雑な後宮関係があったからこそと言えるでしょう。
興味深いのは、一条天皇が表面上は藤原道長と協調して政治を行いながらも、実際には彼の強い権力に制約されていた点です。一条天皇は敦康親王(定子の子)を皇太子にしたいと考えていたものの、道長の意向を尊重し実現しませんでした。
また、『愚管抄』には天皇崩御後、道長と彰子が天皇の遺品から「三光明ならんと欲し、重雲を覆ひて大精暗し」という手紙を発見したという記述があります。これは「道長一族の専横によって国は乱れている」という意味だと解釈され、一条天皇が道長の権力に対して内心批判的だった可能性を示唆しています。
一条天皇の後宮は、平安時代の政治と文化の縮図でした。表面上の華やかさの裏には、藤原氏を中心とした激しい権力闘争があり、そこに翻弄される形で一条天皇と彼の妃たちの人生が形作られていったのです。「一帝二后」という特異な状況は、その複雑な政治力学の象徴だったと言えるでしょう。
この時代の後宮空間は、単なる天皇の私的領域ではなく、摂関政治の中核を成す重要な政治的舞台でした。そして、その舞台で展開された人間ドラマが、日本文学史上に燦然と輝く作品群を生み出す原動力となったのです。