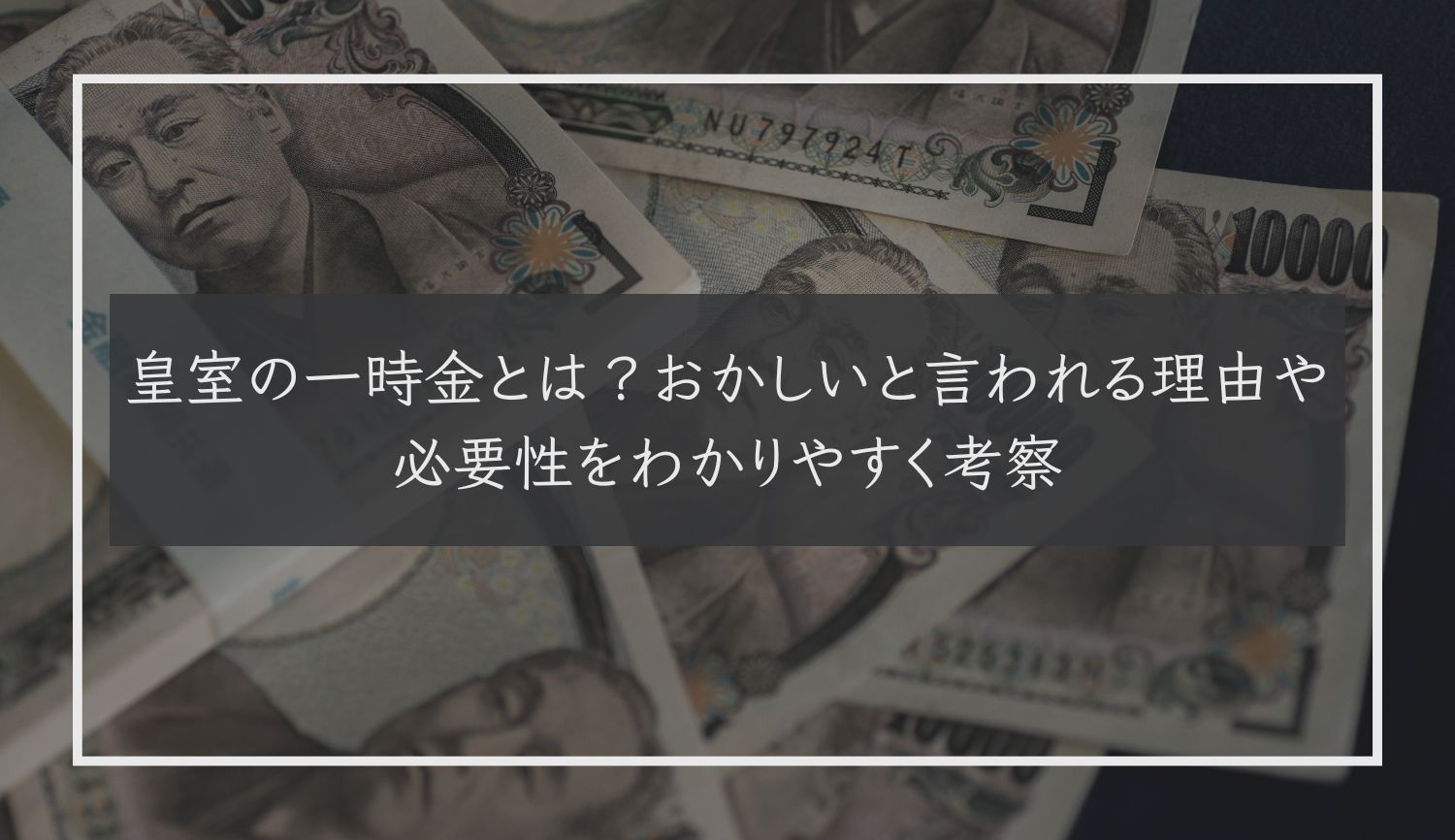皇室の制度に関する話題の中でも、女性皇族が結婚により皇籍を離れる際に支給される「一時金」については、様々な議論があります。2021年に秋篠宮家の長女・眞子さまが小室圭さんと結婚された際に辞退され、話題となった皇室の一時金制度。その仕組みや議論の背景には、皇室制度の在り方や社会が変化する中での伝統的な慣行の意義など、多くの論点が含まれています。本記事では、皇室の一時金とは何か、なぜ批判される場合があるのか、そしてその必要性について詳しく解説します。
皇室の一時金とは?
皇室の一時金とは、女性皇族が「天皇及び皇族以外の者」、つまり民間人と結婚して皇室を離れる際に支給される金銭のことです。この制度は皇室経済法に基づいており、「皇族であった者としての品位保持の資に充てる」ことを目的としています。

具体的な金額は、皇族費(皇族に支払われる生活のための諸経費)から算出されます。「独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額を限度とする」と定められており、例えば眞子さまの場合、基準となる額が1525万円だったため、一時金の限度額は1億5250万円となっていました。
実際に支給される額は、首相を議長とする「皇室経済会議」という機関で決定されます。この会議は、衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の8名で構成されており、一時金の具体的な額を認定する権限を持っています。
重要なポイントとして、この一時金は非課税で支給されるもので、過去には上皇ご夫妻の長女・黒田清子さん(旧紀宮さま)が結婚された際にも同様の金額が支給されています。
皇室の財政は、内廷費、皇族費、宮廷費の3つに分かれており、一時金は皇族費から支出されます1。皇族費は「皇族としての品位保持の資」に充てるためのもので、令和6年度(2024年度)の総額は2億6,372万円となっています。
皇室の一時金がおかしいと言われる理由
さて、皇室の一時金制度に対して「おかしい」という意見が言われるのは、どうしてなのでしょうか?
一概には言えませんが、ここでは3つの理由に焦点を当てて説明していきます。
理由1:支給額の妥当性に関する議論
皇室の一時金がおかしいと言われる第一の理由は、その支給額の妥当性についての議論です。眞子さまの例では約1億5250万円という金額が見込まれていましたが、この金額が「品位保持」という目的に対して適切なのかという点で意見が分かれます。
SNS上でも「結婚の自由を選んだ以上、それに伴う責任も果たすべき。貯金0円の結婚なんて、一般市民では、ザラです。一時金払う事は反対です」といった意見が見られました。一般的な日本人からすれば、結婚に際して国から1億円以上の支給を受けるということは想像しがたく、特権的に映る面があります。
また「女性皇族が皇族以外の男性と結婚して皇室を出る際、『一時金』として1億円以上貰えるなら、皇室に残るより遥かにいいですよね?」といった質問も見られ、制度の趣旨が正確に理解されていない場合もあります。
理由2:支給の是非が個人に左右される不安定さ
二つ目の理由は、一時金の支給が相手や状況によって左右されるべきではないという観点です。政治学者の山口二郎氏は「自由意志で結婚する代わりに一時金を受け取らないというのは奇妙な話。ルール通りに支給して、あとは自由に生きていく、誰も干渉しないというので決着をつけるべき」と述べています。
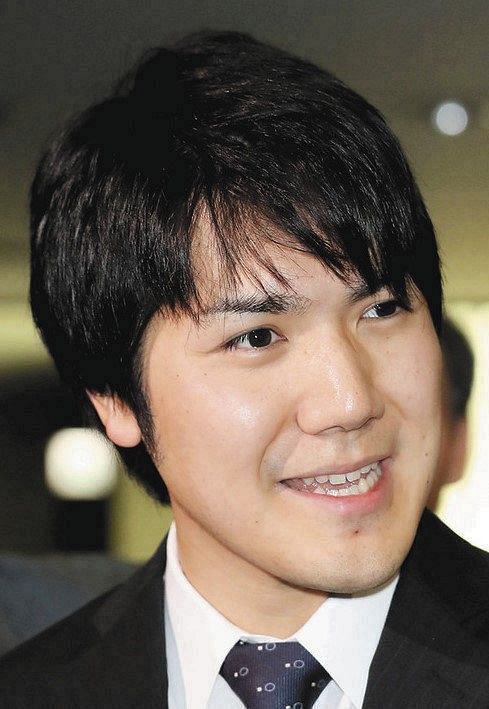
これは制度的な安定性の問題でもあります。一時金は「皇族であった者としての品位保持」という目的のために法律で定められたものであり、相手が誰であるかによって変わるべきものではないという考え方があります。作家の竹田恒泰氏も「小室さん憎しで出さなくていいというお金でもない」と指摘しています。
天皇制は制度として存在するのであり、一時金も制度的に運用されるべきで、「国民に人気のない天皇や皇族が出てきたとしても、その度に経費を上げたり下げたりすることはおかしい」という見方もあります。
理由3:一時金を「ご祝儀」と見なす誤解
三つ目の理由は、一時金を結婚の「お祝い金」や「ご祝儀」のように捉える誤解があることです。SNS上でも「国民は、眞子様に一時金が支払われるのは嫌じゃないのよ。お相手が小室圭さんだから嫌なのよ」といった意見が見られました。
しかし、一時金は結婚自体のお祝いというよりも、皇族としての立場を離れた後の「品位保持」のために支給されるものです。龍谷大学の瀬畑源准教授は「費用対効果で皇室を語ることは危険」と指摘しており、皇室の制度を単純に経済的な視点だけで評価することの問題を指摘しています。
こうした誤解により、一時金の本来の目的や意義が見失われ、「税金の無駄遣い」といった批判に結びつく場合があります。
皇族一時金の必要性
一時金が批判される一方で、その必要性を支持する声もあります。一時金はなぜ必要なのでしょうか。
まず、一時金の最も重要な目的は「元皇族としての品位保持」です。皇族という特別な立場から民間人になったとしても、元皇族として相応しい生活を送るための資金が必要だと考えられています。
特に重要なのは、元皇族の安全を確保するための警備費用です。竹田恒泰氏は一時金について「生活費に充てるお金でもなければ、不動産を買うお金でもありません。建前としては、元皇族であることの体裁を整えていただきたいということで、具体的に言えば、警備費用の前払いなのです」と説明しています。

皇室を離れると皇宮警察による警護が受けられなくなるため、私的に警備をつける必要が生じます。パパラッチや愉快犯などから身を守るためには、相当な費用がかかります。竹田氏は「10年20年、もしくはもっと多くの期間、警備をするためのお金」であり、「元皇族という”品位を保つ”ためにはまず襲われないということ」が重要だと指摘しています。
また、一時金は「退職金」的な性格も持っていると考えられます。女性皇族として生まれた方々は、幼い頃から一挙手一投足を注目され、窮屈な生活を送ってきました。職業選択も公務と兼業できる範囲に制限されており、公的な責務を果たすことが求められてきました。こうした観点から見れば、皇族としての職責に対する「退職金」として一時金を考えることも妥当という見方があります。
さらに、一般国民で計算すると一人当たり「1円少々」の負担であり、元皇族の方々の安全と品位を守るためのコストとしては適切だという意見もあります。
皇族の立場から想像してみよう
皇族、特に女性皇族の立場になって考えてみることも重要です。彼女たちは生まれながらにして皇族という特別な立場に置かれ、一般の人々とは異なる制約の中で生活しています。皇族としての生活には、常に公的な目が向けられており、プライバシーが極めて限られています。また、行動や発言にも厳しい制約があり、自由に職業を選んだり、私生活を楽しんだりすることも容易ではありません。
そんな中で、結婚により皇籍を離れるということは、これまでの生活環境や身分が大きく変わることを意味します。皇室での特権や地位を手放す一方で、新たな自由を得ることになりますが、同時に様々な課題も生じます。
例えば、これまで皇宮警察による警護を受けていた状態から、自身で安全を確保しなければならなくなります。また、元皇族として社会からの注目は続くものの、それに見合った公的支援はなくなります。
眞子さまのケースでは、結婚に至るまでの様々な批判や報道により、精神的な負担を強いられたとも言われています。そうした中での一時金辞退の決断には、国民の理解を得たいという思いがあったと考えられます。皇族女性が結婚で皇籍を離れる際の一時金は、単なる「お金」ではなく、皇族という特別な地位から一般社会へと移行する際のセーフティネットとしての役割も担っているのです。
まとめ:元皇族としての品位保持
皇室の一時金制度は、女性皇族が結婚によって皇籍を離れる際に「元皇族としての品位保持」を目的として支給されるものです。その金額は皇族費の年額の10倍を限度として、皇室経済会議で決定されます。
この制度に対しては、支給額の妥当性、制度運用の安定性、一時金の目的についての誤解など、様々な視点から議論されています。一方で、元皇族の安全確保のための警備費用や、皇族としての職責に対する「退職金」的な側面から、その必要性も指摘されています。
眞子さまが一時金を辞退されたケースは戦後初めてのことであり、皇室制度と現代社会の価値観の間にある緊張関係を示す出来事とも言えます。
皇族という特別な立場に生まれ育ち、結婚により民間人となる女性皇族の立場に思いを馳せることで、一時金の議論もより多角的な視点から捉えることができるでしょう。制度そのものの目的や意義を正確に理解した上で、現代社会における皇室の在り方について考えることが重要です。
一時金制度を単に「税金の無駄遣い」と批判したり、「結婚のお祝い金」と誤解したりするのではなく、皇室制度の一部として、その歴史的背景や現代的な意義を踏まえた議論が求められています。また、皇族の方々が直面する独特の課題や制約に対する理解を深めることも、この問題を考える上で欠かせない視点と言えるでしょう。
皇室の一時金制度は、単なる経済的な問題ではなく、日本の皇室制度や伝統、そして変化する社会との関係性を映し出す鏡でもあるのです。