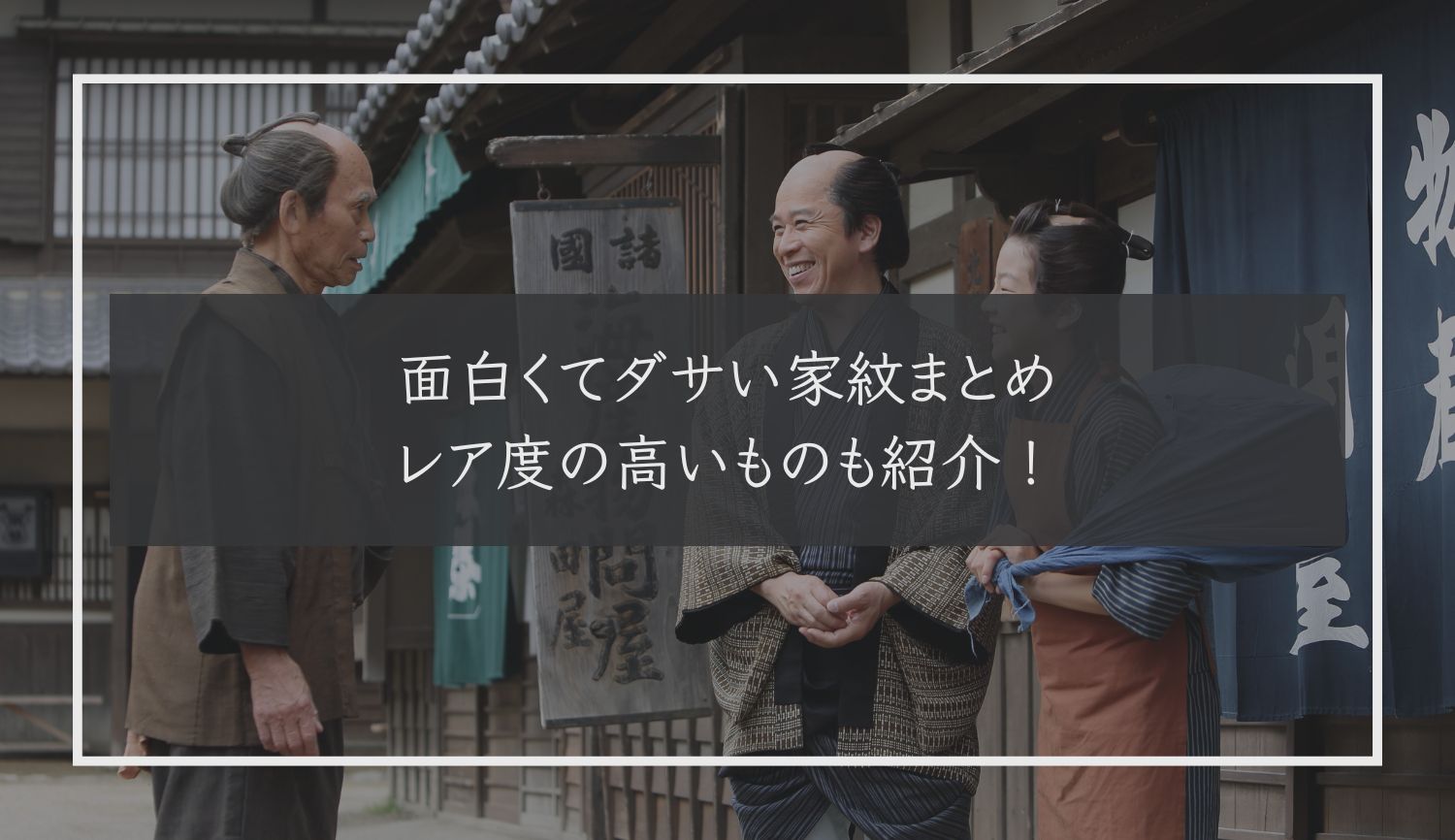家紋と言えば、厳格でかっこいい意匠をイメージする人もいるかもしれませんが、ユニークなデザインも数多く存在します。なかには、「これはダサい……」と言わざるを得ないような変な家紋もあるのです。実際のところ、面白くてダサい家紋には、どのようなものがあるのでしょうか?
この記事では、面白くてダサい家紋をまとめています。また、レア度の高い意匠についても紹介しているので、家紋に興味のある人たちは参考にしてみてください。
面白くてダサい家紋
さて、世にも珍しい面白くてダサい家紋には、どのような意匠があるのでしょうか?
ここでは、デザインがユニークな家紋を5つ紹介していきます。
その1 畠山村濃(はたけやまむらご)
第1に、「畠山村濃」です。武蔵国畠山荘(現在の埼玉県)を拠点に活躍した畠山氏の代表紋です。
源頼朝より与えられた家紋とされていますが、頼朝が家紋とした「笹龍胆(ささりんどう)」と比べると変わったデザインですよね。村濃は染め紋様のひとつです。本来的には色彩があり、その色には意味が込められていました。1種類の色を用いて濃淡のむらを出した事から「むら濃」と呼ばれました。
畠山村濃の家紋はまるで地図記号のような意匠でかっこいいとはお世辞にも言えません……。
その2 真向き大根
第2に、「真向き大根」の家紋も絶妙にダサくて面白いですよね。これは越後の戦国大名だった「柿崎景家」の家紋です。柿崎景家は、上杉謙信の重臣として活躍しました。
しかしながら、当時の日本では、大根は縁起の良い食べ物として大事にされていました。具体的には、春の七草の1つで「無病息災・平穏無事」を願う意味で家紋となりました。また、二股大根は歓喜天や大黒天の神紋でもあり、宗教的な意義で使用している家もあったようです。
食べ物が家紋として使用されるケースは稀ですから、戦場で目にして驚いた武士たちも多かったのではないでしょうか。
その3 対い鳩(むかいばと)
第3に、「対い鳩(むかいばと)」の家紋も絶妙にかっこ悪いです。源頼朝の御家人を務めたとされる高力家の家紋とされています。
そもそも戦で人を殺めるのが当たり前だった時代に、「どうして平和の象徴として知られる鳩が家紋として使われたのか?」を疑問に感じる人たちもいるかもしれません。実のところ、鳩はかつて八幡大菩薩の使いであると信じられていました。
八幡神は武神ですから、鳩は守神として勝利をもたらす存在として縁起が良かったのです。目が点で少々、拍子抜け感がありますが、軍旗としても使われていた由緒正しい家紋なのです。
その4 今川赤鳥(いまがわあかとり)
第4に、「今川赤鳥」はインベーダーのような変わった意匠です。足利の血統として有名な今川義元の家紋として知られています。
「今川赤鳥」は6本の歯を持ち、上部に紐を通す穴がある赤鳥の形が描かれています。代々旗印として使用されており、「垢取り」の当て字で櫛(くし)の歯の汚れをとる化粧道具や馬の垢をとる馬櫛だそうです。由来は「赤い鳥と軍を進めれば勝つ」との神託を受けた事から旗印にしたと言われます。
櫛を家紋に用いるなんて何ともユーモアのある発想ですよね。
その5 木下独楽(きのしたこま)
第5に、「木下独楽)きのしたこま)」の家紋も一見すると意味がわからないデザインですよね。これは木下氏(豊後国日出藩祖)の家紋です。
豊臣秀吉の正室だった高台院の兄が木下という苗字で、文様として使用されたのは比較的遅く、江戸時代以降とも言われています。独楽は玩具として中国から伝来しました。平安時代には男児の遊び道具として広く普及したそうです。
「ダサい」という感覚は主観的なものに過ぎませんが、有名な武将たちが使っていた家紋の意匠と比べると迫力に欠ける意匠ではありますよね。なお、木下独楽は独楽ではなく「高麗焼」という説もあります。たしかに、見た目ではわかりづらいですよね。
レア度の高い家紋
なお、レア度の高い家紋には、どのようなものがあるのでしょうか?
ここでは、あまり見かけたことのなさそうな3つの家紋を紹介します。
その1 日月
はじめに、レア度の高いものとして「日月(じつげつ)」という紋章があります。
これは天皇家の紋章です。天皇家の紋章といえば、「菊花」が有名ですが、日月紋は古くから即位の大典などで使用されました。その由来は「古事記」や「日本書紀」に遡ると言われています。
どちらが日でどちらが月かを判別するために、錦旗には日を金で月は銀で打ちます。その後、日は円形で月は三日月に改められています。
その2 園部額(そのべがく)
続いて、「園部額」もまたユニークであまり知られていない家紋です。園部藩小出氏が家紋としていました。額は神社、仏閣、廟などに奉納される額を意匠化したものです。神聖なものとして家紋に採用されました。その珍しさは2種類の意匠しかないことからも明らかです。
なお、もうひとつの額紋は「額に二八」です。小出氏の分家が使用していたと言われています。
その3 五瓜に卍(ごかにまんじ)
最後に、吉田松蔭が使っていた「五瓜に卍(ごかにまんじ)」もまた見る機会のない家紋です。あまりにも有名な話ですが、「吉田松陰」は長州藩の下級武士として生まれ、「松下村塾」を開き、幕末の長州をけん引した門下生を育てました。
卍(まんじ)が中央に配置され、5つの瓜が周りを囲んでいます。卍は万字と表され、漢字ではなく梵字です。元々は仏教やヒンズー教との関わりが大きく、今も仏教の記号や寺を表す標識として使用されています。卍の図形に込められた意味は「幸運到来」です。
松陰神社に行くと、この家紋がみられるので興味がある人は訪れてみてください。
多種多様な家紋がたくさんある
今現在、わかっているだけでも家紋の種類は30,000種類を超えています。そのなかには、本記事で紹介したように、有名な家紋とは異質な意匠を持つデザインも数多く見受けられます。
もちろん、どんな家紋にも使っている人たちの思いが込められている以上、本来的には「ダサい」なんて言えません。ただ、思わず笑ってしまうような面白い家紋があるのも事実です。これを機会に是非一度、調べてみてください。
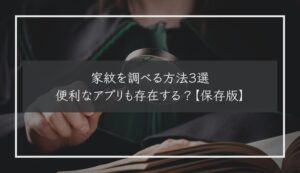
参考文献一覧
- 『決定版 知れば知るほど面白い!家紋と名字』綱本光悦 西東社
- 『面白いほどよくわかる 家紋のすべて 安達史人』日本文芸社
- 『家紋から日本の歴史をさぐる』インデックス編集部 ごま書房
- 『日本の家紋事典 由来と解説』大隈三好 金園社
- 『知識ゼロからの日本の家紋 入門』楠戸義昭 幻冬社