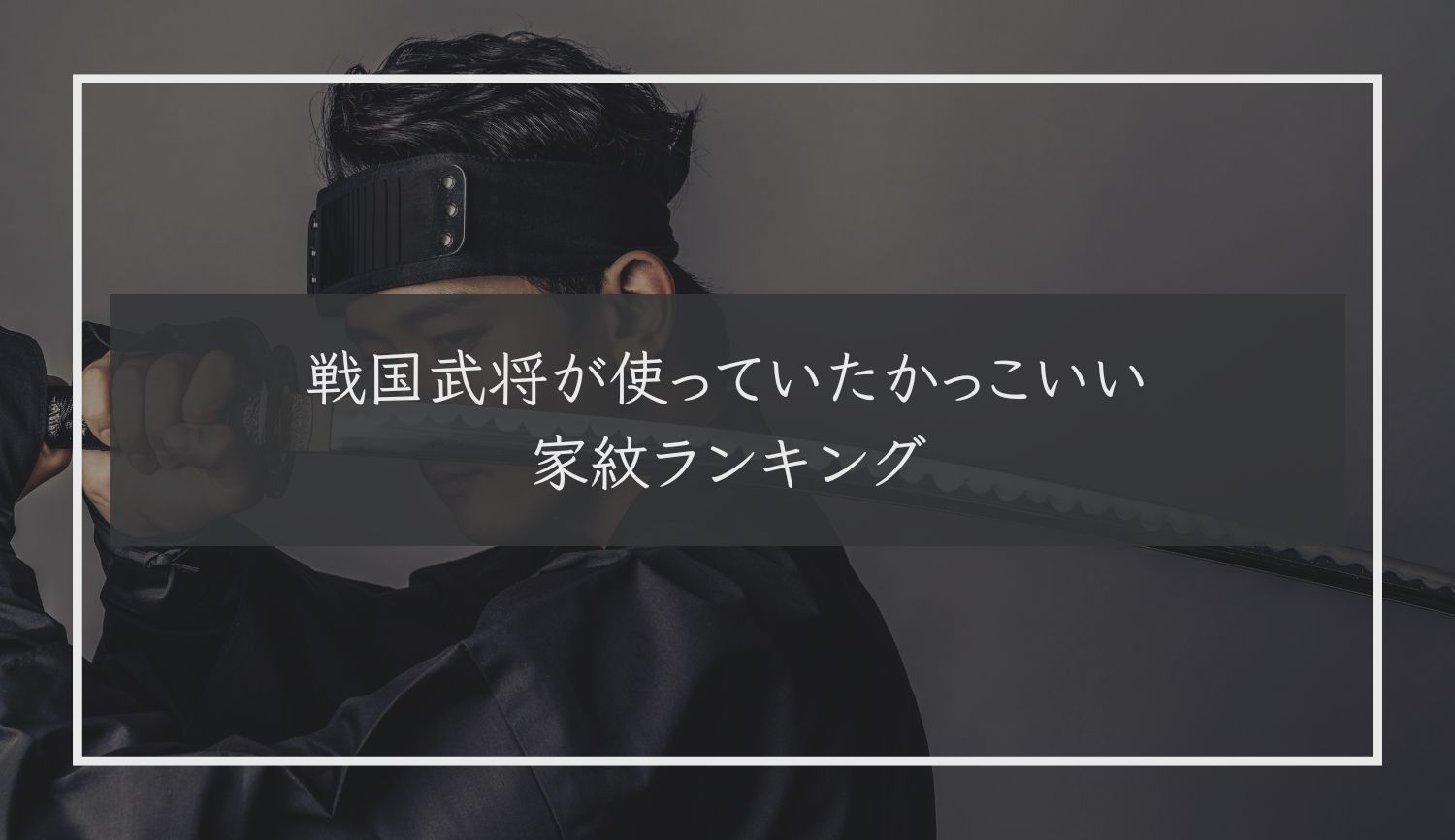日本の家紋は30,000種類以上のデザインがあると言われています。
いわゆる、歴史的人物が使用していた有名なもの以外にも特徴的な意匠が数多く存在します。なかには、思わず二度見しそうなくらい「かっこいい」家紋もあるのです。
この記事では、戦国武将が使っていたかっこいい家紋ランキングを紹介しています。日本の家紋に興味にのある人たちは参考にしてみてください。
戦国武将が使っていたかっこいい家紋ランキング
さて、Deep Japan Questでは、戦国武将が使っていた家紋の中で「かっこいい」ものを独断でランキングにしています。ここでは、10種類の意匠が素敵な家紋を紹介していきます。
10位 菊水 (きくすい)
第1に、「菊水(きくすい)」です。楠木正成の代表的な家紋です。
「菊」と言えば天皇家の家紋として有名です。菊は不老長寿の薬効があると言われており、後醍醐天皇が「正成の名が千年先まで残るように」と下賜されました。しかし、天皇家と同じ紋を持つのは恐れ多いと「水」の紋を付け加えたと言われています。
9位 大内菱(おおうちひし)
第2に、「大内菱(おおうちひし)」です。
下剋上に散った大内義隆の代表家紋です。義隆は尼子氏との戦いで後継を失ったことをキッカケに軍事を家臣に任せ、自らは京から公家や文化人を招き、山口を「西の京都」と呼ばれる文化の都としました。「花菱」を用いた人目を引く家紋です。
8位 丸に七つ片喰
第3に、「丸に七つ片喰(まるにななつかたばみ)」です。
四国全土を平定した長宗我部元親の代表家紋です。長宗我部氏は土佐の有力守護ですが、元親は「姫若子」と揶揄されるほど柔弱な若者だったそうです。しかし、その印象とは裏腹に一旦挙兵するとわずかな手勢で五倍ほどの軍勢を圧倒し敵味方を驚かせました。その後、四国統一を成し遂げます。
「片喰(かたばみ)」はどこにでもある雑草で踏まれても立ち上がることから繁殖力と子孫繁栄を願う武家に好まれた十大家紋の一つです。中央の片喰に丸く割った6つの葉が描かれ、バランスも良く美しいデザインですね。四国統一を成しても片喰を愛用する姿がかっこいい点です。
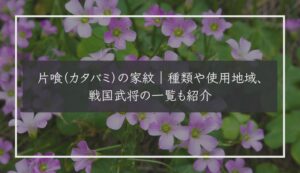
7位 三つ足烏
第4に、「三つ足烏(みつあしどり)」、別名は「八咫烏(やたがらす)」です。
独自の軍事力で信長を苦しめた鈴木孫市の代表家紋です。「三本足の烏は太陽に住む」と言われる伝説として語られる金の鳥でした。
実は、サッカー日本代表のエンブレムに記載されている烏はこの八咫烏がモチーフとなっています。太陽を象徴する八咫烏はサッカーにふさわしく、たくましさが生き生きと伝わる家紋の例とされました。
6位 福島沢瀉
第5に「福島沢瀉(ふくしまおもだか)」です。
賤ヶ岳の一番槍として秀吉に仕えた福島正則の代表家紋です。様々な功績が認められ、家康から安芸広島の大大名に任じられました。沢瀉は十大家紋の一つで、別名を「勝ち草」と呼ばれ武士に好まれた紋の一つでした。
由来は、毛利元就が沢瀉に止まったトンボを見つけ、勝ち虫と言われたトンボが勝ち草に止まって縁起がいいという事から紋にされました。戦国の武将らしい縁起を担いだ点が興味深いですね。
正則は、広島城を許可なく改築したことがキッカケで旗本まで格を下げられました。正則の人生とは裏腹に沢瀉の姿が印象的でした。
5位 三つ盛り木瓜
第6に「三つ盛り木瓜(みつもりもっこう)」です。
因縁の織田信長に翻弄された名家の朝倉義景の代表紋です。義景は当主となりながら政治や軍事を任せ、公家や文人墨客を招いて宴などを盛んに開きました。城下町に貴族文化が花開く契機を築きました。
木瓜は瓜の断面をかたどったもので、子孫繁栄を象徴する鳥の巣に似ていることから様々な武将に愛されました。織田信長の「織田瓜」の原型は、朝倉氏の木瓜紋だそうです。
4位 足利二つ引き
第7に、「足利二つ引き(あしかがふたつひき)」です。鎌倉時代を通じて新田氏をしのぐ強大な一族となった「足利尊氏(たかうじ)」の代表紋です。
足利の伝統的家紋と言えば、「二つ引き」です。
足利氏が二つ引きを使い始めた理由として、源頼朝の白旗と違いを付けるために旗に二つ線を入れたのが始まりとされています。「引両(ひきりょう)」紋の一種で、引両とは「引霊」のことで一引両は太陽を二引両は月を表しているという説があるそうです。
埼玉県立歴史と民俗博物館より抜粋
嵐山町web博物館より抜粋
シンプルなデザインですが、戦いにおいても非常に目立ちますね。遠くから見ても区別がつくのは戦いにおいて重要な点です。
3位 北条鱗
第8に「北条鱗(ほうじょううろこ)」です。
関東を手中におさめた北条氏康の代表紋です。北条氏の前家紋だった「三つ鱗」を元に平べったい二等辺三角形にしたデザインを採用しました。鱗と聞くと魚を想像しますが、蛇から来ているそうです。
ゲームが好きな人からすると、ゼルダの伝説に出てくるトライフォースとそっくりだと思った人たちもいるかもしれません。実は、すでに日本の歴史に登場している意匠なのです。
2位 抱き菊の葉に菊
第9に、「抱き菊の葉に菊(だききくのはにきく)」です。
早口言葉のような紋名ですね。明治維新を推進した西郷隆盛の代表紋です。
菊は上述しましたが、天皇家の由緒正しき紋です。明治維新の指導者として大きな功績を残した隆盛に対して明治天皇に下賜されました。「抱き」の形に配した葉の中央に菊花を置いた「抱き菊の葉」には「左右から補佐せよ」との意味が込められているそうです。
かっこいいというよりは、高貴な印象が目立ちますね。この紋を着物に描かれているだけで背筋が伸びるような印象です。
1位 組み合い角に桔梗
第10に、「組み合い角に桔梗(くみあいかくにききょう)」です。
薩長同盟の立役者となった坂本龍馬の代表家紋です、「組み合い角に桔梗」の紋は「桔梗」を中央に配置し、「組み合い角」で囲っているデザインです。
明智家の桔梗紋を紹介しましたが、桔梗は「裏切りの紋」として有名です。一説では、坂本家は土佐に落ちてきた明智秀満(明智光秀の娘婿)の子孫であると言われています。家紋を研究・愛好する人たちの間では明智光秀に繋がる系譜にロマンを感じる人たちも多いそうです。
おしゃれな家紋がたくさんある
家紋は一族を象徴するものだからこそ、掲げられるときに意匠へのこだわりは強かったと考えられます。今回、紹介したのようなかっこいいデザインの家紋はその他にもたくさんあります。これを機会に、あなたが好きな家紋の形を見つけてみるのも面白いかもしれません。
参考文献一覧
- 『決定版 知れば知るほど面白い!家紋と名字』綱本光悦 西東社
- 『面白いほどよくわかる 家紋のすべて 安達史人』日本文芸社
- 『家紋から日本の歴史をさぐる』インデックス編集部 ごま書房
- 『日本の家紋事典 由来と解説』大隈三好 金園社
- 『知識ゼロからの日本の家紋 入門』楠戸義昭 幻冬社