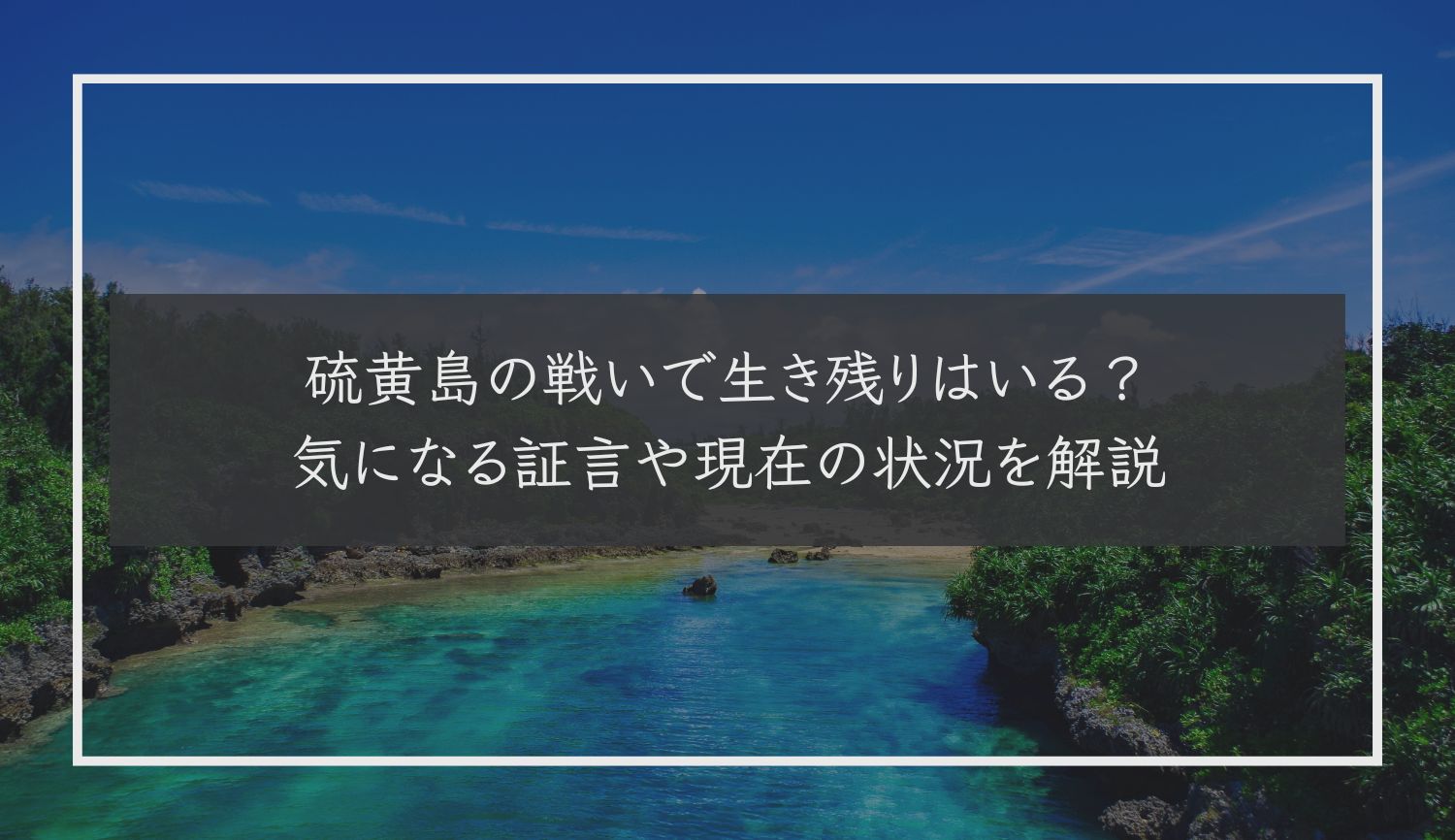硫黄島の戦いは太平洋戦争末期に行われた激戦として知られていますが、この戦いからの生還者は極めて少なく、その証言は貴重な歴史資料となっています。日本軍約2万2千人のうち生還者は約千人のみという壮絶な戦いから80年が経過した現在、証言者のほとんどが既に亡くなっています。この記事では、硫黄島の戦いの概要、生還者たちの運命、そして彼らが残した証言を独自の視点から掘り下げていきます。
硫黄島の戦いとは?
硫黄島の戦いは1945年2月19日から3月26日まで、東京都硫黄島村硫黄島(現在の東京都小笠原村)で繰り広げられた日米間の島嶼攻防戦です。東京から南に約1250キロメートル、東京とサイパン島のほぼ中間に位置するこの島は、B-29爆撃機による日本本土空襲の中継基地として米軍にとって戦略的価値があり、日本にとっては本土防衛の最前線でした。
栗林忠道陸軍中将(戦死認定後陸軍大将)を最高指揮官とする日本軍硫黄島守備隊(小笠原兵団)は、米軍の圧倒的な火力に対して全長18キロに及ぶ地下壕網を構築し、徹底した持久戦で抵抗しました。米軍は当初5日間で攻略する予定でしたが、日本軍の激しい抵抗により作戦は大幅に遅延し、最終的に40日間にわたる死闘となりました。
この戦いの特筆すべき点は、太平洋戦争において米軍が反攻に転じて以降、米軍の死傷者数(約2万5000人)が日本軍のそれを上回った唯一の地上戦闘だったことです。3月26日、栗林大将以下300名余りが最後の総攻撃を敢行し壊滅、これにより日米の組織的戦闘は終結しましたが、現在も約1万1千人の日本兵の遺骨が未収容のまま島に眠っています。
硫黄島の戦いで生き残りはいる?
硫黄島の戦いでは日本側守備隊約2万2千人のうち、生き残ったのはわずか約1千人と記録されています。では、この千人はどのような人々で、どのように生き延びたのでしょうか?

生還者の多くは、戦闘中に負傷して米軍に捕らえられた兵士、戦闘終了後も島に潜伏していた者、そして学徒兵として後方任務に就いていた若者たちでした。1941年に東条英機陸軍大臣が発令した「戦陣訓」により捕虜になることを禁じられていた日本兵にとって、生き残ることすら「不名誉」とされる風潮がありました。
西進次郎さん(享年99歳)は、米軍上陸の直前まで学徒兵として防衛任務にあたり、幸運にも生還した一人です。2023年7月6日に亡くなるまで、戦時中の島の状況について語れる数少ない証言者でした。秋草鶴次さん(2018年に90歳で死去)は、17歳の時に海軍通信兵として硫黄島に派遣され、送信所が火炎放射を受けて重傷を負いながらも奇跡的に生き延びました。
また特筆すべきは、敗戦後も約4年間硫黄島の地下壕で生活を続けた山蔭光福氏と松戸利喜夫氏の存在です。彼らは1949年1月初めに米軍に投降し、帰国しましたが、山蔭氏はその後の生活に適応できず、26歳の若さで自ら命を絶ってしまいました。
2025年現在、硫黄島の戦いの生存者はほぼ全員が鬼籍に入っていると考えられます。彼らの高齢化と死去により、直接体験を語れる人々はもはやほとんど存在せず、記録された証言が貴重な歴史資料となっています。
硫黄島の戦いに関する証言
それでは、硫黄島の戦いに関して、どのような証言が現在に至るまで残っているのでしょうか?
その1:西進次郎さんの証言
西進次郎さんは1923年生まれで、2023年7月に99歳で亡くなりました。亡くなる数ヶ月前の1〜2月に行われたリモート形式や電話でのインタビューは、合計10時間に及ぶ最後のロング・インタビューとなりました。
西さんは学徒兵として硫黄島に送られ、米軍上陸の直前まで島にいました。彼の証言の特徴は、一般兵ではなく学徒兵という立場からの観察にあります。学徒兵たちは主に後方支援に従事していたため、前線での戦闘とは異なる視点で島の状況を見ていました。
特に興味深いのは、西さんが語った米軍上陸前の島の準備態勢や、栗林忠道中将の下で行われた防衛体制の構築過程です。これらは公式記録にはあまり残されていない、兵士目線での貴重な情報でした。
その2:秋草鶴次さんの証言
足利市島田町出身の秋草鶴次さんは、17歳で海軍通信兵として硫黄島に派遣され、島の中心部の玉名山送信所で任務に就いていました。
秋草さんの証言によれば、「爆撃を受けて舞い上がる土砂に混ざって飛び散る人の頭や手足、肉片。『おっかさーん』。いまわの際の叫びが、方々に波紋のように広がっていった」という戦場の残酷な光景が生々しく描写されています。「視界を埋め尽くすほどに飛び交う銃弾。1分ごとに3人、部隊が1メートル進むたびに1人が死んでいく」という証言からは、想像を絶する激戦の様子がうかがえます。
3月に送信所が火炎放射で攻撃された際、秋草さんは重傷を負いながらも本部への報告を試みましたが、艦砲射撃により右手の指3本を失い、左足に貫通傷を負いました。その後、地下壕に残された彼は「暑さがむせかえり、排せつ物や遺体の腐乱臭が充満」する環境で、「体に付いたノミやシラミ、傷口にわいたウジさえ口にした」という極限状態を経験しました。
最終的に意識を失った秋草さんがグアム捕虜収容所のベッドで目覚めたのは、負傷から3カ月後のことでした。
その3:田川正一郎さんの証言
長崎県出身の田川正一郎さんの証言は、戦場だけでなく捕虜となった後の経験も含む点で貴重です。1945年4月に硫黄島からグアムの野戦病院に移された田川さんは、同じ長崎県出身の林田毅さんと出会います。林田さんは自決を図りましたが生き延び、両足を失っていました。
その後ハワイの米軍病院に移送された彼らは、そこで日本の敗戦と、広島・長崎への原爆投下を知ります。田川さんは「日本はアメリカの属国になるのか」と思い、新聞で見た浦上天主堂の写真から家族の安否を心配しましたが、復員後になって初めて、二人の妹や叔父叔母ら計七人の親族が原爆で亡くなっていたことを知りました。
敗戦を知った時、田川さんは「これで日本も終わりだ」と感じ、死んでいった仲間の顔を思い浮かべて「申し訳ない」と涙を流しました。この証言は、戦場での体験と本土での悲劇が二重写しになった、硫黄島の生還者ならではの視点を示しています。
硫黄島から帰ってきた人の現在
硫黄島の生還者たちは、戦後どのような人生を送ったのでしょうか。多くは深い心の傷を負いながら、それぞれの道を歩みました。
前述の山蔭光福氏は、敗戦後約4年間硫黄島に残り、1949年1月に帰国しました。しかし、岩手県出身の彼は定職を得られず、警察予備隊への志願も不採用となりました。米国人ジャーナリストのジョン・リッチ氏とのつながりから島での4年間の日記を取りに硫黄島に戻ったものの、1951年5月、26歳の若さで摺鉢山山頂から投身自殺しています。
戦争の恐怖体験から逃れられず、社会に適応できなかった山蔭氏の悲劇は、戦争の「見えない犠牲者」の代表例と言えるでしょう。
一方、秋草鶴次さんは戦後、執筆や講演活動を通じて自らの体験を語り継ぎました。「自分はなぜ生かされたのか」という問いを持ち続け、戦友たちの最期の叫び「おっかさーん」の次に続く言葉を「必ず平和が来ると信じて戦った。だから、自分の分も幸せに生きてくれ」と解釈していました。
しかし、秋草さんの長男・茂之さんによれば、父は自宅では自分から戦争の話をすることはほとんどなかったといいます。息子が父の戦傷を知ったのは、小学3年生の頃に風呂場で偶然見かけたときだけでした。家族に対しては多くを語らず、外部向けに語り部として活動するという二面性は、多くの戦争体験者に共通する特徴かもしれません。
硫黄島での日本軍は恐ろしかった
硫黄島の戦いで特筆すべきは、栗林忠道中将が実施した新たな戦略です。従来の「水際撃滅」戦術を放棄し、地下壕網を駆使した持久戦で米軍に損害を与える作戦を展開しました。
栗林は1944年9月19日の「小笠原兵団硫黄島戦闘計画」で、安易な「バンザイ突撃」を禁じ、持久戦の重要性を強調しました。地下壕や陣地の造成を進め、実戦訓練を重ねた結果、米軍の艦砲射撃や空襲に対しても大きな損害を受けることなく迎え撃つことができました。
「私が島に着いたころ、1日4回の空襲がありました。現地の兵士たちは、それを『定期便』と呼んでいました」という証言は、日常的な空襲に慣れた兵士たちの心理状態を示しています。
島には電波探信儀(レーダー)が設置され、爆撃機の接近を監視していました。「見張り所の兵士は『180度方向! 敵編隊100キロ近づく!』などとメガホンで周知する」システムがあり、20キロに近づくとサイレンが鳴り、兵士たちは防空壕に避難しました。
しかし、この徹底した持久戦は日本兵にとって過酷な環境での任務を意味しました。地下壕での生活は「暑さがむせかえり、排せつ物や遺体の腐乱臭が充満」する劣悪なものでした。さらに資源が枯渇するにつれ、「生きるために同じ日本軍兵士の間で食べ物を盗んだり、盗まれたりすることがあった」という状況も発生しました。
最も悲惨なのは、「最期の時が近付いている戦友が水を求めても、あげる者はいなかった。重傷者がうめき声をあげると、首を絞めて死なせてしまう例もあった」という証言です。これは米軍に居場所を知られるのを防ぐためでしたが、同胞への非人道的行為を強いられた兵士たちの心の傷は計り知れません。こうした極限状態の中で、日本軍は奇襲をかけるゲリラ戦を展開し、米軍に予想外の大きな損害を与えました。それは確かに軍事的には「成功」でしたが、兵士個人にとっては言葉に表せない苦痛の日々だったのです。
まとめ:遠い歴史になる前に
硫黄島の戦いから80年が経過した今、この戦いの記憶は生存者の証言とともに薄れつつあります。2023年に西進次郎さんが99歳で亡くなったように、直接体験を語れる人々はほぼ存在しなくなりました。
この戦いの最大の悲劇は、日本軍約2万2千人のうち約1万1千人の遺骨が今も未収容であることです。これは、戦争が単なる「過去の出来事」ではなく、現在も続く問題であることを示しています。遺骨収集活動は続けられていますが、硫黄島の火山性地形と戦闘の激しさから、完全な収集は極めて困難です。
生還者たちの戦後の人生からは、戦争のトラウマが生涯続くことを教えられます。山蔭光福氏の自殺、秋草鶴次さんの語り部活動と家庭での沈黙、そして多くの兵士が抱え続けたPTSDなど、戦争の傷跡は深く、長く残りました。
「戦争は何も生まない」という秋草さんの言葉は、実体験に基づく重い警告です。硫黄島の激戦が示すのは、どれほど勇敢に戦おうとも、最終的には多くの若者の命が失われるだけだという冷厳な事実です。歴史が遠い過去になる前に、私たちはこれらの証言に耳を傾け、記録し、次世代に伝える責任があります。それは単なる歴史継承ではなく、平和への誓いでもあるのです。
日米両国にとって深い傷跡を残した硫黄島の戦いは、戦争の無意味さを教える最も雄弁な事例の一つです。生存者の証言がほぼ聞けなくなった今だからこそ、彼らが残した言葉を大切に保存し、その意味を深く考え続けなければなりません。