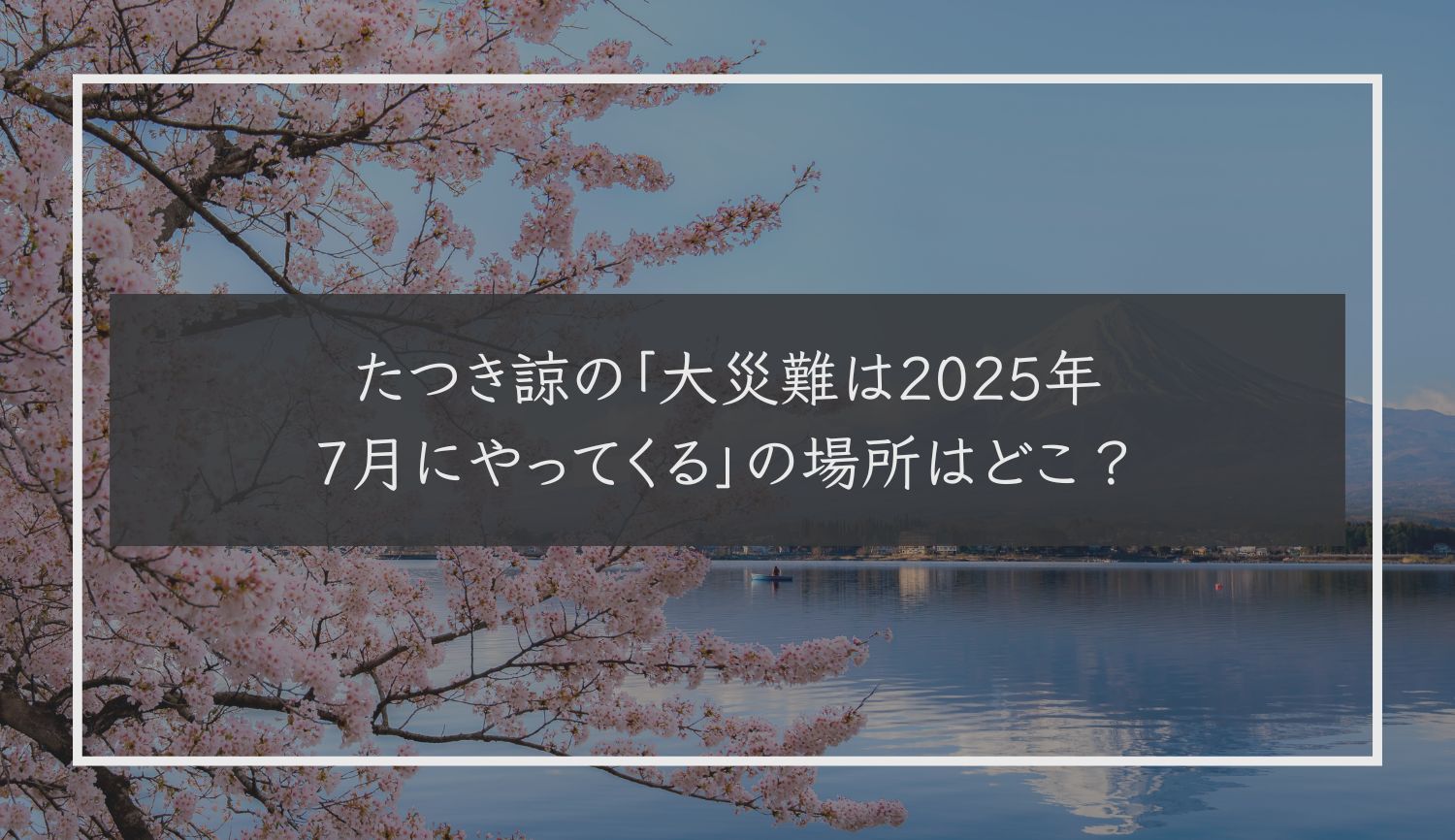2021年に出版された『私が見た未来 完全版』で「2025年7月に大災難が来る」と予言し、社会現象となった漫画家・たつき諒氏の予言について、その詳細や信憑性を深掘りします。東日本大震災を予言したとされる彼女の新たな警告は、具体的にどこで何が起こるとしているのでしょうか。科学的見地と予知夢の関係性、そして私たちがどう向き合うべきかを考察します。
たつき諒の経歴
たつき諒(竜樹諒)は1954年12月2日、神奈川県に生まれました。現在70歳の女性漫画家です。彼女の人生は17歳の時に遭った交通事故が大きな転機となりました。この経験から「家でできて、生きた証を残せ、顔を出さずに済む仕事」として漫画家を志すことになったのです。
最初は白泉社の『花とゆめ』での掲載が決まっていましたが、秋田書店の編集者にスカウトされ、1975年6月6日発売の『月刊プリンセス 1975年7月号』に掲載された読み切り『郷ひろみ物語』で20歳にして漫画家デビューを果たしました。その後『人形物語 ドールストーリー』をはじめ多数の作品を発表し、1982年には公式ファンクラブが発足、会報誌『クラッシュ』を創刊しています。
特筆すべきは、彼女が1978年頃から睡眠中の夢の内容を記録し始め、1985年からは『夢の記録』と題した夢日記を絵と文章で記述し続けてきたことです。この習慣が後の「予言漫画」へと繋がることになります。
1990年代には主に怪談やミステリーなどの作品を手がけるようになり、1998年9月に作品『白い手』を発表した後、「充電期間」を名目に休業。1999年に44歳で漫画家を一旦引退しました1。
その引退の年に出版された短編集『私が見た未来』(朝日ソノラマ)の表紙に「大災害は2011年3月」という一文があったことから、2011年3月11日の東日本大震災発生時に「この大震災を予言していた」として注目を集めることになります。絶版となっていたこの本は中古市場で10万円以上の値が付き、一時は50万円にまで高騰したといわれています。
2021年には興味深い事件が起きました。「たつき諒」を名乗る成り済まし犯が現れ、週刊誌『FRIDAY』や月刊誌『ムー』にインタビュー記事を掲載させる騒動が発生。さらに飛鳥新社から『私が見た未来』の復刻版を出版すべく画策していました。
これに対し本人が出版社と連絡を取り、企画を白紙に戻した上で、彼女自身の承認のもと予言の解説などを加えた『私が見た未来 完全版』を2021年10月に発刊しました。この本は爆発的な人気を博し、80万部以上を売り上げる大ベストセラーとなりました。2022年3月には67歳にして新たな漫画単行本を発刊し、過去の絶版作品のほか書き下ろし漫画も収録され、引退から約22年を経て作家活動を再開しました。
「大災難は2025年7月にやってくる」の場所はどこ?
2021年に出版された『私が見た未来 完全版』で、たつき諒は新たな予知夢として「2025年7月に大災難が来る」と警告しています。この予言について、具体的にはどのような内容なのでしょうか。
たつき諒によれば、『私が見た未来 完全版』の締切前の2021年7月に見た夢の中で、映画のスクリーンのようなところに「本当の大災難は2025年7月にやってくる」という黒い文字が表示されたそうです。さらに彼女は、震源地らしき海底がボコンと盛り上がる様子も夢の中で目撃しました。この時、彼女は「昔マンガに描いた夏の津波の夢は、実は東日本大震災ではなくこのことなのかな」と感じたといいます。
特筆すべきは、たつき諒が予言の中で具体的な日時まで言及していることです。彼女は「2025年7月5日4時18分」という時刻と分数まで特定しています。
場所についても、「ハワイの西側で発生した二匹の竜」が西へ進み、フィリピンと日本の中間でぶつかって巨大な津波となると描写しています。この津波は南海トラフの想定を遥かに超えるような大災害となり、日本列島の南側半分に大きなダメージを与えると予測されています。
メルマガ『施術家・吉田正幸の「ストレス・スルー術」』によれば、たつき諒の予言から読み取れる内容は以下のように要約されています:
- 海底破裂と大津波:南海トラフの南側にあるフィリピン海で海底がボコンと破裂し、東日本大震災の3倍以上の高さの津波が太平洋周辺の国に押し寄せる
- 陸地の変形:津波の影響で陸が押されて盛り上がり、日本とフィリピン、台湾が地続きになる可能性
- 火山噴火:南海トラフの南側にある火山が噴火する可能性
- 気候への影響:海底破裂や火山噴火によって気候にも影響が及ぶ
- 人類への影響:この大災難は人類に大きな影響を与える2
興味深いことに、たつき諒の予言する地域は、政府が警戒している南海トラフ地震の想定域と重なる部分があります。内閣府の「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」が計算した被害想定によれば、南海トラフ巨大地震では最大で建物被害が約209万棟、死者は最大23万人に達する可能性があるとされています。
たつき諒の予言は的中しているのか?
たつき諒の予言が注目される最大の理由は、1999年に出版した『私が見た未来』の表紙に「大災害は2011年3月」と記載し、実際に2011年3月11日に東日本大震災が発生したという「的中」があったからです。この偶然とも思える一致が、彼女の新たな予言にも信憑性を持たせる大きな要因となっています。
しかし、この「的中」については慎重に検証する必要があります。『私が見た未来』の表紙には6枚の「夢日記・夢の記録」が描かれており、そのうちの1枚に「大災害は2011年3月」という記述があったにすぎません。重要なのは、この夢に関する記述は漫画本編には一切登場しないという点です。また、他の5枚の記述についても「夢が的中した予言は特に見当たらない」と指摘されています。
一方で、たつき諒の予言する地域が科学的にも危険視されていることは事実です。政府の発表によれば、南海トラフ巨大地震の今後30年以内の発生確率は70~80%と非常に高く、元京都大学長で地震学の第一人者である尾池和夫氏も、富士山の噴火がいつ起きてもおかしくないと指摘しています。

石破茂首相の下で2026年度に創設を目指す防災庁も、激甚化する風水害や巨大地震の発生リスクの高まりを念頭に置いています。防災庁は災害時に行政の各組織や民間の企業・団体を横断的に束ねて政府の防災対応の司令塔となる役割を期待されており、避難生活の環境改善や防災に関するデジタルトランスフォーメーションの推進にも取り組む予定です。
デジタル庁も防災DXの取り組みを進めており、住民支援のための防災アプリ開発・利活用の促進、データ連携基盤の構築などを推進しています。
つまり、たつき諒の予言する災害の可能性そのものは、科学的な見地からも完全に否定できるものではないのです。ただし、「2025年7月5日4時18分」という具体的な日時については、科学的根拠に基づくものではなく、あくまでも彼女の夢に基づく予言であることは明記しておく必要があります。
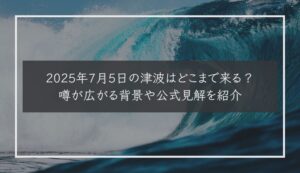
予言を盲信するのは危険
たつき諒の予言は多くの人々の関心を集め、中には極端な行動に出る人も現れています。日刊ゲンダイの記事によれば、「北海道と八ケ岳以外は沈没する」といったさらに極端な解釈が広まり、「日本を離れる準備をしている」「八ケ岳に拠点を設けた」という人もいるとされています。
このような過剰反応は危険です。信州大学教授の菊池聡氏は、2025年7月の隕石衝突説について「何年ぶり何度目の終末ですか。一度でも終末が来たら次はないはずでしょう」と冷静に指摘しています。実際、過去には2012年のマヤ暦に基づく終末予言など、多くの終末予測が外れてきました。
宇宙航空研究開発機構(JAXA)名誉教授の的川泰宣氏も「衝突はないでしょう。さまざまな機関が監視していますから、本当だったら研究者が騒ぎます」と隕石衝突説を一笑に付しています。
占星術師の水晶玉子氏も「この時期は決してよい運気の時ではない」としながらも、「極端なことも起こりやすい『七曜陵逼』ですので、警戒した方がいいことは間違いありません。せっかくなら日本は災害の多い国ですし、備蓄であったり、家族との連絡手段や集合場所の確認などリスクマネジメントをしておくのはよい時」と冷静な対応を呼びかけています。
たつき諒自身も、予言を過度に恐れるよりも備えることの大切さを強調しています。「今後起こるかもしれない災害への警鐘を鳴らすことによって、被害を最小限に抑えることができる」「皆さんには、自分の住んでいる地域の地形の特徴や過去の災害を自分で調べた上で、しっかり備えてほしい」と述べています。
予言を盲信することなく、科学的な視点と現実的な防災対策のバランスを取ることが重要です。
まとめ:備えることに意味はある
たつき諒の「2025年7月に大災難が来る」という予言については、その真偽を現時点で判断することはできません。しかし、日本が地震・津波・火山噴火などの自然災害リスクの高い国であることは紛れもない事実です。
政府の想定によれば、南海トラフ巨大地震は今後30年以内に発生する確率が70~80%と非常に高く、被害想定では最大で建物被害約209万棟、死者最大23万人という甚大な被害が予測されています。
たつき諒は「自宅周辺のハザードマップを確認したところ、江戸中期の大津波を軽視していて、想定が甘いことがわかった」と指摘しています。彼女は「いざという時『やっておいてよかった』と言うことはあっても、『やりすぎだ』と苦言を呈する人はいない」と述べ、備えの重要性を強調しています。
実際、政府も防災対策を強化しています。2026年度に創設予定の防災庁は「本気の事前防災」のための組織として位置づけられており、デジタル庁も防災分野のデータ連携基盤の構築や防災アプリの開発・利活用促進に取り組んでいます。
予言の真偽にかかわらず、私たちができることは冷静に備えることです。具体的には:
- 自宅周辺のハザードマップを確認し、避難経路や避難場所を把握する
- 非常食や飲料水など、最低3日分(できれば1週間分)の備蓄をする
- 家族との連絡手段や集合場所をあらかじめ決めておく
- 家具の固定など、自宅の安全対策を行う
- 公的機関からの信頼できる情報を常に確認する習慣をつける
特定の予言を過度に恐れるよりも、科学的な知見に基づいた実践的な防災対策を講じることこそが、私たちと大切な人の命を守ることにつながります。たつき諒の予言が的中するかどうかは定かではありませんが、備えることに意味があることは間違いないのです。
「備えあれば憂いなし」とはまさにこのような状況のためにある言葉ではないでしょうか。2025年7月が近づくにつれて不安が高まるかもしれませんが、冷静に、そして着実に防災対策を進めていくことが最も賢明な選択と言えるでしょう。