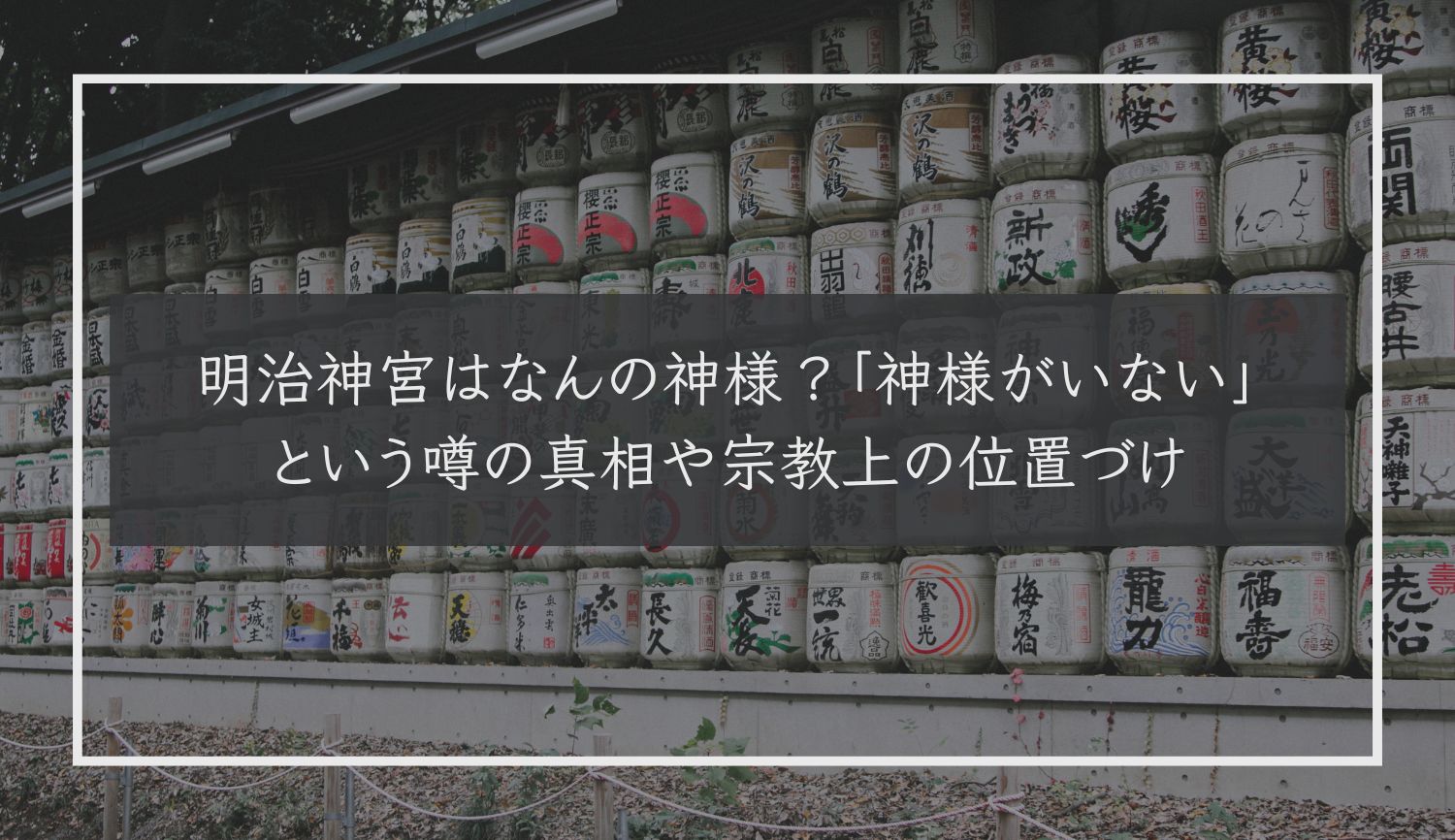東京の中心地に広がる鬱蒼とした森の中に鎮座する明治神宮。初詣では毎年日本一の参拝者数を誇り、外国人観光客にも人気のスポットです。しかしながら、日本有数の明治神宮は神社であるにもかかわらず、「神様がいない」という噂を聞いたことはありませんか?
今回は明治神宮の祭神や宗教的位置づけについて一般には知られていない視点から深掘りしていきます。
明治神宮の概要
明治神宮は東京都渋谷区に位置する神社で、1920年(大正9年)11月1日に創建されました。約70ヘクタール(約22万坪)という広大な敷地を持ち、その多くが深い森に覆われています。
この森は「永遠の杜」と呼ばれ、完全な人工林であるという事実に多くの人が驚きます。神宮創建時、この場所はほとんどが荒れ地でしたが、全国から集められた約10万本の樹木が植えられ、延べ11万人もの青年団ボランティアによって植林されました。
特筆すべきは、この森が100年後の自然な成長を見越して科学的に設計されたという点です。北は樺太(サハリン)から南は台湾まで、当時の日本の各地から献木が集まりました。その結果、今では都会の中心に自然の森が存在するかのような錯覚を覚えるほどの豊かな緑地が広がっています。
境内には8基の鳥居があり、南参道と北参道の出会い口にある第二鳥居は、木製では日本一の大きさを誇ります。柱の直径1.2メートル、高さ12メートル、重さ13トンという巨大な鳥居は、樹齢1500年を超える巨木から作られたものです。
明治神宮はなんの神様?
明治神宮には明確な神様がいます。祭神は明治天皇と昭憲皇太后の二柱です。空想上の神とは違って、歴史上存在していた人を祀っているのが特徴的です。
明治天皇(1852-1912)は、日本が封建制度から近代国家へと移行する明治時代を象徴する存在でした。大日本帝国憲法の制定をはじめ、外交改革や教育制度の整備を進め、日本を西洋列強と肩を並べる近代国家へと導いた人物として歴史に名を残しています。
一方、昭憲皇太后(1849-1914)は明治天皇の皇后で、福祉活動や女子教育の向上に尽力しました。日本の赤十字運動を支援し、当時の女性たちに学ぶ機会を広げるなど、社会事業に大きな功績を残しています。明治神宮の創建が内定した当初は明治天皇一柱のみを祀る予定でしたが、その後、神社創建前に崩御した昭憲皇太后も合祀され、合計二柱が鎮座することとなりました。
興味深いのは、明治神宮では社殿や参道だけでなく、境内全体、特に森そのものが神聖視されている点です。日本の神社の本質は建物ではなく、それを包む森にあるという考え方が表れています。万葉集には「神社」と表記して「もり」と訓んだ例があり、元々「もり」だったところに神社の社殿が造られたという歴史的背景があります。
神様がいないという噂の真相
なお、「明治神宮には神様がいない」という噂はなぜ広まったのでしょうか。この噂には複数の要因があります。
第一に、明治神宮が祀るのは神話上の神々ではなく、実在した歴史上の人物だという点があります。多くの神社が天照大神やスサノオノミコトのような神話的存在を祀るのに対し、明治神宮は明治時代に生きた実在の人物を神格化している点で特殊です。この点が「神様がいない」と言われる理由の一つとなっています。
第二に、明治神宮のおみくじは他の神社とは異なり、「大御心(おおみこころ)」と呼ばれるもので、通常のおみくじにある大吉や凶などの吉凶の記載がありません。代わりに、明治天皇と昭憲皇太后が詠んだ和歌が15首ずつ、計30首選ばれており、その歌の意味が記されているだけです。この独特なおみくじの形式が「明治神宮には神様がいない」という印象を与える一因となっています。しかし実際には、これは明治神宮ならではの形式であり、御祭神の思いを直接伝える方法として考案されたものです。
日本の仏教文化では、亡くなった人は49日間(四十九日法要まで)は「霊」としてこの世とあの世の間を行き来し、四十九日法要を経て「仏様」になるという考え方があります。
そのため、四十九日法要前に渡す香典・お供物には「御霊前」という表書きを用い、法要以降は「御仏前」を使います。しかし神道では、人が亡くなると子孫を守護する「神」となるという考え方があり、この違いも明治神宮に対する誤解を生む原因となっています。
神道的な考え方からすれば、明治天皇は亡くなった後、子孫や国民を守護する神となったのです。そして実際に明治神宮では、明治天皇と昭憲皇太后が神として祀られており、特定の功徳を持つ存在として多くの人々から信仰されています。
明治神宮は宗教的にどういう位置づけなのか?
明治神宮の宗教的位置づけを理解するためには、まず神社の格式について知る必要があります。
明治神宮の旧社格は「官幣大社」で、さらに「勅祭社」でもありました。「官幣大社」とは、明治時代から第二次世界大戦終了までの間に定められた神社の格付けで、国家から最も手厚い保護を受ける神社を意味します。「勅祭社」は天皇の命により祭祀が行われる神社を指します。
また、「神宮」という称号は、天皇を祀ることから与えられました。創建時には「東京神宮」とする案も出されましたが、元号・時代としての「明治」も加味して「明治神宮」となったという経緯があります。
明治神宮の創建背景には、明治天皇の崩御後、国民の天皇に対する尊崇の念を形にするという目的がありました。当初は銅像や記念碑、美術館など、明治天皇を「記念」するための施設が多数提案されましたが、最終的に「神社」という形態が選ばれました。
これは単なる記念施設ではなく、国民と天皇との関係性を神道における「崇敬」の概念と結びつけたものと見なされたからです。明治神宮は、日本の近代化における明治天皇の功績を称えるとともに、国民統合の象徴として機能することが期待されていました。
第二次世界大戦後、神社と国家の結びつきは解消されましたが、明治神宮は現在も日本を代表する神社の一つとして、多くの参拝者を集めています。特に初詣では毎年、国内外から多くの観光客が集まり、例年全国1位の参拝者数を記録しています。明治神宮には、主殿だけでなく、厄除・七五三などの祈願を行う神楽殿、明治時代の宮廷文化に関する展示を行う明治神宮ミュージアム、武道場「至誠館」、神道文化の国際的な発信を行う明治神宮国際神道文化研究所なども設けられており、単なる宗教施設としてだけでなく、文化的・教育的な役割も担っています。
ここでの神とは何のこと?
明治神宮の神様について考えるとき、そもそも神道における「神」とは何かを考える必要があります。
神道では「八百万(やおよろず)の神」という言葉があるように、自然の中のあらゆるものに神が宿ると考えられています。山や川、岩や木など自然物はもちろん、優れた技術や芸術、そして偉大な功績を残した人物も神として祀られることがあります。
明治神宮に祀られている明治天皇と昭憲皇太后も、その功績から神として崇められるようになった例です。これは西洋の一神教における「神」の概念とは大きく異なります。
神道においては、亡くなった人間が神となる「人神(ひとがみ)」の信仰があります。特に優れた功績を残した人物は死後に神格化され、崇敬の対象となります。明治天皇は日本の近代化に大きな役割を果たしたことから、崩御後に神として祀られるようになりました。興味深いのは、明治神宮の祭神となった明治天皇は、人間の感覚を忘れていない神様だと言われていることです。伊勢神宮から神々が来て指導したという話もあり、創建と同時に立派な神様になったとされています。
まとめ:人物が神として祀られている
明治神宮は確かに通常の神社とは異なる特徴を持っていますが、「神様がいない」というのは誤解です。明治天皇と昭憲皇太后という実在した人物が神として祀られており、日本の宗教観の中では立派な神様です。神道において天皇や優れた人物が神格化されるのは珍しいことではなく、歴史上の人物を神として崇める「人神信仰」は日本の宗教文化の一部です。明治神宮の「大御心」という独特のおみくじも、このような背景から生まれたものと理解できます。
明治神宮を訪れる際には、単に参拝するだけでなく、その歴史的背景や宗教的意義を知ることで、より深い体験ができるでしょう。都会の中心にある広大な森に囲まれた静謐な空間で、日本の近代化を導いた人物への敬意を表すとともに、自然と歴史の調和を感じてみてください。
訪問時に見逃せないのは「清正井」や「夫婦楠」などのパワースポット、四季折々の自然を楽しめる「明治神宮御苑」、そして何より参道を歩きながら感じる静けさです。また、神社特有の参拝方法(二拝二拍手一拝)や鳥居をくぐる際の作法など、日本の伝統的な作法を体験してみるのもおすすめです。
明治神宮は単なる観光地ではなく、日本の歴史と文化、そして信仰の形を今に伝える貴重な場所です。その深い意味を理解して訪れれば、より充実した体験ができることでしょう。