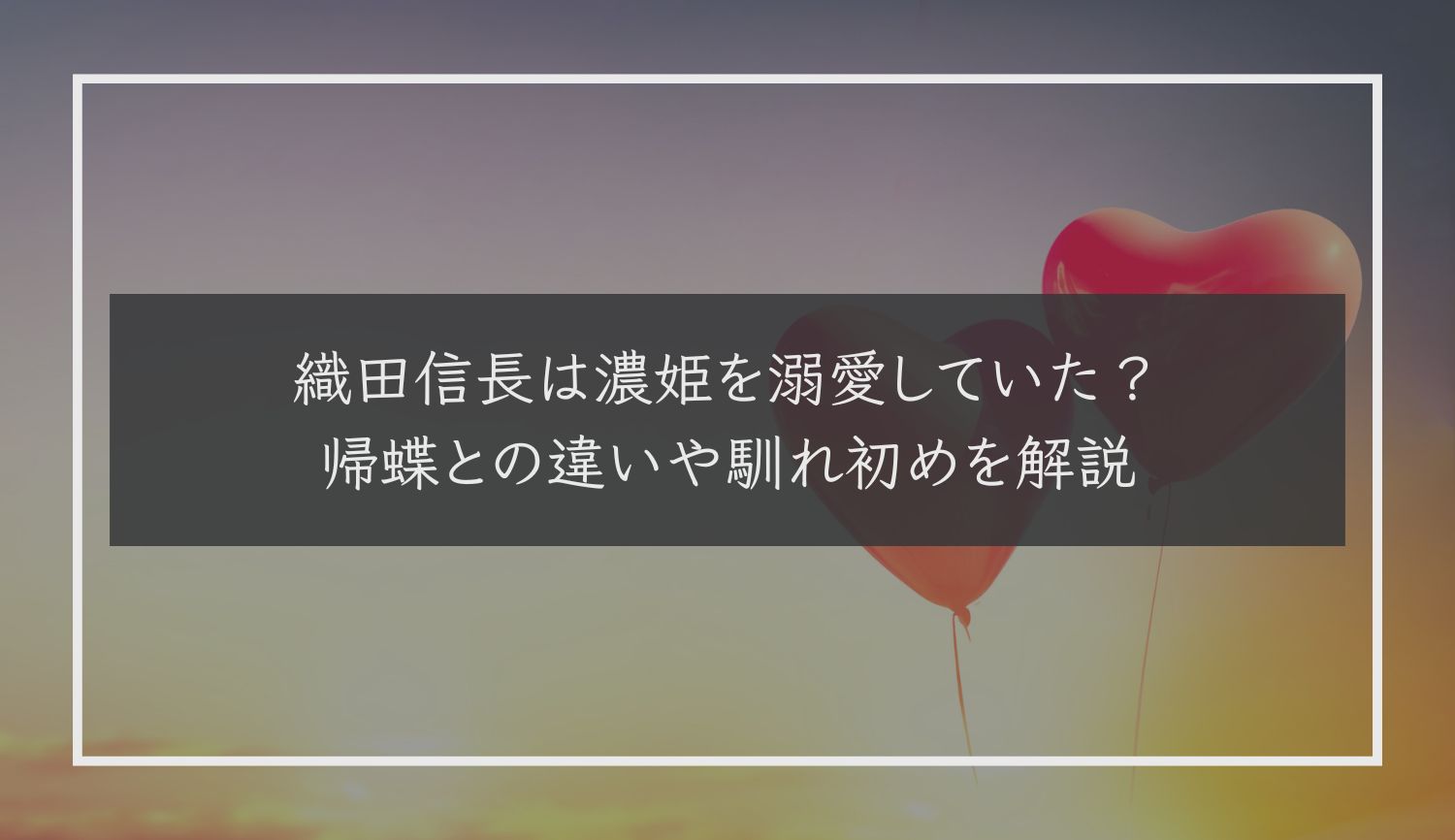戦国時代を代表する武将・織田信長と彼の正室である濃姫(のうひめ)は、日本史に名を残す夫婦として知られています。しかし、二人の関係性については諸説あり、特に「信長は濃姫を本当に愛していたのか」という点は歴史ファンの間でも議論が絶えません。さらに、「濃姫」と「帰蝶(きちょう)」という二つの呼び名が存在することも混乱の一因となっています。本記事では、史実と伝承を丁寧に分析し、信長と濃姫の関係性に新たな光を当てていきます。
濃姫の経歴
濃姫は1535年(天文4年)、「美濃のマムシ」の異名を持つ戦国大名・斎藤道三と正室・小見の方(おみのかた)の間に生まれました。父・道三は油売りから身を興し、策略を駆使して美濃国(現在の岐阜県南部)を掌握した下克上の象徴的存在でした。
注目すべきは、濃姫が若くして複数の結婚を経験していたという点です。史料によれば、織田信長と結婚する前に、彼女はすでに土岐家の二人の男性と政略結婚していたとされています。
土岐八郎頼香、続いて土岐次郎頼純との結婚は、いずれも父・道三の政治的思惑によるものでした。そして驚くべきことに、これら二人の夫は不審な死を遂げており、道三の暗殺という説も存在します。
15歳という若さで二度の夫との死別を経験した濃姫は、1549年(天文18年)、16歳の織田信長と政略結婚しました。この結婚は、長年対立関係にあった斎藤家と織田家の和睦の証として執り行われたものでした。当時、信長は周囲から「うつけ」(愚か者)と呼ばれる型破りな若者でした。「尾張のうつけ」と「美濃のマムシの娘」の組み合わせ——当時の人々はこの結婚をどう見ていたのでしょうか。
織田信長は濃姫を溺愛していた?
信長と濃姫の関係性を示す直接的な史料は驚くほど少なく、その実像は謎に包まれています。しかし、断片的な記録から浮かび上がるのは、一筋縄ではいかない複雑な関係性です。
『絵本太閤記』と『武将感状記』に記された有名なエピソードによれば、結婚して1年ほど経った頃、信長が深夜に出かけて朝方に帰る行動を続けたため、濃姫は浮気を疑いました。
問い詰められた信長は「美濃の家老から連絡を待っている」と説明。これを信じた濃姫が父・道三に密書を送ったところ、実はこれが斎藤家を弱体化させるための信長の策略だったというのです。
一方で、二人の関係が次第に変化していったことを示唆する記述もあります。映画『レジェンド&バタフライ』の解説記事によれば、50歳近い晩年において、病に倒れた濃姫を信長が甲斐甲斐しく看病し、その過程で初めて夫婦らしい関係を築いていったともされています。
信長が濃姫を溺愛していたという説は、史実というよりも後世の創作によって形作られた面が大きいと言わざるを得ません。彼らの間に子供がなかったとされることや、信長に「生駒吉乃」という側室がいたことを考えると、現代的な意味での「溺愛」とは異なる関係性だったと考えるのが自然でしょう。
しかし、濃姫が信長の世界において特別な存在だったことは間違いないようです。信長が自らの事業拡大に濃姫の存在を利用しながらも、彼女を「正室」の地位に保ち続けたという事実は、彼女への一定の尊重を示しているとも考えられます。
織田信長と濃姫の馴れ初め
信長と濃姫の出会いは、典型的な戦国時代の政略結婚の形を取りました。両家の和睦の証として行われたこの結婚には、双方の思惑が絡み合っていました。
斎藤道三は、娘を嫁がせることで織田家の内情を探るスパイとしての役割を期待していたという説があります。実際、道三は濃姫に短刀を持たせ、「信長がなにかたくらんでいたら刀で刺すように」と告げたとされています。これに対し濃姫は「もしかするとあなたを刺すかもしれない」と応じたという逸話も残されており、彼女の強い性格を垣間見ることができます。
小説『身代わり濃姫』の中で描かれるように、二人の初夜には興味深いエピソードがあります。信長が刀を抜いたところ、濃姫は柔道の技で信長を投げ飛ばし、喉元に刀を突きつけたというのです。このエピソードが史実かどうかは定かではありませんが、彼女が単なる従順な妻ではなく、戦いの技術を身につけた武家の娘であったことを示唆しています。
濃姫と帰蝶との違い
「濃姫」と「帰蝶」の違いについては、多くの混乱がありますが、実はどちらも本名ではない可能性が高いのです。「濃姫」という呼び名は、「美濃から来た姫」という意味の通称にすぎません。江戸時代の『絵本太閤記』や『武将感状記』などの創作物によって広まったものです。
一方、「帰蝶」(きちょう)という名前は美濃国の歴史書『美濃国諸旧記』に登場します。しかし、別の史料である『武功夜話』では「胡蝶」(こちょう)と表記されており、「帰」と「胡」の崩し字が似ていることから、どちらかが誤記である可能性も指摘されています。
さらに「安土殿」「鷺山殿」といった別称もあり、彼女の本当の名前は現在も不明のままです。
現代において「濃姫」と「帰蝶」はどのように使い分けられているのでしょうか。一般的には「濃姫」の方が広く知られており、ドラマやゲームなどでもこの名前で登場することが多いようです。
しかし、「帰蝶」という名前も「なんとなく優美な感じがして」好まれることがあり、特に歴史に詳しい人の間では「帰蝶」と呼ばれることもあります。本人の本名が不明である以上、どちらを使っても間違いとは言えない状況です。いずれにしても、同一人物であるというのが共通の解釈です。
まとめ:愛の形はわからない
信長は濃姫(帰蝶)を愛していたのでしょうか?これは単純に答えられる問題ではありません。現代的な「愛」の概念を戦国時代に当てはめることの難しさもさることながら、二人の関係性を直接示す資料が極めて限られているからです。
それでも、いくつかの観点から考察することは可能です。信長と濃姫の関係は、初めは純粋な政略結婚であったとしても、長い年月の中で変化していった可能性があります。信長が彼女を正室の地位に保ち続けたこと、晩年には病床の彼女を看病したとされることなどは、ある種の絆が二人の間に存在したことを示唆しています。一方で、信長には側室がいたことや、二人の間に子どもがなかったという事実は、現代的な意味での「溺愛」とは異なる関係性だったことを示しています。
最終的に、「信長は濃姫を愛していたのか」という問いへの答えは、愛の定義をどのように考えるかによって異なるでしょう。戦国大名としての政治的判断と個人的感情の狭間で、二人がどのような関係を築いていたのかは、今となっては知る由もありません。
しかし、この謎に満ちた関係性こそが、500年近い時を経てなお、私たちの想像力を掻き立て続ける理由なのかもしれません。史実と創作の間で揺れ動く濃姫(帰蝶)の物語は、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。