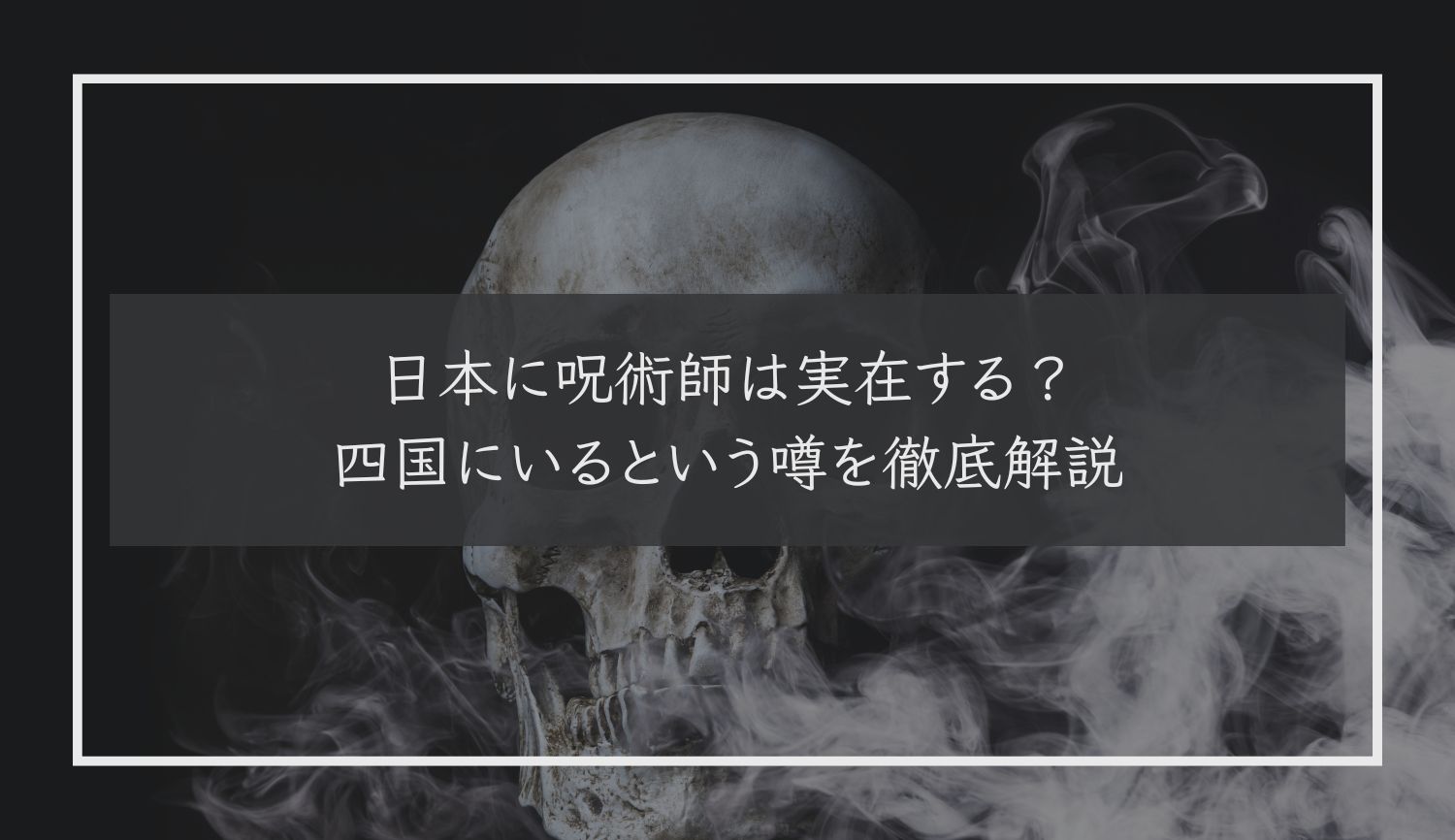古来より日本文化に根付いている呪術。漫画『呪術廻戦』の大ヒットにより、現実の日本にも呪術師は存在するのかという疑問が多くの人の関心を集めています。特に四国地方には現在でも呪術の伝統を守り続ける人々がいるという噂があります。
この記事では、日本における呪術師の実態と、四国の呪術伝統に焦点を当て、その歴史、現状、そして呪術師になる道筋までを詳しく解説します。現代社会に息づく日本古来の霊的実践の真実に迫ります。
呪術師とは?
呪術師(じゅじゅつし)とは、呪術ないし「まじない」を行う者のことで、呪師とも呼ばれます。特に民間治療や病気の診断・治療を中心的な職能としている場合は呪医(じゅい)とも呼ばれています。呪術医は病名の診断にトランスや占いを行ったり、治療に際して治療儀礼を施すことがあります。
呪術師の特徴的な点は、医療効果の根拠を超自然的なものに求めるという点です。現代医学が科学的な根拠に基づいて治療を行うのに対し、呪術師は目に見えない力や精霊、神々の力を借りて病や災いを祓うとされています。
重要なのは、呪術師が必ずしも伝統的な徒弟制度や秘密結社に所属している必要はなく、現代社会においても広く同種業態の活動が行われているという点です。伝統的な呪術師のイメージは「黒魔術」を連想させるかもしれませんが、実際の呪術師の役割は主に「のろい」を祓う「まじない」の方に重きを置いており、人々の不安を取り除く存在として機能してきました。
また、呪術師は卜占(ぼくせん)つまり占いを行う者と区別されることもありますが、多くの場合、呪術的な病気治療を行う呪医がまず占いを行ったり、占いの前に呪文を唱えたりするなど、呪術と占いは密接に結びついていることが少なくありません。さらに、神がかりになる呪術師も伝統社会には存在し、これはシャーマンとも呼ばれます。
日本に呪術師は実在する?
「呪術師は日本に実在するのか?」という問いに対して、2021年12月15日に放送されたフジテレビ系「世界の何だコレ!?ミステリーSP」では、この疑問に真正面から向き合い、日本で現在でも活動している呪術師を取材しています。
番組では、呪術について研究している佛教大学の斎藤英喜教授に取材し、現代日本における呪術師の存在について質問しています。斎藤教授は「呪術師は存在します」と断言しました。特に、戦国時代から呪術を伝えている村が高知県香美市物部町(旧物部村)に存在するとのことです。
ただし、現在ではこの地域の人々は「呪術師」という名称ではなく、「太夫(たゆう)」と呼ばれる人々が陰陽師のような活動をしているとされています。番組では実際に、いざなぎ流太夫の森安正芳さんを取材しました。森安さんは普通の風貌をしていますが、斎藤教授によれば「式神のような術を今でも使う学術的にも非常に貴重な存在」だということです。
実際、日本各地にはこうした民間の「拝み屋さん」と呼ばれる人々が存在しています。彼らは「人を呪わば穴二つ」という言葉がある通り、現代では主に呪いを祓う役割を担っており、人を呪うことはしないと語っています。
こうした呪術的実践は、必ずしも過去の遺物ではなく、現代日本社会の中で形を変えながらも脈々と受け継がれているのです。特に地方に行くほど、こうした民間信仰や呪術的実践が色濃く残っている傾向があります。

呪術師が四国にいる噂は本当なのか?
四国地方、特に高知県や香川県には、古くから呪術的な伝統が根付いていると言われています。高知県の旧物部村(現在の香美市物部町)には「いざなぎ流」と呼ばれる民間信仰が残っており、これは民俗学者の小松和彦氏などがフィールドワークの場にしていたことでも知られています。
いざなぎ流は民間信仰でありながら、陰陽道と修験道が混じったような性質を持っています。「太夫」と呼ばれる呪術師が祈祷を行うとされ、平安時代の安倍晴明のように式神(鬼神)を操るなど、一見おどろおどろしいイメージで語られることもありますが、実態はより地域に根ざした民間信仰の実践者です7。
また、香川県西部(西讃岐)の地域にも、悪いことがあったらお祓いしてくれる「拝み屋さん」のような人々とは別に、町に一人、地域に一人ぐらいの割合で黒魔術師的な、呪い専門の人がいるという証言もあります。これらの人々は「白い蛇の藤憑」を使うと言われており、呪いをかけるときにも一定の「仁義」があるとされています。
四国がこうした呪術的伝統の宝庫である理由として、四国八十八ヶ所の霊場があることや、「管狐」や「犬神」といった呪術使いの伝承が多いこと、そして都からは遠くても完全に孤立しているわけではないという地理的特性が挙げられます。また、安倍晴明は摂津、蘆屋道満は播磨の出身と言われ、熊野修験の影響も受けやすい位置にあることも要因とされています。
いざなぎ流は、近年、安倍晴明の子孫に当たる土御門家の認可を受けていたことが判明したとされています。これは、いざなぎ流が単なる地方の民間信仰ではなく、一定の正統性を持つ呪術伝統であることを示しています。現代の太夫たちは、膨大な祭文(呪文)を唱えながら、地域の人々の不安を取り除く重要な役割を担っているのです。
陰陽師との違い
呪術師と混同されやすい存在として「陰陽師」があります。陰陽師は歴史的には「陰陽寮」という公的機関に属していました。陰陽寮は701年制定の大宝律令に基づき、中務省という中央省庁の管下に置かれた組織でした。つまり、陰陽師は国家公認の職業だったのです。
一方、呪術師はより民間の存在であり、公的な地位を持たない場合が多いという違いがあります。また、陰陽師は占星術や暦の作成、方位の吉凶判断など幅広い任務を担っていましたが、呪術師は主に病気の治療や呪いの祓いなど、より直接的な民間の問題解決に特化していました。
陰陽師が使用する札としては「霊符(れいふ)」または「呪符(じゅふ)」が有名です。これに対し、いざなぎ流の太夫は「御幣(ごへい)」を用いて儀式を行います。
興味深いのは、四国のいざなぎ流が「ある地域で特化した陰陽道」と表現されることもある点です7。これは、地方の民間呪術が中央の陰陽道の影響を受けつつも、地域独自の信仰体系と融合して独自の発展を遂げた結果と考えられます。
陰陽師と呪術師の最も大きな違いは、陰陽師が国家の制度の中に位置づけられた存在であったのに対し、呪術師は常により民衆に近い立場で活動してきた点にあります。この違いは、現代に残る呪術的実践を理解する上でも重要な視点です。
まとめ:まやかしに逃げてはいけない
日本における呪術師の存在は、単なる迷信や伝説ではなく、実際に地域社会の中で機能してきた重要な文化的実践であることがわかります。特に四国地方には「いざなぎ流」をはじめとする伝統が現代まで受け継がれており、地域の太夫たちが人々の不安を取り除く役割を担っています。
現代社会では科学的な世界観が支配的であり、呪術的な実践は「まやかし」や「迷信」として切り捨てられがちです。しかし、こうした伝統的な実践には、単なる迷信以上の文化的・社会的意義があります。呪術的実践は地域の人々の精神的安定や社会的結束を促進する機能を持ち、現代医学では対応しきれない「生きることの不安」に対処する知恵が蓄積されているとも言えるでしょう。
一方で、現代において呪術に過度に依存することや、科学的治療を拒否して民間療法のみに頼ることには危険性もあります。重要なのは、こうした伝統を文化的資源として尊重しつつも、批判的思考を持って向き合うことではないでしょうか。
日本に呪術師は実在するのか――この問いに対する答えは、単純に「いる」か「いない」かではなく、伝統的な呪術の担い手たちが形を変えながらも現代社会の中で生き続けているという複雑な現実にあります。四国の太夫たちに代表される呪術文化は、日本の重要な無形文化遺産として、今後も研究され、記録され、そして尊重されるべき価値を持っているのです