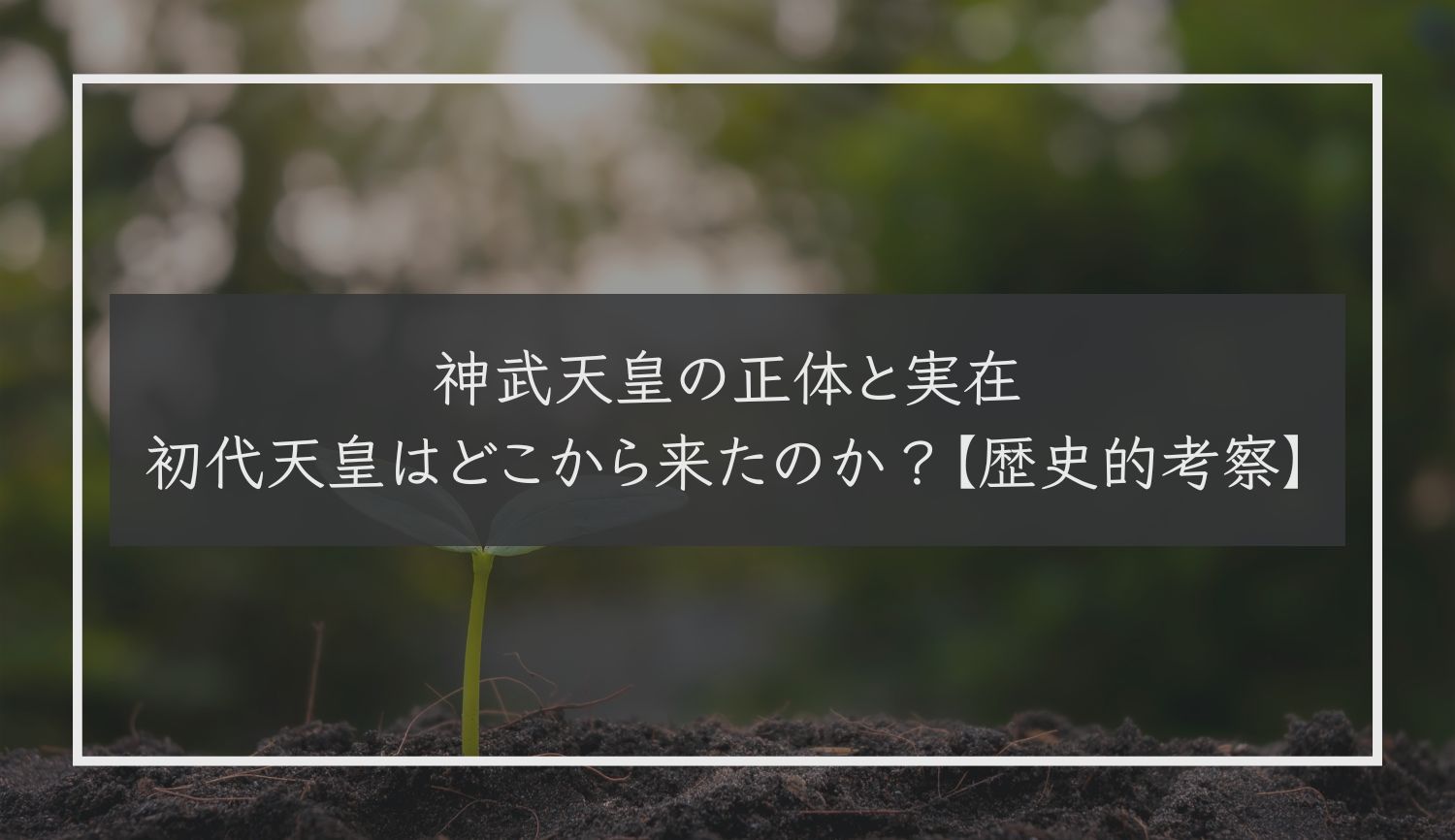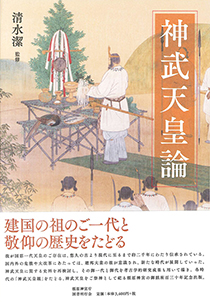日本の歴史書『古事記』と『日本書紀』に記された初代天皇・神武天皇。長い間、実在性についての議論が歴史学者の間で続いてきましたが、近年では新たな視点から研究が進められています。
本記事では、神武天皇の正体と実在の可能性について、最新の研究成果や歴史的視点から多角的に検証します。神話と歴史の境界線に位置する初代天皇の謎に迫り、その出自や東征ルート、現代における意義までを包括的に解説します。
神武天皇とは?基本情報と伝承の世界
神武天皇は、日本書紀によれば紀元前660年に即位したとされる日本の初代天皇です。本名は神日本磐余彦天皇(かむやまといわれひこのすめらみこと)、別名を神倭伊波礼毘古命(かむやまといわれびこのみこと)と呼びます。
彼は日向国(現在の宮崎県)で生まれ、兄弟とともに東方への遠征(神武東征)を行い、大和の地に橿原宮を建てて即位したと伝えられています。伝承によれば127歳まで生きたとされ、その非現実的な寿命からも神話的要素が強いことがわかります。

日本書紀や古事記に描かれた神武天皇像は、建国の英雄として理想化されている側面があります。日向の地から東へと旅立ち、「東のよき地で大いなる国を治める」という志を持って、数々の困難を乗り越えながら大和の国に到達したという物語は、日本創世の物語として今なお人々に語り継がれています3。
この物語は単なる神話ではなく、九州から瀬戸内、そして近畿を結ぶ各地に足跡が残されており、自然、風習、信仰、祭礼といった様々な形で現代に伝えられています。これらは壮大な物語のパズルのピースとして、当時の社会状況や文化的背景を映し出す鏡でもあるのです3。
神武天皇は実在したのか?
古事記と日本書紀に共通して初代天皇と位置付けられている神武天皇ですが、その描写には多くの神話的要素が含まれています。127歳で没したという記述や、金鵄(きんし)が神武天皇の弓に舞い降りたという金鵄伝説など、現実離れした描写が数多く見られます。
しかし、両書に共通して初代天皇と位置づけられていることの意味は重要です。成城大学教授の外池昇氏は「おそらく、いろんな人物の事績や伝説をつなぎあわせて作られた人格だと思いますが、それとても何らかの歴史と考えられます」と述べています。これは神武天皇の存在を単に「架空」と切り捨てるのではなく、その背後にある歴史的実態を探る重要性を示唆しています。
現代の歴史学において、神武天皇は同時代の史料や考古学的資料で存在が確認できないため、歴史上の他の人物と同様の意味では「実在しなかった」と考えるのが一般的です。
しかし近年、この問題に対する視点は変化しつつあります。実は戦後の歴史学界では、神武天皇や神武天皇陵を中心に扱った研究はほとんど見当たりません。これは戦前の「皇国史観」への反動として、神話の時代を日本古代史の範疇に入れない傾向があったためです。
外池昇氏は「神武天皇を否定した上に成り立った日本古代史でありながら、神武天皇をどう見るかという問題にまともに答えてこなかったのは、あまり褒められた態度ではなかった」と指摘しています。
考古学的には、神武天皇の時代とされる紀元前660年頃は弥生時代中期に相当し、当時の日本列島には小規模な集落が点在していた時代です。文字通りの神武天皇が実在したとは考えにくいものの、その伝承が何らかの歴史的事実を反映している可能性は否定できません。皇學館大学の研究者たちによる『神武天皇論』では、考古学的研究成果も参照しながら、神武天皇の生涯と治世を描き出す試みがなされています。
欠史八代とは?初代~10代崇神天皇までの謎
日本の古代史において「欠史八代」と呼ばれる期間があります。これは神武天皇から第10代崇神天皇までの8代の天皇について、具体的な事績がほとんど記録されていない時代を指します。この期間は約600年にも及ぶとされ、歴史的空白期間として知られています。
なぜこのような空白期間が生じたのでしょうか。一つの説として、古代の編纂者が中国の王朝と並ぶ古さを主張するために年代を意図的に遡らせた可能性が指摘されています。つまり、実際の日本の国家形成期と伝説上の建国時期との間にずれが生じ、その間を埋めるために創作された可能性があるのです。
欠史八代の存在は、神武天皇の実在性に関する議論と密接に関連しています。仮に神武天皇が実在したとしても、記紀に記された時代よりもずっと後の時代であったかもしれません。あるいは、複数の歴史的人物や伝承が合成され、理想的な建国の祖として神武天皇像が創り上げられた可能性も考えられるのです。
この問題に対する新たなアプローチとして、記紀の記述を単なる神話として切り捨てるのではなく、その中に埋め込まれた歴史的記憶や政治的意図を読み解くことが重要視されるようになっています。欠史八代を含む初期の天皇系譜は、当時の権力構造や政治的正統性の確立過程を反映している可能性があるのです。
初代天皇はどこから来たのか?
神武東征は、日向国(現在の宮崎県)を出発点として、吉備(岡山県)、大阪、熊野を経て大和(奈良県)に至るルートとされています。この壮大な旅程は、実は現代の文化財政策においても重要な意味を持っています。
2020年には、神武天皇の出立地である宮崎市と終着地である橿原市、そして神武東征の途上に位置する24の市町村が、その道のりを「神武東遷」として文化庁へ日本遺産申請を行いました。申請タイトルは「日本最古の冒険物語『神武東遷』~The first emperor JINMU : Journey to the east~」とされており、この歴史的な旅路を文化資源として活用する試みが進められています。
神武東征のルートに沿った地域には、それぞれ神社や遺跡などの構成文化財が残されています。例えば広島県安芸郡府中町には多家神社が神武東遷のストーリーにまつわる構成文化財として申請されています。こうした各地の文化遺産をつなぐことで、神武天皇の足跡をたどる文化的・歴史的な回廊が形成されつつあるのです。
東征ルートの分析から見えてくるのは、単に神話的な旅路ではなく、当時の人々の移動経路や文化伝播の道筋が反映されている可能性です。実際、考古学的には弥生時代に西日本から東日本へと人々の移動や文化の伝播があったことが確認されており、神武東征の物語はそうした実際の人口移動や文化的膨張の記憶が神話として結晶化したものかもしれません。
最新研究が示す「初代天皇」の起源と可能性
近年の研究では、神武天皇の伝承を単なる神話として捉えるのではなく、歴史学的・考古学的アプローチから再検討する試みが進んでいます。皇學館大学の研究者たちによる『神武天皇論』では、神武天皇の時代を弥生時代と位置づけ、記紀をベースにしつつ考古学的研究成果を参照しながら、その生涯と治世を描き出しています。
この研究では、神武天皇に関する史料を再検討したうえで、考古学的研究成果も用いて描き、さらに各時代の「神武天皇観」をたどることで、歴史上の神武天皇像を立体的に浮かび上がらせています。
神武天皇の正体を考える上で注目すべきは、近年の考古学が明らかにしてきた弥生時代の社会構造です。紀元前1世紀から紀元後1世紀頃の日本列島には、多数の小規模な政治集団(クニ)が存在していたと考えられています。神武東征は、こうした小集団の連合や統合過程を象徴的に表現した可能性があります。
また、DNAや同位体分析などの最新技術によって、弥生時代の人々の移動経路や出自に関する新たな知見も得られつつあります。こうした科学的アプローチと伝承の分析を組み合わせることで、神武天皇の物語の背後にある歴史的実態に迫る可能性が広がっています。
現代における神武天皇・建国記念の日(紀元節)の意義
神武天皇の即位日とされる紀元前660年2月11日は、明治時代には「紀元節」として国家的祝日となりました。現在の「建国記念の日」の起源です。この日付は明治政府によって制定されましたが、その背景には興味深い歴史があります。
明治天皇は神武天皇祭を継承し、明治10年(1877年)の紀元節には神武天皇陵を参拝しました。儀仗兵が整列する中で参拝し、御告文を奏したとされています5。これは近代国家形成期における「建国の祖」への敬意表明であり、新しい国家体制の正統性を古代に求める政治的意図も含まれていました。
神武天皇に対する認識は、時代によって大きく変化してきました。後陽成天皇は「神武天皇より百数代の末孫」と自認し、光格天皇も「百二十代」や「神武百二十世兼仁合掌三礼」という署名を残しています。これは近代以前の天皇たちも神武天皇を初代天皇と見なしていた証拠として注目されています。
特に注目すべきは、孝明天皇が幕末の危機的状況の中で神武天皇陵を整備させ神武天皇祭を制定したことです5。これは単なる伝統の継承ではなく、国家的危機における精神的支柱として神武天皇が位置づけられていたことを示しています。
現代日本における神武天皇の意義は、歴史的実在性の問題を超えて、日本という国家のアイデンティティや連続性の象徴としての側面が強いと言えるでしょう。建国記念の日は、神話と歴史が交錯する日本の複雑な建国過程を考える機会となっています。
神武天皇研究の新たな地平
神武天皇の正体と実在性をめぐる議論は、単に「実在したか否か」という二項対立を超えて、より多面的な研究へと発展しつつあります。戦後長らく避けられてきたこのテーマが、近年になって再び学術的関心を集めるようになったのは、歴史研究のパラダイムシフトを象徴しています。
成城大学教授の外池昇氏は、神武天皇を避けてきた戦後歴史学の姿勢を批判し、「考古学上の発見や、新しい研究手法を受け入れて、それを妨げない範囲で『古事記』や『日本書紀』の歴史も受け入れていいんじゃないか」と提案しています。これは、イデオロギー的な二項対立を超えた、新たな歴史認識の可能性を示唆しています。
神武天皇研究の新たな地平は、文献史学と考古学の協働、また民俗学や神話学などの隣接分野との学際的アプローチにあります。例えば皇學館大学の研究では、古代天皇祭祀・儀礼の史的研究や東アジアにおける日本書紀の位置づけなど、多角的な視点から神武天皇を含む古代天皇制の研究が進められています4。
日本の起源に関わる神話と歴史の境界領域は、これからも多くの新発見や解釈の可能性を秘めています。神武天皇の正体と実在性の問題は、日本の古代史研究における重要なテーマであり続けるでしょう。
まとめ:神話と歴史の狭間に浮かぶ初代天皇の姿
神武天皇の正体と実在性について、本記事では多角的な視点から検証してきました。歴史上の他の人物と同様の意味では「実在しなかった」としても、その伝承が歴史的な記憶や社会変動を反映している可能性は十分にあります。単に「架空の人物」と片付けるのではなく、神話に埋め込まれた歴史的記憶や文化的意義を探る研究が重要なのです。
神武東征のルートやそれにまつわる文化遺産は、神話と歴史の境界に位置する貴重な研究対象です。また、各時代における神武天皇観の変遷は、日本人のアイデンティティ形成や国家意識の展開を映し出す鏡でもあります。
今後の研究では、イデオロギー的な先入観を排し、文献研究と考古学的知見を組み合わせた学際的アプローチが求められるでしょう。神武天皇の伝承は、日本の建国過程や国家形成に関する重要な手がかりを提供してくれるかもしれません。
神話と歴史の狭間に浮かぶ初代天皇の姿は、日本文化の深層を理解する上で欠かせない研究テーマであり、これからも多くの新たな発見と解釈をもたらすことでしょう。